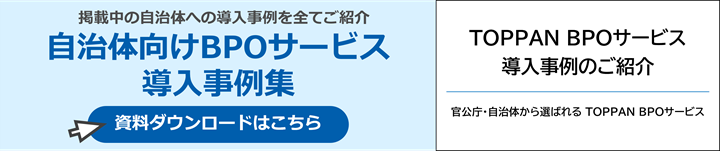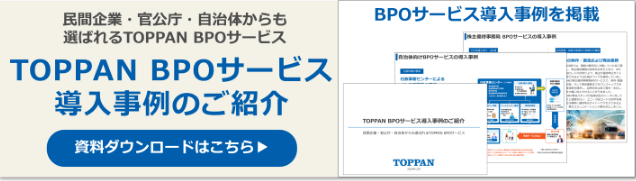補助金・助成金・給付金の
違いと活用法とは
補助金、助成金、給付金の3つは企業経営を支援するための財政手段として、様々な場面で活用されます。また、これらの支援策は、特に中小企業にとって重要な資金源となります。
しかし、これらの用語は混同しがちで、それぞれの特徴や適用条件を正確に把握している方は少ないのではないでしょうか。
本コラムでは、補助金、助成金、給付金の違いについて詳しく解説し、それぞれの特徴と適用条件、さらに活用するメリットについて考察します。
目次
1. 補助金・助成金・給付金とは?
2. 補助金・助成金・給付金の違い
3. 補助金・助成金・給付金の申請・受給にあたっての注意点
4. 企業が活用するメリット
5. まとめ
1. 補助金・助成金・給付金とは?
補助金・助成金・給付金は、いずれも国や自治体から支給される資金ですが、それぞれの定義と特徴には違いがあります。以下にて、詳しく解説していきます。
●補助金の定義と特徴
補助金とは、国の政策目標に沿った事業を行う個人事業主や法人などに対して支給されるお金です。例えば、新しい技術の研究開発や地域活性化プロジェクトなどが対象となります。補助金の特徴としては、以下の点が挙げられます。
選考:多くの場合、補助金は限られた予算内で提供されるため、申請者が選考されます。
目的特化:補助金は特定の目的に対して提供されることが多く、研究開発、設備投資、地域振興など、特定の分野に限定されることが一般的です。
返済不要:補助金は基本的に返済不要ですが、条件を満たさなかった場合や不正があった場合には返還を求められることがあります。
●助成金の定義と特徴
助成金は、主に法人が国の政策目標に沿って労働環境改善や雇用促進などに取り組む場合に支給されるお金です。例えば、従業員の研修費用や教育技術の導入費用が助成金の対象となります。助成金の特徴は次の通りです。
広範な対象:助成金は、雇用促進、教育、環境保護など、様々な分野で提供されます。
条件付き:助成金も一定の条件を満たす必要があり、その条件を満たせば受給が可能です。
返済不要:助成金も基本的には返済不要ですが、条件を満たさなかった場合や不正があった場合には返還を求められることがあります。
●給付金の定義と特徴
給付金とは、国や自治体が個人や事業者などに向けて支給するお金です。給付金は、特定の条件を満たす場合に支給されることが多く、例えば、災害時の生活支援や育児支援などが対象となります。給付金の特徴は以下の通りです。
対象者:給付金は、災害被災者、低所得者、特定の業種など、特定の条件を満たす個人や企業に対して提供されます。
申請手続きの簡略化:給付金は、迅速に支給されることが求められるため、申請手続きが比較的簡略化されていることが多いです。
返済不要:給付金も基本的には返済不要ですが、条件を満たさなかった場合や不正があった場合には返還を求められることがあります。
2. 補助金・助成金・給付金の違い
続いて、補助金・助成金・給付金の違いについてより詳しく解説します。
●申請プロセスと条件
1.補助金
補助金の申請プロセスは、まず公募情報を確認し、申請書類を作成して提出します。審査が行われ、合格した場合にのみ支給されます。審査基準は厳しく、競争率も高いことが多いです。条件としては、詳細な事業計画の提出や、特定の技術やプロジェクトに対する具体的な成果が求められます。
2.助成金
助成金の場合、申請プロセスは比較的簡単で、条件を満たせば受給できる可能性が高いです。例えば、雇用促進助成金の場合、新たに従業員を雇用することや、研修を実施することなどが条件となります。申請書類も簡素で、審査も迅速に行われることが多いです。
3.給付金
給付金の申請プロセスは最も簡単で、基本的には必要な情報を提出するだけで受給できます。例えば、災害時の給付金の場合、被災証明書や身分証明書を提出するだけで支給されるケースもあります。条件も緩やかで、迅速に支給されることが多いです。
●受給額と用途の違い
1.補助金
補助金の受給額は、プロジェクトの規模や内容によって大きく異なります。大規模なプロジェクトの場合、数百万円から数千万円に及ぶこともあります。用途は厳格に定められており、事業計画に沿った使途でなければなりません。
2.助成金
助成金の受給額は、補助金に比べて比較的小規模であることが多いです。例えば、雇用促進助成金の場合、1人当たり数十万円程度が一般的です。用途も指定されていますが、補助金ほど厳格ではありません。
3.給付金
給付金の受給額は、生活支援や災害支援が主な目的であるため、比較的小額であることが多いです。例えば、災害時の給付金の場合、数万円から数十万円程度が一般的です。用途に対する制約も少なく、自由に使うことができます。
3. 補助金・助成金・給付金の申請・受給にあたっての注意点
続いて、補助金・助成金・給付金の申請・需給にあたっての注意点を解説します。
●補助金申請・受給の注意点
補助金は採択枠が限られ、審査競争が激しいため「いかに評価ポイントを押さえて事業計画を作り込むか」が最大の注意点です。公募要領を熟読し、①課題の明確化と解決策の具体性、②数値目標・KPIの妥当性、③地域経済や社会課題への波及効果など、評価項目に直結する要素を過不足なく盛り込みます。また、採択後は「実施内容・支出内容が計画どおりか」を証憑で証明する義務があり、領収書・発注書・見積書などは原則5年間以上の保管が必要です。実績報告が遅れたり、経費区分を誤ると交付取消・全額返還のリスクがあるため、経理部門と連携した記帳・証憑管理体制を事前に整えておきましょう。
●助成金申請・受給の注意点
助成金は「要件を満たせば原則受給できる」制度が多い反面、対象経費や人事労務の運用ルールが細かく定められています。特に雇用関係助成金では、①就業規則・労働条件通知書の整備、②賃金台帳・出勤簿・タイムカードの整合性、③社会保険・労働保険の適正加入が必須です。書類の不備や従業員への未払い残業代が発覚すると不支給だけでなくペナルティ(2年間申請不可等)が科される場合もあります。申請書の提出先がハローワーク、労働局など複数にまたがるケースも多いので、スケジュール管理と窓口確認を徹底しましょう。
●給付金申請・受給の注意点
給付金は災害・コロナ禍など緊急時の資金繰り支援として設計されることが多く、「申請期間が短い」「電子申請のみ対応」などスピード感が鍵を握ります。申請時に提出した売上台帳や確定申告書に誤りがあると給付遅延や不支給となりやすいため、①数字の整合性チェック、②添付データの規格・ファイル形式の確認、③代表者名義の銀行口座情報のミス防止がポイントです。また、虚偽申請が厳罰化されており、後日の追加資料提出要請や税務署・金融機関とのデータ照合に耐えられる証拠を保管しておく必要があります。受給後に条件変更(休業要請の対象外転換など)があった場合は速やかに事務局へ報告し、過大受給は自主返納する姿勢が求められます。
4. 企業が活用するメリット
続いて、企業が活用するメリットについて解説します。
●資金調達の多様化
補助金・助成金・給付金は返済不要の資金源であり、企業の資金調達手段として非常に有効です。これにより、以下のような利点が得られます。
資金の確保:銀行融資や自己資金だけでは賄いきれないプロジェクトや事業に対して、補助金や助成金を活用することで、必要な資金を確保することができます。
リスク分散:多様な資金調達手段を活用することで、企業の財務リスクを分散させることができます。例えば、銀行融資に依存することなく、補助金や助成金を活用することで、返済義務のない資金を確保することができます。
成長機会の拡大:補助金や助成金を活用することで、新たな事業やプロジェクトに挑戦する機会が増え、企業の成長を促進することができます。また、公的な支援を受けることで、取引先や金融機関からの信頼が増し、ビジネスチャンスが広がる可能性があります。
●財務健全性の向上
補助金・助成金・給付金を活用することで、企業の財務健全性を向上させることができます。具体的には、以下のような効果が期待できます。
自己資本比率:補助金や助成金は返済不要な資金であるため、自己資本比率に悪い影響を与えることはありません。これにより、企業の財務基盤が強化され、信用力が向上します。
キャッシュフローの改善:補助金や助成金を活用することで、キャッシュフローの改善が期待できます。特に、設備投資や研究開発などの大規模な支出に対して補助金を活用することで、キャッシュフローの圧迫を防ぐことができます。
5.まとめ
補助金・助成金・給付金は、それぞれ異なる目的と条件に基づいて提供される財政支援策であることが分かったかと思います。
各支援策の特徴を理解し、自社の状況に最も適したものを選ぶことが、経営の安定と成長に繋がるでしょう。今後も最新の情報を収集し、適切な支援策を活用することが重要です。
最後に、TOPPANでは自治体様をはじめ、多種多様な業種・業界の企業様のご希望に沿ったBPOサービスのご提供が可能です。
また、デジタルとアナログを両立したご支援が可能なため、給付金の申請や問い合わせ対応といったアナログな行政事務を代行しつつ、ITツールやチェックシステムを活用した窓口業務やWeb申請の受付処理といったデジタル化のご支援を行うことも可能です。
TOPPANはノンコア業務をアウトソースしていただくだけではなく、各自治体・企業様のニーズに応じた業務体制の構築や効率化を推進いたします。ご用命の際には、お気軽にお問い合わせください。
自治体向けBPOサービス関連コラム
2026.01.23