『共創型』で現場の課題を解決!
『クラシラセル®』がつくばスーパーサイエンスシティ構想実現のための
住民向けポータルアプリの開発を支援
日本百名山の一つ『筑波山』を擁し、近辺は筑波山地域ジオパークに認定されるなど豊かな自然に囲まれる茨城県つくば市。一方で、科学技術の拠点都市『筑波研究学園都市』として多くの実績を残してきており、約2万人の研究従事者を有する国内最大のサイエンスシティにまで発展した。また、政府から『スーパーシティ型国家戦略特別区域』として指定。住民のつながりを力にして、大胆な規制改革とともに先端的な技術とサービスを社会実装することで、科学的根拠をもって人々に新たな選択肢を示し、多様な幸せをもたらす大学・国研連携型スーパーシティの実現を目指している。
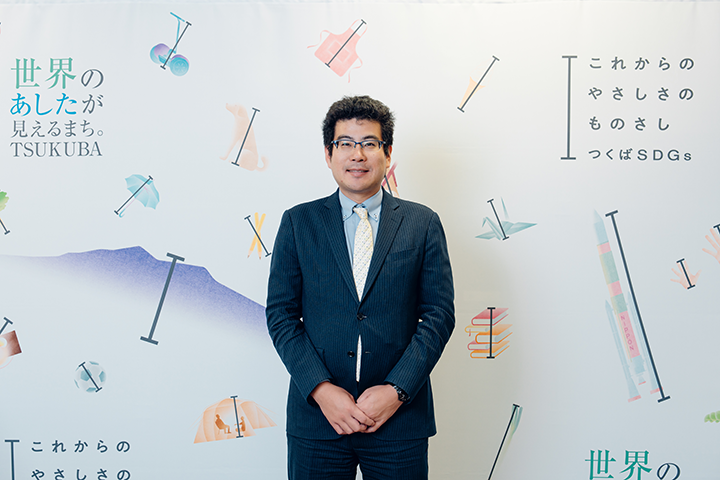
同市はスーパーサイエンスシティ実現のための独自構想を策定しており、その実現のために欠かせなかったのが『住民向けのポータルアプリ』だ。どのようなコンセプトの下、具体的にどうアプリ開発を進めていったのか、また、同アプリを開発したことで何が実現できたのか、政策イノベーション部長 髙橋 安大氏にお話を伺った。
多言語ポータルアプリによってつくば市独自の課題解決を目指す
最先端のテクノロジーを活用した新たな住民サービスの選択肢
『つくばスーパーサイエンスシティ構想』
2022年4月 に内閣府から『スーパーシティ型国家戦略特別区域』に指定されたつくば市は、現在『最先端のテクノロジーを活用して人々に新しい選択肢を与えて幸せになってもらおう』のコンセプトの下、さまざまな取り組みを始めている。そして同市が独自に策定したのが『つくばスーパーサイエンスシティ構想』(以下、『つくばSSC構想』)だ。
「『つくばSSC構想』は、特定の分野に限らずさまざまな分野で、最先端テクノロジーを活用して住民サービスに新しい選択肢を与えることを目的としています。 ‟行政” ‟移動” ‟物流” ‟医療・介護” ‟防犯・防災・インフラ”の合計5つの分野を対象にしています」。髙橋氏は『つくばSSC構想』の全体像をこう語った 。
つくば市は同構想の下、最先端技術の社会実装と都市機能の最適化を進め、住民参加や住民と行政のつながりを深めながら、社会課題の克服や生活環境の革新的な改善を目指している。
つくば市特有の課題解決を目的に『つくスマ』を開発
『つくばSSC構想策定』に至る背景には、同市が抱える独自の課題を最先端技術によって解決しようという意図もあった。
「まず1つ目の課題が、地域の格差が広がっているということ。当市の人口は増加していますが、人口が大きく増加している都市部とその他の地域との二極化が徐々に顕著になりつつあります。2つ目が、街づくりを考える上で外国人の割合が高いということを考慮しなければならない点です。研究学園都市にふさわしく教育・研究機関が多数存在し、多くの国から研究者が集まっていることがその背景にあります。3つ目が、市民の方が研究学園都市としてのメリットをそれほど感じていないという調査結果が出ており、研究学園都市としての存在意義をもう一度問い直す必要が生じていることです。さらに、近年のインフラ老朽化の問題も存在します」と、髙橋氏はつくば市特有の課題 を述べた。
今回つくば市が提供を開始した市民向けの多言語ポータルアプリ『つくスマ』は、同構想内に『多言語ポータルアプリ』として謳われている。行政分野における先端的サービスとして、多言語で情報発信することなどを目的としたスマートフォンアプリだ。その他にも、最新情報を分かりやすく提供したり、属性や希望に応じた情報をプッシュ通知したりする機能が搭載されている。さらに、このアプリを通じて行政手続きDXやインターネット投票、さらにビッグデータ活用につなげようとするビジョンも描かれている。
「喫緊の課題は、『多言語対応』でした。在住する外国人の方の国籍はおそらく140カ国以上で、これだけ多くの言語に対応しようとすると、市職員のマンパワーでは限界があります。また、先ほど二極化についてお話しましたが、現在市役所本庁の他に7か所の窓口センターを設けて市民の方に対応しています。しかし、そこまで足を運びにくいという方もおられます。そのような方々に対しても、迅速かつ確実に市の情報をお届けし、将来的には各種申請なども直接行えるような多言語ポータルアプリが必要だと判断し、『つくスマ』の開発を決定しました」と、髙橋氏は『つくスマ』開発の経緯を振り返った。
『共創型』アプリケーション開発で本当に役立つアプリを

『つくばSSC構想』を進めるにあたっては、行政の力だけはやはり限界がある。そこで、最先端の技術を有する研究機関や教育機関、民間企業などの協力を得て『みんなでつくばを変えていく』ことを目指し『つくばスマートシティ協議会』を設立した。同協議会では行政からのニーズに対して技術的にどのような形で実現可能か、また、民間企業の視点でビジネスとして育てていくことはできるのかなどを検討。さらに、実証実験から実装フェーズへの取り組みも進めた。
「最終的にTOPPANさんに協力を求める決め手になったのは次の2点でした。まず、1点目は既にサービスとして存在しているアプリありきではなく、市側のニーズをくみ取りながら我々と一緒にアプリを作り上げていく『共創型』で臨んでいただけることです。どのように開発していけば良いのかを相談しながら進めていくことがきるのが非常に頼もしかったですね。2点目が『拡張性』です。既存のサービスやアプリをベースにすると、どうしても機能などに制限があります。今後さまざまなことにチャレンジしていく可能性がある為、技術的に実現不可能な状況はできるだけ避けたいという考えがありました」と、髙橋氏はTOPPANの『共創型』での取り組みなどを評価した。
各担当課と協力関係を築きながらスムーズに開発を進める
住民向けポータルアプリで重要となるのが、どのような情報を掲載するか、つまりその『内容』だ。情報が不足していたり、役に立たないものばかりでは活用は進まない。そしてその内容や情報を握っているのは、実際に市の事業を担っている各担当課だ。従って、担当課の理解と協力がなければ良いものは生まれない。
「どこの組織でも同じだと思いますが、新しい取り組みに対してはまず警戒されてしまいます。そこで先ほどの『共創』というキーワードが重要になってきます。アプリ開発などでは、我々が仕様書を作成してそれを基にベンダーさんに発注するのが一般的な方法です。しかし、この方法だと、実現したい機能とそれを実現するための技術的な課題を別々に考える必要があり、各担当課の細かなニーズに応えていくのは難しくなります。TOPPANさんの場合は、我々と一緒になって動いてくれたことで、各担当課が持つ要望や疑問にタイムリーに対応することができました。技術的な解決方法もその場で提案でき、担当課とうまく協力関係を築きながら非常にスムーズに開発を進めることができました」と、 髙橋氏は開発時のポイントを説明した。
『つくスマ』が“つくばらしい“利便性の高いサービスを提供

『つくスマ』で現在最も重宝されているのが、市からの情報を確実に伝えることができる『プッシュ通知』機能だ。アプリインストールの際に自分の興味や関心のある分野を選択するようになっており、その分野の情報がプッシュ通知される仕組みだ。具体的にはイベント情報や防災情報などさまざまなものが含まれる。
「自治体が発信する情報は、住民の方がその都度必要な情報を探し出して確認するという方法が一般的です。住民の方に確実に情報を届けるためには情報の伝達方法が重要で、個別に情報がプッシュされてくる方法は非常に有効です。当市では各事業課から情報発信する際には、『つくスマ』のプッシュ通知が第一の選択肢になっています」と髙橋氏は語った。
地域格差・二極化などの課題解決に有効な『地域マップ』の活用も進んでいる。つくば市内では移動スーパーが活躍しているが、交通事情などによって予定どおりに移動できない場合もある。地域マップ機能を使って移動スーパーの現在位置を表示するようにしたことで、スマートフォンさえあればどこからでも状況が確認できるようになった。その他にも次のような独自施策を展開している。
「五十嵐つくば市長 の思い入れが大きく、『つくばSSC構想』の中でも謳っている『インターネット投票』の仕組みを整えました。最終的には公職選挙で活用したいのですが、現状では法的な制限があります。しかし、市民の皆さんに実際に触れてもらってインターネット投票がどういうものなのか、考えるきっかけにして欲しいと思い模擬投票をこれまで2回実施しています。1回目がつくば市の美しい風景を『映えスポット』として募集し、気に入ったものを投票してもらうもの。2回目がインターネット投票の仕組みを使って市長の行政評価を市民の皆さんにしてもらい、それを基に退職金を決めるというものでした」と、髙橋氏は独自の取り組みについて説明した。

『つくスマ』開発の成果を活かした『クラシラセル®』サービスを一般提供開始
市行政の面では、情報をタイムリーに提供できる文化 が根付いたことが一番の効果だと言う。もちろんこれにより市民の方もいち早く確実に情報を入手できるようになる。リアルタイムで位置情報を共有できる地域マップなど、今まで無かったサービスを利用できる点も導入効果として大きい。TOPPANは、今回の『つくスマ』開発の成果と知見を活かして、他自治体でも『共創型』で住民向けアプリを開発できる『クラシラセル®』というSaaS型サービスの提供を始めた。自治体がこれを使ってアプリ開発する際のメリットについて髙橋氏は次のように語った。
「やはり『カスタマイズ性』が非常に大きいのではないでしょうか。既存のアプリをカスタマイズする場合、どうしても思うようなアプリができず、物足りなくなってもう1度作り直すというようなことも発生します。そうすると住民の方の期待値も徐々に下がってきてしまう。重要なのは、将来発生する市民の方の要望や新しいテクノロジーを取り込みながら、長期的な視点で進めていけるようなカスタマイズ性や拡張性を有していることでしょうね。もちろんその際には『共創型』で開発を進めていくことが成功の秘訣にもなります」。
「つくばに住んで良かった!」と感じてもらえるようなサービスを作っていきたい

『つくスマ』を通じて市民との接点を強化しながら、新たなサービスを提供してきたつくば市だが、スーパーサイエンスシティへの取り組みはもちろんこれで終わりではない。
「位置情報や画像を使って市民の側から情報発信・共有できる『つくレポ』という機能があります。今後はこの機能を使って市へさまざまな情報を発信してもらうことで、より暮らしやすい環境を作り上げていくことができないか検討しています。例えば街路灯が消えている場所を画像と位置情報を合わせて送っていただくと、即座に状況と場所が把握でき、修理に向かうことができます」と、髙橋氏は今後のつくスマ活用の方向性を示した。
その他にも、多言語化の推進や地域マップの拡充、データ連携基盤を活用したデータ統合による市内のサービス連携などによりさらに『つくスマ』の利用価値を向上させていく。
「すこし抽象的かもしれませんが、『それってつくばにしかないよね』『つくばに住んで良かったね』と感じてもらえるようなサービスを作りたいという思いがあります。その入り口にあるのは常に『つくスマ』であり、むしろそうあるべきだと考えています」と、髙橋氏は思いを語った。
つくば市 五十嵐市長からコメントを頂戴しました
 つくば市 市長
つくば市 市長五十嵐 立青(いがらし たつお)氏
つくば市は、科学のまち という特性を活かし、「科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せを」というスローガンのもと、スーパーシティ構想の実現に向けた取り組みを推進しています。私が本部長を務め、特別職・アーキテクト・庁内全部局長で構成される「つくば市スーパーシティ型国家戦略特別区域推進本部」が中心となり、‟行政” ‟移動” ‟物流” ‟医療・介護” ‟防犯・防災・インフラ”といった各分野で先端技術の実装を進めています。
その中でも、特に行政分野の情報発信やサービス提供は、これまで画一的かつ一方的になりがちでした。当時、住民の皆さんから寄せられた声が、今も強く印象に残っています。
「自分に必要な行政情報をホームページから探し出せない」「外国人にとってはゴミの捨て方すらわからない」これらの声を受け、一人ひとりに必要な情報をプッシュ型で届ける重要性を改めて認識しました。
そこで誕生したのが、TOPPANさんと共創した『つくスマ』です。これは行政が一方的に作るアプリではなく、住民とともに創るアプリ。TOPPANさんの協力があったからこそ、実現できた取り組みです。今後も、新機能の追加や既存機能の改善を重ね、より使いやすく便利なアプリへと進化させていきます。『つくスマ』が、つくば市のスマートシティ化を加速させ、市民の生活をより豊かにすることを期待しています。
最後に
TOPPANでは、自治体様の課題に一緒に向き合い、それぞれの自治体様に最適な住民ポータルサービスを提供いたします。是非、お気軽にTOPPANへお問合せください。
TOPPANデジタルのソリューションのご紹介
お客さまのビジネス変革と持続的な発展をサポートするため、さまざまなデジタルソリューションを提供しています。下記画像をクリックし、その他のソリューションもご覧ください。
つくば市役所様インタビューコラム
下記画像をクリックすると、つくば市役所様のインタビューコラムが無料ダウンロードできます。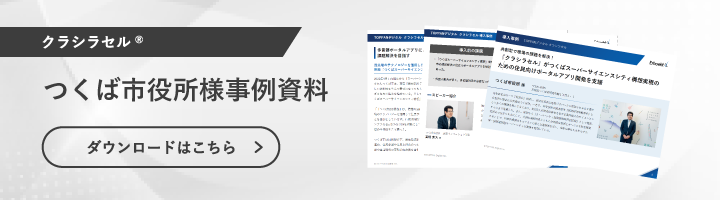
2025.03.03











