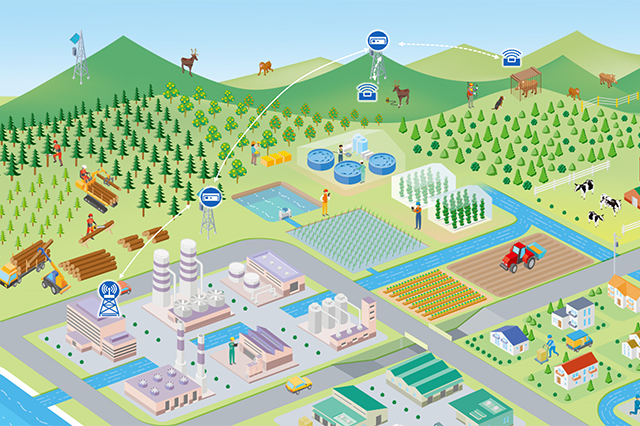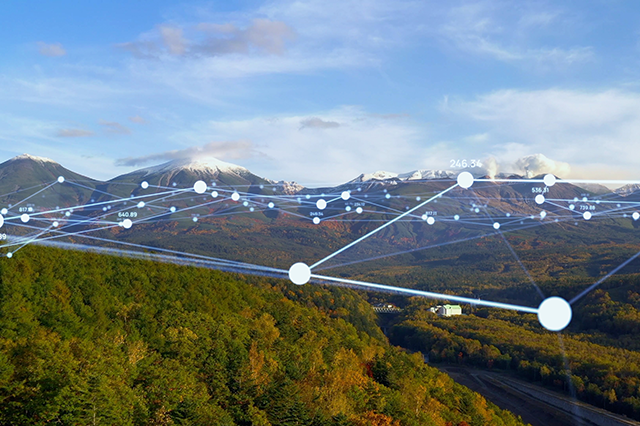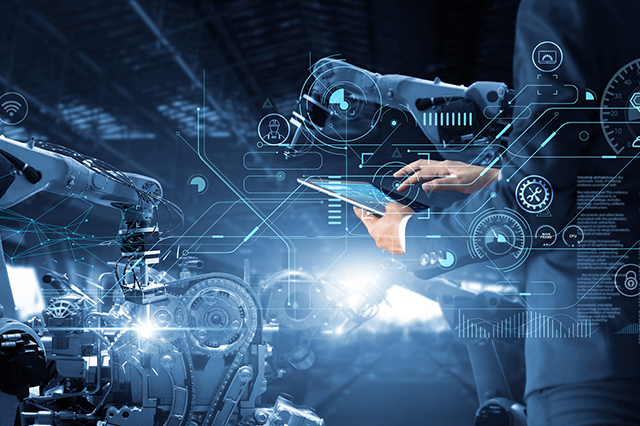インフラ老朽化が深刻に!
IoT活用による対策とは?
近年、インフラの老朽化問題が世界的に広がっており、喫緊の課題となっております。さまざまな解決方法が進められている中で、IoTをはじめとしたICT技術の活用は有効な方法の一つです。
本コラムでは、インフラ老朽化の課題と解決策、インフラ老朽化へのICT技術活用による対策やIoT対策事例をご紹介します。
インフラ老朽化の課題とは?
インフラ老朽化の課題は近年深刻化しています。その現状と背景をみていきましょう。
●インフラ老朽化とは
インフラとは、社会基盤や生活基盤となる電気・ガス・石油などのエネルギー供給施設や港湾・ダム、通信、水道、学校・公園・医療機関などの施設、鉄道・高速道路などの交通機関などを指します。主に1950~60年代の高度成長期に構築されたそれらの設備や施設の老朽化が進んでいます。
老朽化によって生じるリスクとして、災害による大きなダメージや、経年劣化による故障や不具合によってインフラが正常稼働しなくなることが挙げられます。インフラは人々の暮らしを支える基盤であることから、老朽化は大きなリスクをもたらします。
インフラ老朽化は、日本のみならず世界的に起きている問題であり、そのリスクについても多数指摘されています。
●インフラ老朽化の背景
日本においては、インフラ老朽化の大きな背景として、耐久年数の問題があります。高度成長期によるインフラの構築から約60年ほど経過した現在、経年劣化による不具合は避けられなくなっています。
●インフラ老朽化の課題
・修繕や維持管理にあてる財源不足
インフラの修繕には数兆円にも上る費用がかかるといわれています。これらの財源不足が懸念されており、不具合が起きてからの修繕という考え方を改め、予防保全を進める必要が出てきています。
・技術系人材不足
国内の少子高齢化による人手不足を背景としたインフラ業界における技術系職員の減少に伴い、インフラ施設を管理する高いスキルを持つ人材が不足しています。そのため、技術系人材を新たに雇い入れることだけでなく、人材教育を視野に入れる必要性が増しています。
インフラ老朽化の解決策
日本においては、次のことが老朽化の取り組みとして進められています。
●長寿命化
インフラの寿命を延ばす試みが進んでいます。日本では2014年5月に国土交通省による行動計画「インフラ長寿命化計画」を皮切りに、2021年には「第二次インフラ長寿命化計画」が公表され、取り組みが進められています。この計画では、官民連携により新しい技術を用いることが検討されています。

●予防保全によるコスト削減
維持管理費を捻出することは大きな課題であることから、事後保全から予防保全へのシフトをはかり、インフラ維持管理費の支出を可能な限り少なくするコスト削減の方向へと進められています。

●インフラストックの適正化の促進化
インフラを更新する際に、ただ更新するのではなく地域のニーズや将来的なまちづくりも考慮に入れ、インフラ施設を適宜見直して再編・集約を図るなど適正化を図っていく計画も進められています。

●メンテナンス作業の生産性向上の取り組み
インフラのメンテナンス作業については、適切かつ効率的な作業の促進による生産性向上のために、人材育成の推進や新技術を積極的に取り入れる施策およびデータベースの整備が求められています。

●ICTの活用
ICT(情報通信技術)の活用促進も重要になっています。例えばIoTによってインフラ設備にセンサーを設置し、状況を遠隔から監視したり、AIによってデータを分析してリスク判断を行ったりすることが考えられます。
これらのICT技術の活用は人手不足や生産性向上にも寄与するため、大きな期待がかかっています。

インフラ老朽化へのICT技術活用による点検への対策
インフラ老朽化に対する課題解決策の一つに、ICT技術の活用が期待されていますが、点検分野においては次の技術を用いた対策が挙げられます。
●IoTによるインフラ点検・制御
IoTとはモノのインターネット(Internet of Things)を指します。センサーなどを通じて現地や機械設備の状況を情報取得し、インターネットを通じて通信を行い、機械設備の自動操作や制御、データの見える化、監視などを実現する技術です。
前述の通り、IoTはすでにインフラ監視に役立てられており、省人化や生産性向上につながるため、今後もインフラ老朽化対策として重要な役割を担っていくでしょう。
またインフラ設備や施設は人里離れたインターネットがつながらない地域にも多く設置されていることから、インターネット以外の通信技術の活用や開発も期待されています。
IoTデバイスにおいては近年、サイバー攻撃のリスクが高まっていることもあり、インフラ点検・制御で活用する際にも、万全のセキュリティ対策が求められます。
●AI・RTK測位によるリスク検知
AI(人工知能)を用いることで、大量のデータを学習してリスクのあるパターンを検出したり、画像診断によってインフラ設備や施設の劣化のリスクを検出したりすることが可能になります。
またRTK(Real Time Kinematic)という人工衛星を用いる位置情報取得を実現する技術を用いることで、高精度に測位できることから、ドローンなどの操作に活用されています。
ドローンについては、特にインフラ点検への活用が進んでおり、インフラ施設を空中からカメラ撮影をして、画像や映像によって点検やトラブル予測などを行う手法が取られています。ドローンを活用すれば人が遠隔地へ出向いたり、足場を組んだりしなくて済むようになることから、人手不足対策や高所の危険作業の低減につながります。
インフラ老朽化へのIoT対策事例
インフラ老朽化に対して、IoTを用いて対策を行った事例をご紹介します。
●橋などの公共構造物・公共施設の変位検知
橋などの公共構造物や公共施設では、クラックと呼ばれるひび割れや位置の変化などの変位を迅速に把握することで、未然に大きな不具合を避けるための処置を行うことができます。
IoTを活用して定量的なデータを取得することによって、対象物の劣化状況を検知し、日常点検を効率化する試みが行われています。取得したデータはインターネット経由で送られることから、PCはもちろんのこと、スマートフォンでも確認できるため、わざわざ現地に出向く工数やコストを削減できます。
●LPWA「ZETA」活用による河川の水位監視
「ZETA(ゼタ)」というLPWAを用いたインフラ管理の事例があります。LPWAとはLow Power Wide Areaの略称で、少ない電力で広範囲に通信可能な無線通信技術です。ZETA はLPWAの規格の一つであり、数多くの中継器を設け、通信をつなげることによって通信しにくい場所にも低コストで通信エリアを拡大できる特長を持ちます。
TOPPANでは、ZETAを河川などの水位や雨量を監視するIoTソリューション「スイミール®︎」を提供しています。スイミールは遠隔地にある河川に設置したセンサーを通じて、リアルタイムでデータを収集し、情報統合プラットフォームを通じて可視化します。そのセンサーからサーバーまでの通信にZETAを使用しています。
ZETAは山間部などの通信インフラが整っていないエリアにおいても通信を可能にすることから、インフラ管理に役立てることができます。今後、日本全国にある通信しにくいインフラ設備に対しても、ZETAとIoTの活用が期待されます。
●老朽化したアナログメーターの自動検針
インフラ設備のIoT化を阻む大きな要因の一つに、アナログメーターの監視があります。アナログメーターは検針した情報をデジタル化する必要があるため、IoT化は容易ではありません。またインフラ設備のある遠隔地ではネットワークが確保できないことも多くあります。
これらの課題を解決するTOPPANのスマート点検支援サービス「e-Platch™」 では、自動検針が可能になる技術とZETAを用いることで、アナログメーター監視のIoT化と点検の効率化を実現できます。
当サービスでは、アナログメーターにマグネットホルダーと磁気センサーで角度情報を計測し、デジタル化することで遠隔自動検針を可能にします。さらにデータ変換機器「ZETABOX™」を用いて、計測器から出力されるデータをデジタル化し、ZETAネットワークに転送することで、遠隔からのデータ確認、点検が可能になります。
まとめ
インフラの老朽化対策として、さまざまなアプローチ方法が採用されています。その中でもICT技術の活用は設備点検をはじめとしたリスク対策に役立てられます。
TOPPANでは、M2MとIoTを組み合わせ、ZETA通信を利用することで山間部など電波の届きづらい場所においての監視・点検業務の効率化を実現しています。今回ご紹介したリモート水位監視ソリューション「スイミール®」、スマート点検支援サービス「e-Platch™」のほか、遠隔獣害対策「リモワーナ®」も提供しています。
ぜひ、ZETAを活用したTOPPANのIoT技術をご検討いただければ幸いです。
お客さまのビジネス変革と持続的な発展をサポートするため、
さまざまなデジタルソリューションを提供しています。
下記画像をクリックし、その他のソリューションもご覧ください。


2024.12.10