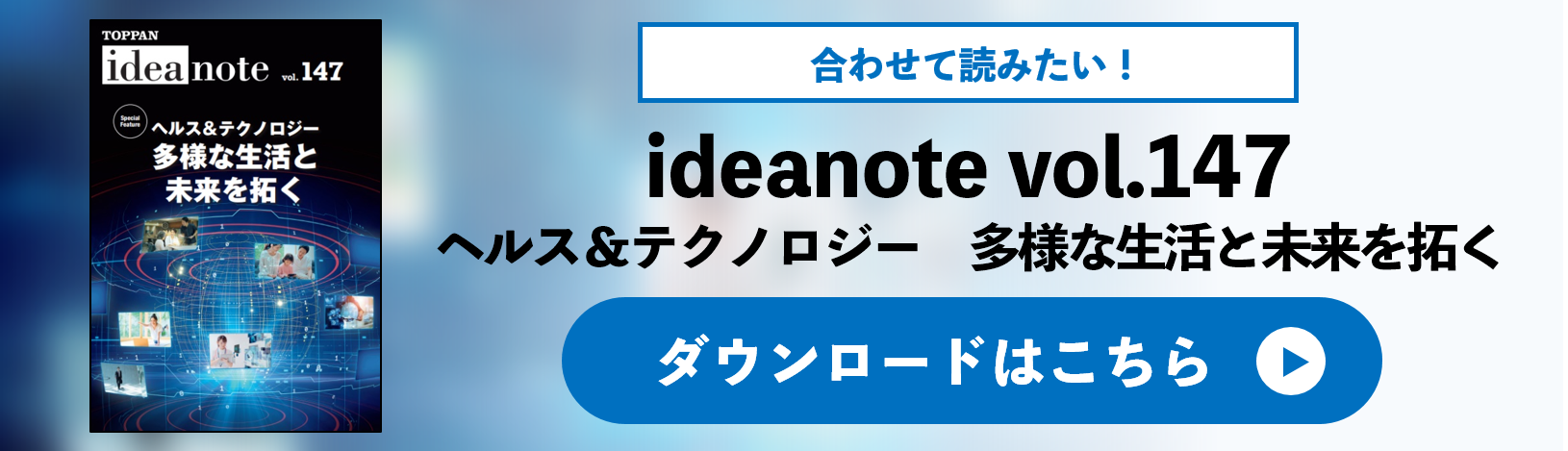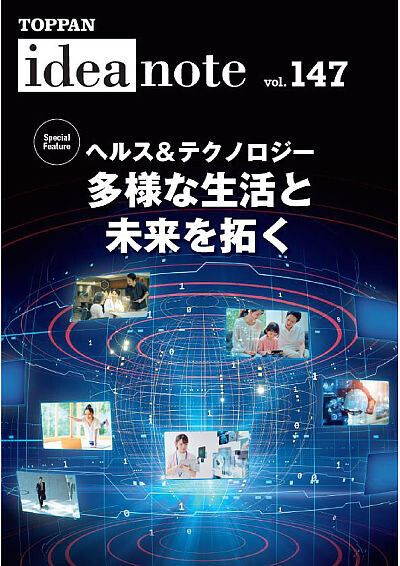ヘルスケア領域で進む、データ活用!
課題から活用事例まで未来のヘルスケアの形をご紹介
近年、国内外でヘルスケア市場が盛り上がりを見せています。そして近年、多くの領域がそうであるように、ヘルスケア領域でもデータ活用が進められています。
今回は、ヘルスケア領域におけるデータ活用の背景やヘルスケアデータの種類、ヘルスケアデータの利活用の課題、活用事例をご紹介します。
ヘルスケア領域で推進されるデータ活用
近年、ヘルスケア領域においてデータ活用が進められています。ビッグデータという大規模な基盤構築の構想から、ビジネス用途でのヘルスケアデータの利用まで幅広く進行しています。
ビッグデータ基盤構築の構想
国はデータヘルス改革を進めており、ヘルスビッグデータの基盤構築を推進しています。
データヘルス改革では、ビッグデータのプラットフォームを構築し、健康・医療・介護のビッグデータの分析を行い、保険者が主体的に保険運営を行えるよう、保険者機能を強化し、実効的なデータヘルスの推進を図ることが目指されています。
医療現場の情報や、血圧や心拍数などの生体データがリアルタイムに収集されビッグデータとなることで、人々の快適な生活や健康増進、最適治療、負担軽減が実現できると考えられています。
ビジネスへのデータ活用も進む
ビジネスの分野でも、ヘルスケア領域のデータ活用が進んでいます。IoTによる情報取得やデータ通信などのほか、ビッグデータを活用した事業モデルの創出の動きが活性化しています。
ヘルスケアデータの種類
近年、注目を集めているヘルスケアデータには、次のような種類があります。

EMR
EMRとは「Electronic Medical Record」の略であり「電子医療記録」と訳されます。これは紙のカルテを電子化したものです。
EMRは情報をデジタル化してデータベースに保存しており、検索性や可読性、長期保存性が高いことから医療従事者の業務効率化につながっています。
基本的に外部の医療機関との共有はせず、医療機関の中で運用されることが想定されています。
EHR
EHRとは「Electronic Health Record」の略であり、「電子健康記録」と訳されます。
EHRは、患者の診断に関する情報のほか、検査結果や既往歴、血圧、体重などの生体データ、診療行為、薬剤などのレセプト(診療報酬明細書)情報が含まれています。
個人の診療情報を複数の医療機関の間で共有・活用する仕組みが想定されています。この点がEMRとは異なる点です。EHRを通じて地域医療の実現が目指されています。
PHR
PHRとは「Personal Health Record」の略で、「個人健康記録」と訳されます。「Personal」と名付けられている通り、基本的には、患者個人が自分の健康を管理することを目的とした健康記録となります。
自身の検査結果や既往歴、服薬履歴、日々の体重や血圧などの身体情報から生活習慣まで、生活に根付いた情報である点が特徴です。
PHRと、医療機関が扱うEHRとを連携させることで医療の質が上がり、地域医療の促進、在宅医療の推進などにつながることが期待されています。
ヘルスケアデータの利活用の課題
ヘルスケアデータを医療機関やビジネスにおいて事業者が利活用する際には、さまざまな課題があります。
個人情報保護のためのセキュリティ強化
ヘルスケアデータで重要になるのは、患者情報などの個人データです。同時にデータ提供者である個人のプライバシー保護はヘルスケアデータ活用の大きな課題の一つとなっています。
そのため、ヘルスケアデータの利活用を進める上でセキュリティの強化は欠かせません。情報漏洩や改ざんのリスクを、収集・共有時に徹底して回避する処置を行わなければなりません。
一般生活者がヘルスケア関連サービスを利用する場合においても、セキュリティ不安が少ない環境を構築しなければ、普及も進んでいかないと考えられます。
データの標準化
ビッグデータによるプラットフォーム構築も目指されている医療データは、あらゆる箇所にあらゆる形式で存在しています。そのようなバラバラのデータをいかに統一し、標準化させるかがデータの利活用をするために重要な課題となっています。
しかし、データの標準化には、ルール決めはもちろんのこと、フォーマット統一なども実施する必要があり、時間とコストがかかることは否めません。
小規模な医療機関における電子カルテの普及率が低い
厚生労働省のデータによると、電子カルテの普及率は2020年時点では一般病院で57.2%となっています。
病床規模別に見ると、200床未満の施設においては48.8%と、電子カルテはまだ当たり前のものではないのが現状です。年々、徐々に高まってきてはいることから、今後の普及率向上が期待されます。
ヘルスケアデータの活用事例
ヘルスケアデータは、すでにさまざまなケースで活用されています。活用事例を3つご紹介します。

地方都市のレセプトデータ分析により医療関連情報サービスを提供した事例
ある企業が、地方都市の医療費適正化や健康寿命の延伸といった課題を解決するため、レセプトデータを独自のICT技術で分析し、その結果を医療関連情報サービスの提供につなげました。具体的には、糖尿病重症化予防や受診勧奨の指導、頻回受診者への指導、ジェネリック医薬品通知などです。
その結果、糖尿病性腎症重症化予防により国保被保険者の透析移行遅延に貢献したり、被保険者の健康増進により健康寿命の延伸や生産年齢人口の確保に貢献したりしたほか、医療費の適正化を図ることに寄与しました。
保険会社のヘルスケアデータ分析による新型保険商品開発事例
ある保険会社は、健診・レセプトデータの分析の結果を活用した新型保険商品の開発を行いました。分析の結果導き出した、「健康年齢」という独自の指標を基準に、健康である人ほど保険料が下がる仕組みを設定する保険商品です。保険加入と同時に健康を推進したくなる画期的な商品となりました。
IoT住宅で健康データを取得して見える化した事例
昨今のヘルスケアサービスへのニーズの高まりを踏まえ、新築や中古の分譲マンションにTOPPANのIoT健康管理サービス「cheercle(チアクル)」が導入されています。
cheercleは、住宅の生活動線上でデータを収集・蓄積・管理するIoT洗面空間サービスです。床埋め込み型体組成計「cheercleメーター」と、タッチ操作が可能なIoTミラー「cheercleミラー」を組み合わせ、洗面空間で身体データを計測する仕組みです。
計測したデータは、独自開発のクラウドに蓄積・解析し、アドバイスコメントと共にミラーやスマホアプリを介してユーザーへ届けることで、健康管理の習慣化を促します。
まとめ
ヘルスケアデータの現状や課題、今後の利活用のための事例をご紹介しました。今後はヘルスケアデータのさらなる利活用のためにも課題解決策を積極的に進めていきたいものです。
TOPPANでは、ヘルスケア関連サービスを多数展開しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連サービス
関連コラム
2023.12.21