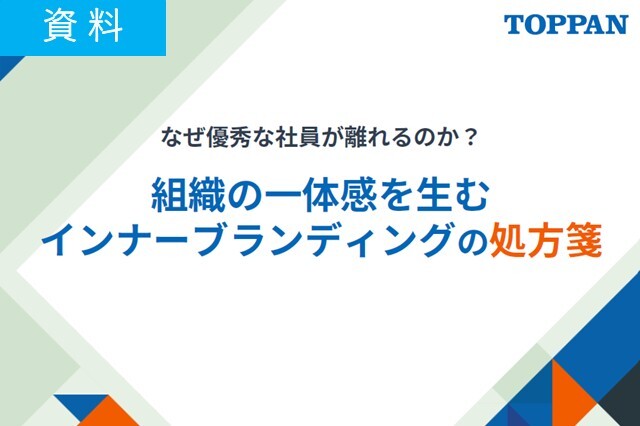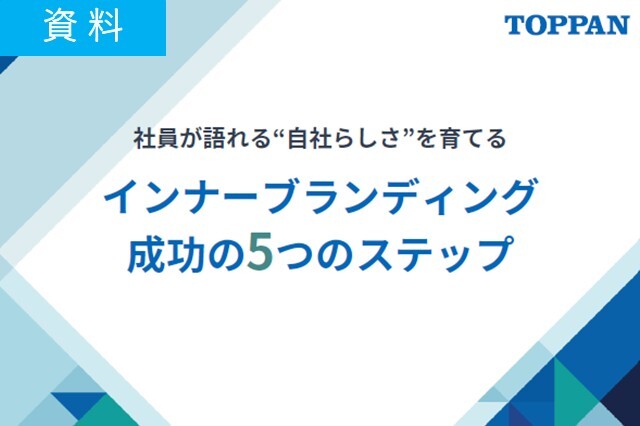インナーブランディングと
アウターブランディングの違いとは?
それぞれを比較!
人材獲得競争の激化が進む中、自社の企業理念や価値観を体現する従業員を数多く確保する取り組みであるインナーブランディングは、重要な施策といえます。
インナーブランディングは社内に対するブランディング活動ですが、社外に対するブランディング活動であるアウターブランディングとの違いを知り、施策に役立てたい方も多いのではないでしょうか。
今回は、インナーブランディングとアウターブランディングとの違いを、定義から効果、手法だけではなく、両輪で進めることが重要な2つの手法の進め方についてもご紹介します。
インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?

インナーブランディングとアウターブランディングの定義の違いを見ていきましょう。
インナーブランディングとは?
インナーブランディングとは、自社の従業員に対して企業理念や価値観を浸透させる取り組みです。従業員が自社の目指している方向性や大切にしている価値観などを理解し、共感した上で、自ら体現しながら仕事を進めることで、生産性向上および組織の一体感の醸成などを促進させます。
アウターブランディングとは?
アウターブランディングとは、社外の人々を対象としたブランディング活動です。具体的には、お客さま、取引先、一般消費者、パートナー企業、株主、採用候補者などが挙げられます。自社そのものや自社のブランド、商品の魅力や独自の特徴を対外的に効果的に伝えることで、認知度・好感度の向上につなげます。
インナーブランディングとアウターブランディングの違い
インナーブランディングとアウターブランディングは、どちらも同じブランディング活動です。ブランディング活動とは、対象者に対して、独自のブランドに対する認知や理解を促し、共感や信頼を生むことで、ブランドの価値向上や他ブランドとの差別化を目指す取り組みです。
インナーブランディングとアウターブランディングの大きな違いは、その「対象者」にあります。インナーブランディングが「社内」に対するブランディングであるのに対し、アウターブランディングは「社外」に対するブランディングとなります。
また、「目的」にも違いがあります。インナーブランディングの主な目的は、従業員一人ひとりが自社の理念に共感し、より生産性高く働いてもらうことです。そして、そのような従業員が増えれば理念が浸透した組織的な一体感が生まれ、企業の目標を達成することができます。
アウターブランディングの主な目的は、競合優位性を得ることです。売上面、顧客や採用候補者、株主などからの信頼面をはじめ、あらゆる方面で競合他社に勝ることを目指します。
インナーブランディングとアウターブランディングの効果の違い

インナーブランディングとアウターブランディングには、主に対象者と目的に違いがあるとお伝えしました。その結果、生まれる「効果」には次のような違いがあります。
インナーブランディングの効果
①従業員エンゲージメント向上
従業員エンゲージメントとは、従業員が抱く自社に対する愛着を意味し、「仕事へのやりがい・情熱」と「企業理念への共感・愛着・貢献意欲」の大きく2つで構成されています。インナーブランディング施策によって自社への愛着と理解が増すことで、より仕事への情熱が高まります。また他の従業員を刺激し、良い影響を与えるメリットもあります。
②企業・ブランドイメージアップ
インナーブランディングにより従業員に対して自社や自社ブランドの印象が良くなり、好感度が増すと考えられます。より一層、自社への貢献意識が高まるでしょう。
③生産性向上
自社への理解や好感度が上がれば、自身の日頃の仕事への貢献意欲が高まり、モチベーションアップによる生産性向上につながります。
④離職率低下・優秀な人材の確保
企業理念に則り、イキイキと働く従業員が増えれば、人材流出を予防し、優秀な人材確保にも寄与します。
アウターブランディングの効果
①差別化による売上アップ
アウターブランディングの当初の目的を実現できます。差別化により競争優位性が高まれば、より多くの顧客からの信頼と共感を得られ、売上アップにつながります。
②認知度・共感度向上によるファン・リピーター創出
ブランドの価値観を浸透させることで、ブランドの深い思いに共感する顧客が増えます。ファンやリピーターの創出にも寄与するでしょう。
③採用面における人材確保
採用候補者に良いブランディングがなされれば、「買いたい」だけでなく「働きたい」と思わせることもできるでしょう。その結果、ブランド理念に愛着を持った人材を確保できる可能性もあります。
インナーブランディングとアウターブランディングの手法の違い

インナーブランディングとアウターブランディングは、手法も異なります。
インナーブランディングの手法
【社内報、社内ポータル、社内イベント、ノベルティグッズ配布、表彰制度、ビジョン浸透プログラムなど】
インナーブランディングの手法は、社内に対して実施するものであるため、社内報や社内ポータルの展開による情報共有、直接交流する社内イベント開催、ノベルティグッズの配布、理念を体現する従業員への表彰、研修のような形で実施するビジョン浸透プログラムやワークショップなどが挙げられます。
アウターブランディングの手法
【広告、SNS、イベントなど】
アウターブランディングの手法は、社外に対して実施します。一般消費者に向けた施策と、顧客・取引先・株主などのターゲットを限定した施策があります。
社外の一般消費者に向けた施策はオンライン・オフライン広告が主流であり、SNSやオウンドメディアなどを活用したWebマーケティングも活発に行われています。また、広い一般消費者を対象としたイベントや優良顧客、取引先などに限ったイベントの開催もブランディング施策の一種です。
インナーブランディングとアウターブランディングは両輪の関係にある

これまでインナーブランディングとアウターブランディングの違いを解説してきましたが、それぞれは両輪の関係にあり、同時進行することで、相乗効果を生み出すことができます。
インナーブランディングとアウターブランディングが両輪の関係にある理由
なぜこの2つが両輪なのか、それは、互いに施策を進める上で必要な要素であるためです。
例えば、インナーブランディングを進める際には、顧客に対する考え方も一つの浸透項目となります。顧客に対してどのように対応するか、どのような目標・指針を持って接遇するかといったことは、アウターブランディングにも必要な視点です。
また、対外的なSNSでの情報発信などを行うのは従業員であり、インナーブランディングにより企業理念がしっかりと浸透していなければ、企業理念にそぐわない行動が散見されるようになってしまいます。そのちょっとした「ずれ」が間違ったブランディングにつながり、アウターブランディングがうまくいかなくなってしまう場合もあります。
このように、インナーブランディングとアウターブランディングは、どちらか一方で成り立つものではないのです。
一貫性を持って両方を実施することが重要
このことから、インナーブランディングとアウターブランディングそれぞれの効果を出すには、両方を連動させて進行することが必要といえます。そしてこのとき、インナーブランディングとアウターブランディングで浸透させる理念や価値観には一貫性を持たせることが何より重要です。その結果、一貫性のあるブランディングが可能になります。
まとめ
インナーブランディングとアウターブランディングの違いは、社内・社外といった対象だけではなく、目的や効果、手法にも見ることができます。
そしてインナーブランディングとアウターブランディングは連動させて進めることで、はじめて効果が出る上に、相乗効果も生みます。
インナーブランディングとアウターブランディングの両方を自社で一貫性を持って実施するリソースや知見の不足を感じる際には、TOPPANにご相談ください。
インナーブランディングコンサルティング支援と共に、アウターブランディングを取り扱うブランドコンサルティングサービスをご提供しております。
2025.10.10