企業に求められる災害レジリエンスとは?
国・自治体・企業の取り組みもご紹介
国が災害に強い国家の構築を目指す中、企業も災害への予防策をはじめとした対応、および災害レジリエンスを強化する取り組みが求められています。
今回は、災害レジリエンスの概要から取り組むべき事項、自治体や企業の取り組み例までご紹介します。
災害レジリエンスとは
災害レジリエンスとはどのような意味なのか、概要と共に3つの要素を確認しておきましょう。
災害レジリエンスとは
災害レジリエンスとは、「災害対応力」や「災害回復力」、「災害後復興力」といった意味を持ちます。「レジリエンス(Resilience)」には困難や苦境からの回復力や立ち直る力、復活力という意味合いがあり、国や企業などの組織が災害に直面したときに、いかに回復し、復興できるかどうかの力を指しています。
災害レジリエンスの3つの要素
一般的に災害レジリエンスには、予防策、順応策、転換策の3つの要素があるといわれており、この3つがすべてそろうことで、レジリエンスが成立します。
予防策:災害に対して被害を未然に防止することを意味します。
順応策:事前の対策を超える外力に対して、影響を受け入れつつ地域や社会のさまざまなシステムを変えながら影響を低減し、状況に適応していくことを意味します。そして被害の程度を最小限に留めます。
転換策:起きた災害の経験から学習し、方法を変えることを意味します。閾値を超えて災害の影響が強大化した場合には、これまでのシステムを見直し、抜本的な転換が必要になってきます。
災害レジリエンスの必要性
災害レジリエンスの概念は防災や減災の取り組みと重複するところがあります。すべて並行して行われるべき取り組みですが、災害レジリエンスは特に災害からの「回復」「復興」に力点が置かれています。
災害レジリエンスに取り組むことで、特に大震災などの大規模な自然災害などが起きたときに、被害を最小化し、社会や組織の機能の回復及び復興・復旧のスピードを高めることができるようになります。
災害レジリエンスの国の取り組み
国は、近年立て続けに起きている大規模地震などを背景に、2013年頃より災害レジリエンスを「ナショナル・レジリエンス(国土強靭化)」として、さまざまな取り組みを実施しています。
国土強靭化とは、国家・地域社会・企業が想定すべきすべてのリスクに対し、被害の最小化やバックアップの確保によるリスク分散、実効的なBCP(事業継続計画)の策定・実行により機能の迅速な回復などを可能にすることを目指すものです。
施策例
・避難所機能の強化
2024年1月に起きた能登半島地震では、指定避難所である小学校において空調設備の整備を事前に行っていたことにより、発災後に避難所として支障のない避難生活が可能になりました。
・交通情報収集・提供・活用のためのシステム整備・運用
同じく能登半島地震において効果を発揮した施策の事例です。警察庁が、各都道府県警察が収集した交通情報や交通流監視カメラの画像などの閲覧などを可能にする広域交通管制システムを整備していたことで、発災後の道路状況の迅速な把握が可能になりました。またWebサイトでの一般公開も行い、交通の安全と情報共有を円滑にすることができました。
・流域治水対策
2023年に起きた台風14号では、国土交通省の遊水地整備、河道掘削を実施していたことで洪水時に対して、観測所地点では水位を約1.5m低下させ、本川からの越水を回避し、浸水被害を防止することができました。
災害レジリエンス向上のために企業に求められる対応
災害レジリエンス向上のために、企業に求められる対応にはどのような取り組みがあるのでしょうか。主に次のことが考えられます。
BCPの策定
災害レジリエンスを向上させるには、災害などのリスクに備えてBCP(事業継続計画)の策定を進めることが最重要です。BCPとは災害や事故などが発生した際に、その被害を最小限に留め、事業継続と早期復旧を図るための計画のことです。BCPを策定しているかどうかで災害時の混乱した状況下での適切な判断の中身やスピードが大きく変わってきます。
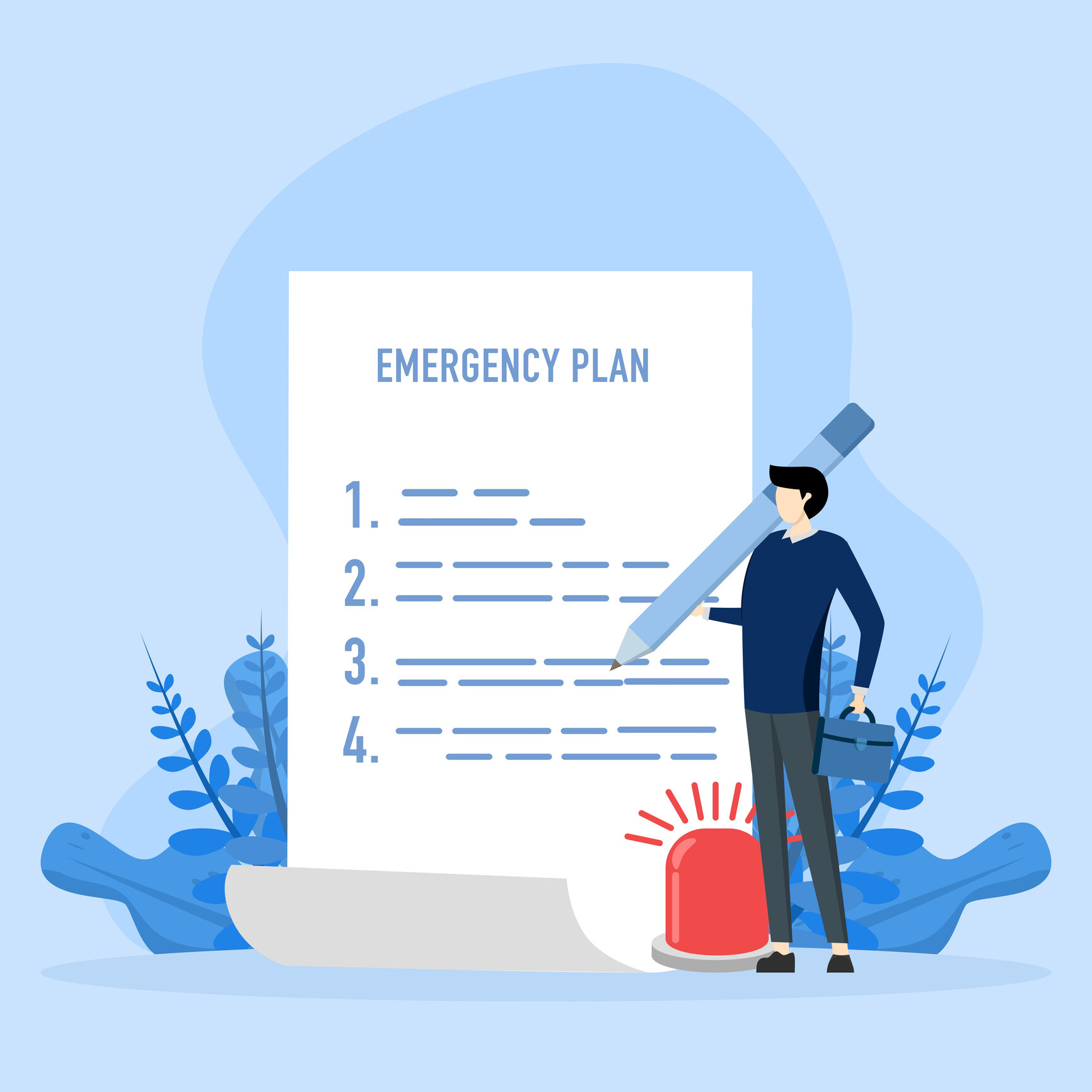
BCPの社内浸透
BCPは策定すればそれで終わりではなく、いかに社内に浸透させ、従業員が当事者意識を持って実践するかが重要です。
BCPをもとにした訓練
BCPでは防災訓練や避難訓練を実施する計画を盛り込むのが一般的です。定期的な訓練を実施することが、災害発生時の行動を大きく左右するといわれています。
サプライチェーンとの連携強化
災害が生じ自社が被災すると、自社だけでなくサプライチェーン全体に影響が及びます。平常時にサプライチェーン同士が連携を強化しておくことは、BCPの一環となります。
各種防災活動
災害レジリエンスの活動においても、防災活動は重要です。オフィス内の家具の固定や備蓄の準備など基本的な取り組みを実施しましょう。
災害レジリエンスに取り組んでいる自治体と企業の例
災害レジリエンスは、具体的に、どのような取り組みが行われているのでしょうか。自治体と企業の例をご紹介します。
地方自治体
ある地方自治体は、災害レジリエンスに注力しており、水害に対して重点的なレジリエンス力を高めるアクションや、水害および土砂災害のリスクを軽減させる防災インフラの整備、避難サポートなどに取り組んでいます。
水害に対するアクションでは、河川整備や河川やダムの流下・貯留能力の回復を目的とした土砂の除去、住民の避難行動の主体性を引き出すための、洪水時に河川に近づくことなく水位観測が可能な危機管理型水位計や河川監視カメラなどの設置を行っています。
避難サポートでは、災害時における逃げ遅れをゼロにするため、避難行動を時系列で整理したタイムラインの作成支援などを行っています。
地方都市
ある地方都市は、レジリエンス戦略として持続可能で強靭なまちづくりに取り組んでいます。世界的にもレジリエンス都市として評価されており、災害分野においては、土砂災害に備えて国土交通省や自治体と共に自然災害対策を進めています。
自動車メーカー
ある日本の自動車メーカーは、災害時における事業継続のために、サプライチェーン調査とリスク品目の抽出から事前の対策実行を平常時から行っており、災害時には即時、被災候補拠点のリストアップができるようにしており、同時に早期に対策を実施できるようにしています。サプライチェーン情報と地理リスク情報をWeb上でデータベース化することで、サプライチェーンとリアルタイムでの情報共有を実現しています。
地図作製会社
ある地図作製会社では、災害時に役立つ地図を提供しています。これは位置情報が建物番地で網羅された地図となっており、通常の地図と縮尺が異なり情報を大きく表示できることが特徴です。被災時に自分の場所を特定するときに、「今、自分がどこにいるのか」について、より細かい情報が素早くわかります。番地などの数字は高齢者でも読めるように大きくしている点も特徴です。平時から使える生活便利マップの機能も備わるため、防災学習を可能にしています。
まとめ
国の取り組みや企業に求められる取り組み、事例を通じて、自治体や企業が行うべき取り組みのヒントを得ることができます。
TOPPANでは、災害レジリエンスにも役立つ防災ソリューションを多数ご提供しております。詳細はサービスページや資料をご覧ください。ご不明な点については、ぜひお気軽にご相談ください。
2024.04.12