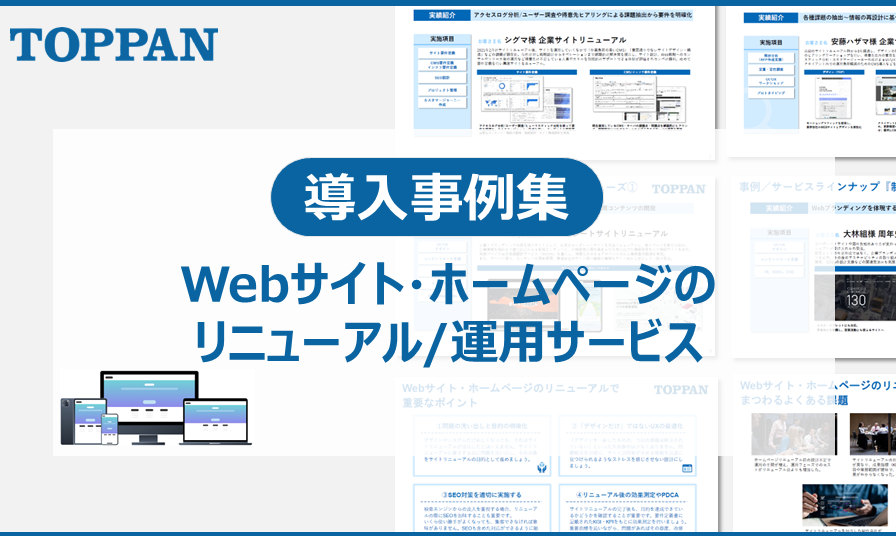サイトリニューアル提案書の作り方|
社内稟議を通し成功へ導く方法
Webサイトをリニューアルする際は、社内向けの提案書や企画書を作成し、決裁者である上司や役員の理解を得てから制作会社に依頼するのが一般的です。そのため、いかに決裁者の納得を得られる社内向け提案書を作成できるかが第一の関門だといえるでしょう。
しかし、いざ提案書を作成しようにも、何から始めれば良いのか分からずに悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。提案書を作成する際には、まず提案書に必要な項目や基本的な構成を理解し、一つひとつの要素を洗い出すことが大切です。
本記事では、Webサイトリニューアルの社内向け提案書を作成する方法やコツについて詳しく解説します。適切な作り方を押さえることで提案書の質が向上し、稟議を通過する可能性が高くなるでしょう。
<目次>
1.サイトリニューアル提案書とは?
2.サイトリニューアル提案書が必要になるパターン
3.サイトリニューアル提案書で必要な項目と基本構成
4.サイトリニューアル提案書作成時のポイント
5.サイトリニューアル提案書の作り方のまとめ
サイトリニューアル提案書とは
サイトリニューアル提案書とは、現在のサイトが抱える課題を可視化し、改善の流れと成果を示す提案書です。経営層への相談・上申資料として、目的・KPI、対応範囲、費用、時間、体制を明記し、担当の責任分担と管理方法を整理します。さらにユーザーとビジネス双方の視点でROIを定量化することで、発注前の意思決定に役立ちます。
充実した提案書があれば、制作フェーズでの仕様変更リスクを抑え、関係者間の齟齬を防いで円滑な推進を促進できます。
サイトリニューアル提案書が必要になるパターン
会社のイメージ変更やブランドの変更
企業の成長や市場の変化に伴い、事業内容やターゲット層が変化することは少なくありません。
例えば、BtoB事業から一般消費者向け(BtoC)にもサービスを拡大したり、ロゴやコーポレートカラーを一新したりする場合です。このとき、既存のウェブサイトが古いままでは、新しいブランドイメージと一貫性がなく、訪問者に誤った印象を与え離脱してしまうおそれがあります。
Webサイトは「会社の顔」であるため、新しいブランド戦略やビジョンを反映させる必要があります。ブランドイメージに合わせた洗練されたデザイン、統一されたトーン&マナー、そして新しいメッセージを伝えるためのコンテンツを盛り込むことで、顧客からの信頼を獲得し、ブランド価値を向上させます。
この目的を達成するためには、現状の課題を洗い出し、新しいブランド戦略をどうWebサイトに落とし込むかを具体的に示す提案書が不可欠です。
ユーザー体験(UX)の改善とコンバージョン率の向上
Webサイトのアクセス数はあるものの、問い合わせや購入などの成果に結びつかない場合、その原因はウェブサイトの使い勝手にある場合があります。
ユーザーが目的の情報にたどり着けない、モバイルでの表示が崩れている、入力フォームが複雑で離脱してしまうなど、集客ユーザーのフラストレーションがコンバージョン率の低下を招いています。
サイトリニューアル提案書では、データ分析に基づいてユーザーの行動を詳細に把握し、どこに課題があるのかを具体的にします。
その上で、よりわかりやすいナビゲーションやストレスなく情報にアクセスできる構造・最適化されたフォームなど、ユーザー視点の行動を促すための具体的な改善策を提案し導入することで、ユーザーの満足度を高め最終的なビジネス目標の達成に貢献します。
テクノロジーの老朽化とセキュリティリスク
現在の公開されているWebサイトが古い技術で構築されている場合、多くの問題が発生します。
古い技術は最新のブラウザやデバイスに対応できず、表示が崩れたり、機能が動作しなかったりします。
さらに深刻なのは、セキュリティリスクです。古いCMSやプラグインには脆弱性が発見されやすく、不正アクセスや情報漏洩の危険性が高まります。
こうしたリスクを放置することは、企業としての信頼を失ったたり損害賠償請求にもつながりかねません。
提案書では、最新のセキュリティ対策が施されたCMSへの移行、ページの読み込み速度を向上させるための技術的改善・プライバシーポリシーの更新などを具体的に提示します。
これにより、サイトのパフォーマンスと安全性を確保し、将来にわたって安定したWebサイト運営が求められます。
マーケティング戦略の変化と新しい機能の追加
企業のマーケティング戦略が従来の「一方的な情報発信」から「顧客とのエンゲージメント」へとシフトするにつれて、Webサイトに求められる役割も変化します。
例えば、ブログやニュースリリースを自社で簡単に更新できる機能、顧客との対話を促すチャットボット、オンラインでの製品販売を可能にするEコマース機能、さらには顧客管理システム(CRM)とのデータ連携など、Webサイトを単なる情報提供の場から、顧客との関係を深めるための場として活用したい場合です。
これらの新しい機能やシステムを導入するためには、全体のWebサイト構造や技術的な基盤を根本的に見直す必要があります。提案書では、新しいマーケティング戦略の目標を明確にし、その達成に不可欠な機能やシステムをどのように実装するか、そのための技術的・コンテンツ的なアプローチを体系的に提示します。
サイトリニューアル提案書に必要な項目と基本の構成

Webサイトリニューアルの社内向け提案書は、思いついた要素を闇雲に記載すれば良いというわけではありません。誰が見ても内容を簡単に理解できるよう、最初に構成を考え、伝える内容を要素ごとに一覧にして整理することが大切です。
ここでは、提案書に必要な項目と、基本的な構成について解説します。
1. 表紙
2. 概要・目次
3. リニューアルの目的
4. 課題分析
5. ターゲットとコンセプト
6. コンテンツ案・デザインイメージ
7. 目標・成果指標
8. 他社事例
9. 予算・スケジュール
1. 表紙
提案書の最初のページには表紙を配置します。
社内の決裁者に提案書を提出する意図を理解してもらうには、サイトリニューアルの目的を表す「タイトル」と、最終的なゴールを示す「キャッチコピー」を記載することが大切です。また、「いつ誰が提案したのか」がわかるよう、自社名や提出日を明記します。
2. 概要・目次
提案書全体の内容を簡略化した概要、もしくは目次を作成しましょう。
概要や目次があると、一目見てWebサイトリニューアルのプロジェクト全体像を把握できます。また、必要に応じて各ページにアクセスしやすくなるのもメリットです。
全体像を把握した後に詳細を確認することで、社内の決裁者がリニューアルの目的や方針を理解しやすくなり、企画が承認される可能性が高くなるでしょう。
3. リニューアルの目的
現行のWebサイトにどのような課題があり、リニューアルによってどういった効果を得たいのかという目的を明確にします。課題なくして目的は存在しないため、まずはアクセス解析ツールを用いた定量分析や、関係者へのヒアリングやインタビューを通じた定性分析で、現状の問題点を特定しましょう。
たとえば、徐々に対面営業を行うのが難しくなり、営業成績が落ち込んでいるとすると、「非対面の重要チャネルとして、契約者が利用するマイページのCX向上をはかる」といった目的が考えられます。目的を明確にすることで、具体的な課題解決策やアクションプランを策定しやすくなるでしょう。
4. 課題分析
現状の課題をより詳細に分析し、その結果や所感を提案書に明記します。リニューアルに取りかかる前に、自社サイトの詳細な課題を決裁者に伝えることで、その問題の重要性を理解してもらいやすくなります。
課題を分析する際は、前述の通り、定量分析と定性分析を組み合わせることが大切です。
たとえば「PVが減少傾向にある」というだけでは課題として漠然としすぎていますが、ここにアクセス解析ツールを用いた定量分析の結果を加え「PVが過去○年間で□%減少している」とすることで、より具体性を持たせることができます。
さらに定量分析として、社内向けのインタビューやユーザーへのアンケートを加えると、「PVが過去○年間で□%減少している。その原因としては、ユーザーに不親切なUI設計が考えられる」といった形で、課題をより絞り込むことが可能になります。
5. ターゲットとコンセプト
誰に対してどのようなアプローチを実施するのか、Webサイトのターゲットとコンセプトを明確にします。
ターゲットを設定する際はペルソナを絞り込みましょう。「20代の男性」といった抽象的なイメージではなく、実際に自社サイトを使用する詳細な人物像を設計するのがポイントです。氏名や年齢、住所、職業、収入、仕事での目標、趣味などの要素を組み合わせ、詳細なペルソナを設定すると、ユーザーのニーズを特定しやすくなります。
そして、設定したペルソナの情報をもとに、リニューアル後のWebサイトのコンセプトを考えましょう。
ペルソナが抱える課題に対して、自社サイトが何を提供できるのかを突き詰めていけば、「60代になり健康的な食生活を意識し始めた一人暮らしの男性へ、調理しやすい低カロリーレシピを紹介」のように、明確なコンセプトが完成します。
6. コンテンツ案・デザインイメージ
リニューアル後のWebサイトの完成図がわかるよう、コンテンツ案やデザインイメージを作成しましょう。
コンテンツ案に関しては、計画段階で洗い出した複数のコンテンツを構造化することで、視認性や可読性が向上します。また、次の通り、既存コンテンツと新コンテンツがわかるように明記することも大切です。
|
【作成例】
【既存コンテンツ】 【新規追加コンテンツ】
【既存コンテンツ】 【新規追加コンテンツ】 |
このようなコンテンツ案とともにデザインイメージを記載します。
リニューアル後のデザインをイメージ化するのが難しい場合は、簡易的な図や画像・テキストで表現したり、他社のデザインを参考にしたりするのがおすすめです。
7. 目標・成果指標
Webサイトリニューアルの提案書には、KGIとKPIを明記することも重要です。KGIは「Key Goal Indicator」の略で、サイトリニューアルの最終目標を指します。KPIは「Key Performance Indicator」の略で、KGIを達成するための中間目標を意味します。
KGIとKPIは、いずれも具体的な数値目標を設定することが重要です。はっきりとした数字があることで、リニューアル後に目標と実績の差をもとに適切な効果検証を行えます。
また、KGIとKPIは、前述した課題や目的に沿って設定するようにしましょう。
たとえば、リード獲得の課題を解決するのが目的であれば、リード獲得数をKGIに設定。その目標を達成するための参考にすべきKPIとして、PVやページスクロール率、フォームのクリック率などを指標にするといったイメージです。
8. 他社事例
Webサイトリニューアルの提案書には、いくつか他社の事例を載せておきましょう。実際にWebサイトリニューアルに成功した事例があると、先ほど設定したKGIやKPIを本当に達成できるのか、その実現可能性をアピールできます。結果、提案書としての説得力が増し、決裁者に前向きに検討してもらいやすくなります。
9. 予算・スケジュール
最後に、Webサイトリニューアルに必要な予算やスケジュールを明記します。
提案書にスケジュールを記載する場合は、工程ごとの目安期間を定めておくと良いでしょう。Webサイトリニューアルには、「要件定義・設計・デザイン・ページ制作・テスト」といった工程が存在します。工程ごとの細かいスケジュールを想定しておくと、制作会社に依頼する際に細かい日程調整が可能です。
サイトリニューアル提案書作成時のポイント

より質の高い社内むけ提案書を作成できるよう、作成時のポイントを押さえましょう。提案書の質が向上することにより、社内稟議に通過する可能性を高められます。
課題や目標は数字で示す
提案書に記載する課題や目標を具体的に数字で示すことで、読み手との認識のズレを抑えられます。
また、単に数字を記載するだけではなく、客観的な情報を意識することも大切です。
たとえば、「コンバージョン数100件」という数字は、判断する人によりその水準が高いのか低いのか、基準が異なるケースも珍しくありません。そこで、「PV10,000回、コンバージョン数100件(コンバージョン率1%)」のように別の数値を付け足すと、その水準をある程度客観視できるようになります。
さらに客観的な情報を加えるなら、「競合他社のコンバージョン率は5%」「業界平均値は3%」など、自社以外の水準と比較できる情報があると良いでしょう。
専門用語は避ける
誰が見ても内容を即座に理解できるよう、具体的な専用用語は避け、平易な言葉を使って提案書の内容を考えましょう。特に、提案書を読む上司や役員にWebサイト運営の知見が不足している場合は、できる限りかみ砕いて、どうしても専門用語が必要なときは補足説明を入れるといった工夫が必要です。
このような工夫により、専門性が読み手の理解を阻害するリスクを避けられます。
不要な説明・項目は極力カット
読み手の理解度が高まるよう、不要な説明や項目を省略することも大切です。
提案書は、あくまでWebサイトリニューアルの必要性を説明するために存在します。その必要性を訴求する際に余計な説明や項目があまりにも多いと、視認性や可読性が下がってしまうでしょう。
調査したデータをコピー&ペーストで貼り付けるのも、適切だとはいえません。調査資料のなかから本当に必要な情報を抽出したり、データを整形したりと、端的で読みやすい提案書を心がけましょう。
お金を絡めてメリットを提示する
費用的なメリットを読み手に提示することで、提案書としての説得力が増します。
費用メリットを提示する際は、「コンバージョン率10%向上」といったKGIやKPIの改善率を訴求できます。しかし、読み手にとっては、その改善が自社にどれだけメリットがあるのかがわかりづらいものです。
そこで、「コンバージョン率が10%向上した結果、売上高が5%増加する」というように、KGIやKPIの改善が企業業績に好影響を与えることをアピールすると良いでしょう。結果、読み手がリニューアルの費用対効果をイメージしやすくなり、稟議に通過する可能性が高まります。
サイトリニューアルの提案書の作り方まとめ
Webサイトリニューアルの社内むけ提案書は、目的や現状の課題、リニューアル後のイメージや目標数値を明確に提示することが大切です。
社内稟議を通過し、予算が獲得できれば、制作会社に提案依頼としてRFPを提示します。また、企業によっては、社内稟議の前に制作会社へRFPを提出し、デザインコンペや見積もりを依頼するケースもあるでしょう。
RFPは、制作会社が的確なデザイン案や課題解決策を提案できるよう、リニューアル要件を取りまとめた書類です。社内向けの提案書とは作り方がやや異なるため、もし作成方法がわからない場合は、TOPPANの「RFP作成支援サービス」を活用してみてはいかがでしょうか。
RFP支援サービスは、お客様の代わりに当社がRFPを作成するサービスです。
アクセス解析や関係者へのインタビューを通じた現状把握・目的の明確化に加え、調査内容にもとづいた課題抽出やその解決策の立案などを実施します。質の高いRFPが完成すれば、制作会社からより良い提案を受けやすくなる、後の契約トラブルを防げるといったメリットが期待できます。
手間をかけずに質の高いRFPを作成したい方は、ぜひご検討ください。
2025.09.30