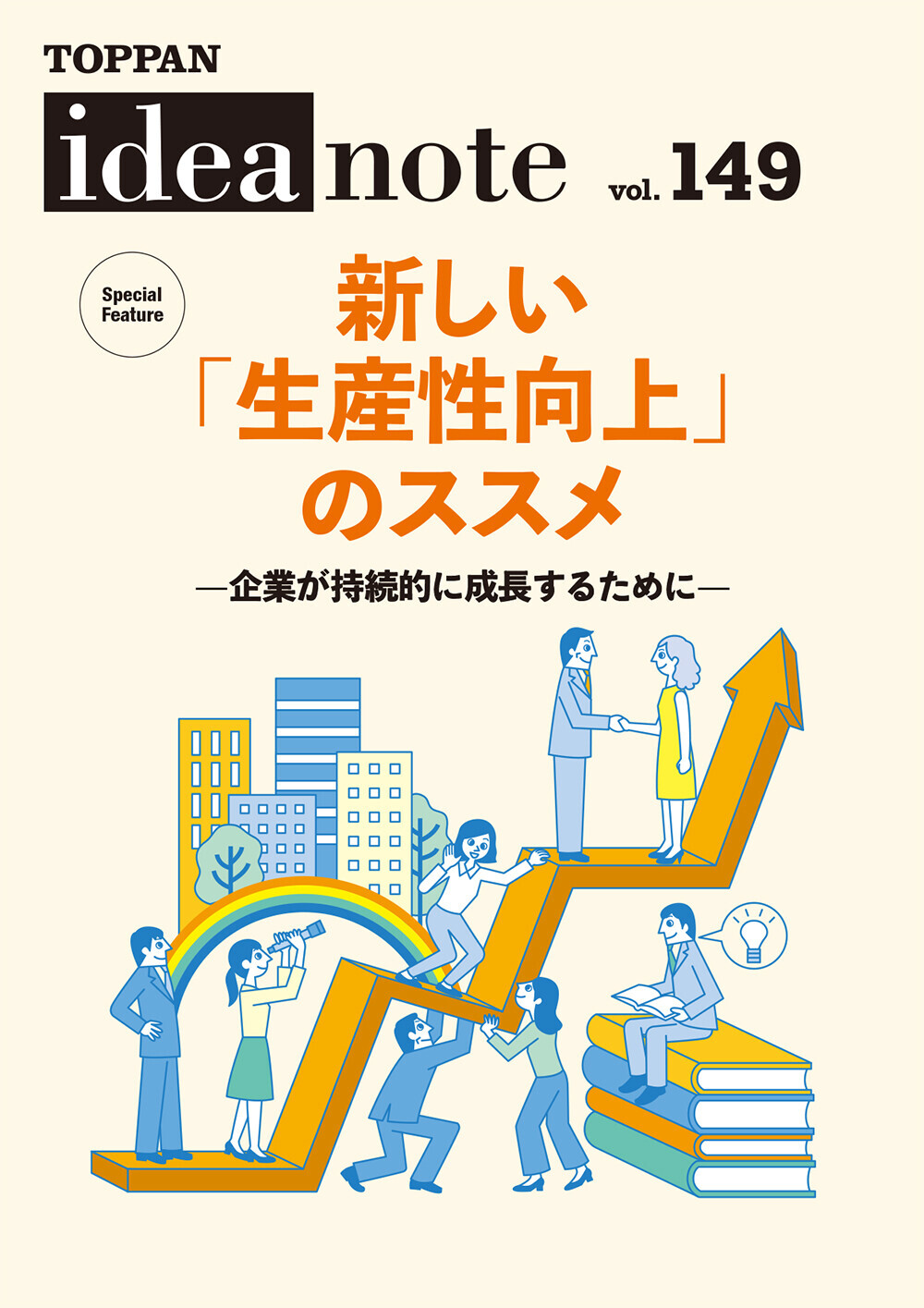デジタル化とは?
電子化との違いや効率的な推進方法を解説
近年、多くの企業でデジタル化が推進されていますが、課題に直面しているケースは多くあります。どのような課題があり、どのような課題解決策があるのでしょうか。
今回は、社内におけるデジタル化のメリットやデジタル化の課題、解決策としてデジタル化を効率的に推進する方法を解説します。
デジタル化とは?
デジタル化の概要を確認していきましょう。
デジタル化とは?
デジタル化とは、手作業や紙で行っていたアナログの業務をデジタルに変えることを指します。例えば、従来は紙の報告書に手書きで記載し、指定の部署に提出していた業務を、PCやデバイス上で作成した報告書のフォーマットに入力し、社内システム上で社内ネットワークを通じて指定の部署宛てに申請するといったことが挙げられます。
電子化との違い
デジタル化と似た言葉に、電子化があります。デジタル化と似ており、近年は同意義として取り扱われることもありますが、厳密にいえば意味合いが異なります。電子化とは紙の書類を電子データに変換することを指します。例えば、紙の請求書を電子データにする行為自体を指します。方法としては、紙の請求書をスキャンしたり、写真撮影してPCに取り込んだりすることが挙げられます。
一方、デジタル化は電子化を行った上で、活用しやすいデータに変換して活用・管理しやすい形にすることを指します。例えば、紙の請求書をスキャンして電子化しただけでは、文字をテキストデータとして扱うことができません。
そこでデジタル化では、OCR(光学文字認識)を用いてコンピューターが読み取り可能なテキスト形式に変換するか、はじめから請求書をExcelファイルとして作成してPC上で文字入力してデジタルデータにすることなどが挙げられます。
電子化はデジタル化の一部であるといえます。
デジタイゼーション・デジタライゼーション・デジタルトランスフォーメーションの違い
近年、デジタル技術を用いてビジネスモデルなどを変革するための活動「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が推進される中、そのDXに至るまでの第一段階として「デジタイゼーション」、第二段階として「デジタライゼーション」という言葉が取り上げられるようになりました。デジタル化というのはこれらの言葉と比較して抽象的な概念であり、どちらもデジタル化の一部分を表しています。
総務省では、それぞれ次のような定義を示しています。
「デジタイゼーション」:既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること
「デジタライゼーション」:組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること
「デジタルトランスフォーメーション」:企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること
出典:総務省「令和3年 情報通信白書」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112210.html
デジタル化できる社内の対象
・社内外のコミュニケーション
対面や電話、FAXでのやりとりをメールやチャット、コミュニケーションツールへと変換します。
・事務作業
文書作成や共有など紙やアナログの手段から、電子化や共有化を進め、デジタル化します。
・契約・申請業務
紙の契約書や申請書をデジタルに変換もしくははじめからデジタル形式で作成します。
・営業・マーケティング活動・顧客管理
営業やマーケティングにおいてはメールや商談ツールなどの顧客とのコミュニケーションツールの利用や、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)、マーケティングオートメーションといった管理ツールの利用が挙げられます。
社内におけるデジタル化のメリット
社内でデジタル化を進めると、次のようなメリットが期待できます。
・業務効率化・生産性向上につながる
社内においてデジタル化を進めることでデータの共有・管理が容易になったり、自動化できたりすれば業務効率化と生産性向上が実現します。
・手続きのスムーズ化
社内の各種申請業務や手続きをデジタル化することで、従来の紙の書類を手渡しもしくは拠点間での郵送・FAXよりも効率化します。
・取引先とのやりとりなどデジタル化の流れに対応できる
取引先との発注書や請求書などのやりとりをデジタル化することで、インターネットやネットワークを通じてスムーズに行うことができます。
・BCP対策になる
BCPとは、事業継続計画のことを差し、企業が地震などの自然災害や大火災、パンデミック、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇したシーンで事業資産の損害を最小限に留め、企業の中核となる事業を継続させるため、停止してしまった場合は早期復旧のために行う活動を指します。緊急時の対応のみならず、平常時行うべき活動や準備も含まれます。
デジタル化を進めておくことはBCP対策につながります。その理由として、災害などの緊急時に従業員の安否確認や被災状況の情報共有がネットワークを通じてスムーズに行えるようになることが挙げられます。データ共有のベースが作られていれば、遠隔地同士のコミュニケーションも進めやすくなります。
デジタル化の課題
一方で、社内でデジタル化を進める際には、次のような課題がよく挙がります。
導入・運用コストが増大する
デジタル化には多くの場合にデジタルツールを新たに導入・運用しなければなりません。コストがかかることは避けられないため、デジタル化を踏みとどまるケースもあります。
ネットワークセキュリティの懸念
社内ネットワークやインターネット上でのデータのやりとりが便利に行えるようになる一方で、情報漏洩のリスクも増加します。アナログ時代にも盗難・紛失による情報漏洩のリスクはありましたが、デジタル化はそれに加えてより広範囲にリスクが広がります。
システム障害・故障時の業務停止リスク
システムやツールに不具合が生じると、業務が進められなくなる恐れもあります。バックアップや可用性(システムが継続して稼働できる能力)を高める処置は可能ですが、業務停止リスクは依然として残っており、最小限に留める必要があります。
DX化を推進する人材不足
業務をデジタル化・DX化するのに際し、それを推進するための人材が必要になってきます。社内で不足しているケースも多く、何をどこから手を付ければいいかわからないという状況に陥っている企業も多くあります。

デジタル化を効率的に推進する方法
では、デジタル化の課題に対応し、効率的に推進するにはどうすればよいのでしょうか。主な方法をご紹介します。
目的を明確にする
ただ単にアナログ業務をデジタル化すること自体を目的にするのではなく、企業成長や事業発展、経営戦略、目的に基づくデジタル化を推進することが重要です。
導入・運用コストは、費用対効果が重要になりますが、目的を明確にすれば目標が立てやすくなるでしょう。
目的を明確にして戦略的にデジタル化を実施していくことで、リスクへの対応やDX人材の育成や採用も組織的に実施していくことができると考えられます。
現場の声を取り入れる
デジタルツールの費用対効果を高めるために、現場で有効活用できるかどうかを事前に検証しておく必要があります。現場の声を十分に取り入れた上で導入すれば、成果が出やすくなるでしょう。
業務整理を率先して行う
まずは現場課題を検証し、業務整理を行いましょう。どの業務を優先してデジタル化すべきかが明確になります。効果の出やすい部分から実施していくことで、成果をもとに水平展開していくことができます。
効率化できる最適なツールを導入する
デジタルツール導入の失敗を防ぐには、最適なツール選びが欠かせません。課題を解決できることはもちろんのこと、現場で使いやすいかどうかという視点で選ぶことをおすすめします。
まとめ
デジタル化の概要や社内で進める上での課題、課題対応策や効率化のための方法をご紹介しました。デジタル化の度合いは各社で異なりますが、どの段階においても、費用対効果の望める、最適なデジタルツールの導入が欠かせません。ぜひ自社に合ったツール選定を行って、デジタル化を成功させましょう。
TOPPANでは、カタログのデジタル化を推進できる「iCata」というサービスをご提供しております。
PDFのカタログや資料をデジタル化しマルチデバイスで閲覧できるサービスで、自社のカタログのほか、他社が一般公開しているデジタル化されたカタログも閲覧できるのが特徴です。何千冊ものカタログをアプリ一つで管理できるので重い紙のカタログ持ち歩かなくて済むほか、必要なカタログの最新版を常に閲覧できるので、営業先にも手軽に提示できます。
詳細はサービスページをご覧ください。
関連コラム
2024.05.15