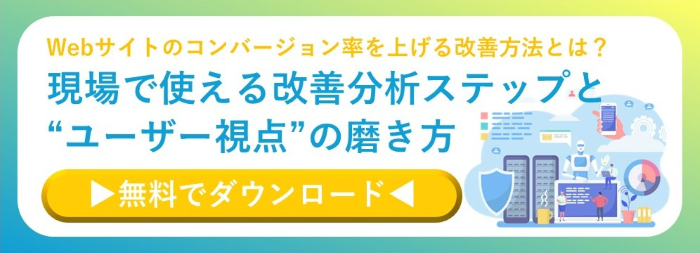Webサイト分析とは?
分析ステップからよくある課題、解決に役立つツールまでご紹介!
Webサイトを改善するために分析を進めたいと考えているものの、どの指標を重視すべきかわからない、分析結果から具体的な改善策を立てられないなどと悩んでいる担当者の方もいるのではないでしょうか。Webサイト分析はポイントを押さえて実施することで、効率的に進めることができ、Webサイト改善の効果を出すことが可能です。
今回は、Webサイト分析の概要から目的、一般的な分析手法、具体的なステップ、役立つツールまでご紹介します。Webサイト分析を始めたい方や、Webサイト改善を強化したい方は、ぜひご覧ください。
<目次>
1.Webサイト分析とは?ポイントを解説
2.Webサイト分析のステップ
3.Webサイト分析のよくある課題
4.Webサイト分析の課題解決に役立つ生成AI活用の「Sprocket Insights」とは?
5.まとめ
1.Webサイト分析とは?ポイントを解説

まずはWebサイト分析の基本から確認していきましょう。
Webサイト分析とは?
Webサイト分析とは、Webサイトをあらゆる角度から分析して課題を特定するための取り組みです。
Webサイト分析の目的は、実施する企業や担当者によってその都度変わりますが、主に次のものが挙げられます。
・Webサイトの成果を出すための改善策を見つけるため
・Webマーケティング施策後のWebサイトにおける効果測定のため
・Webサイトの現状を把握し、問題点が見つかった場合には改善を検討するため
「コンバージョン率が低い」「アクセス数が少ない」など具体的な問題が発覚したことをきっかけに取り組んだり、直近でWeb広告を打ったため、Webサイトへのアクセス状況はどう変化したのかの確認のために実施したり、日々のWebサイトのモニタリングにおいて問題点が検出された場合に中長期的に改善するために実施したりなど、さまざまな目的で実施されています。
いずれにしても、Webサイト分析はWebサイトの成果創出に向けて改善するために行われます。
Webサイト分析の基本ポイント
Webサイト分析の詳しいステップは後ほどご紹介しますが、実施の基本ポイントとして、次の2点があります。
・目的を明確にする
Webサイト分析において何より大事なのは、「何ために行うのか?」を明確にすることです。ただ漠然と分析ツールの画面とにらめっこしているだけでは、無駄な時間に終わってしまいます。
まずはWebサイト分析そのものの目的と具体的なゴールを設定し、逆算する形で「何を行う必要があるのか?」を明確にしましょう。
・定量分析と定性分析の両方をバランスよく取り入れる
分析には大きく分けて数値データで分析する「定量分析」と、数値以外の情報から分析する「定性分析」があります。ツール分析を行っているとつい定量分析に偏りがちですが、ユーザーテストやアンケート調査などを通して行う定性分析ではユーザーの心理や行動、ニーズなど重要な情報を把握しやすいため、成果を創出するために重要です。
まずは定量分析を実施し、量的データから「何が起きているか」の現状を把握し、問題点を把握した後、「なぜそれが起きているのか」を明らかにするために定性分析を行うことで分析がスムーズに進みます。
このように両者の役割の違いによって明確にすみ分けを行い、バランスよく取り入れましょう。
一般的な分析手法
Webサイト分析の一般的な分析手法をご紹介します。
【定量分析】
・アクセス解析によるユーザーの行動分析
・アクセス解析によるCV(コンバージョン)に関係するページ分析
・アクセス解析によるECサイトの商品購入ページの分析
【定性分析】
・ヒートマップ分析によるクリックの多い部分、じっくり読まれた箇所の分析
・ユーザーテストによる行動観察・フィードバック分析
・アンケート調査による使い勝手や閲覧しやすさ、わかりやすさ、印象などの情報取得・分析
2.Webサイト分析のステップ

Webサイト分析は、ただ闇雲に行うだけでは目的を達成できません。次のステップを踏んで確実に目的達成と成果につなげましょう。
【STEP1】Webサイト分析の目的の明確化
何よりもまずWebサイト分析自体の目的を明確にしましょう。先述の通り、目的を明確にすることでWebサイト分析の意義が生まれます。
まずWebサイトの構造理解を行った上で、Webサイトそのものの目標整理を行い、目標達成に至らない課題を洗い出しましょう。
例えばWebサイトの目的が「見込み顧客の集客と資料請求」であれば、課題として「アクセス数が伸びない」「CTA(※1)ボタンのクリック率が低い」「CV率が低い」等が課題として上がってきます。これらの課題のうち、最も改善を急ぐべきところから分析していきます。
優先度を決める基準は、ただ「簡単ですぐできるから」などではなく、改善によって得られる効果が高いものを選びましょう。その際、必要なコストやノウハウの有無、人的・時間的リソースも加味することがポイントです。
※1 CTA:Call to Actionの略で、Webサイト上の行動喚起を指す。商品購入ボタンや資料請求バナーへ誘導部分のこと。
【STEP2】仮説を立て、指標を特定する
課題が生じている原因を予測し、仮説を立てます。またWebサイトの分析目標を具体的にKPIの数値として設定しましょう。
例えば、CTAボタンのクリック率が低い場合、「誘導文言の文字が小さくてわかりにくい」「CTAボタンの色が目立たない」「ファーストビューにCTAボタンがない」などという仮説を立て、KPI(目標値)として「クリック率●%」「CV率●%」などを具体的に設定します。その目標を達成するために必要なアクションを検討し、実行します。
【STEP3】分析ツールによる仮説検証
改善策を実施したら、分析ツール等で仮説検証を行います。例えば先ほどの「誘導文言の文字が小さくてわかりにくい」という仮説検証であれば、文字を大きく改善した後にクリック率やCV率を計測し、改善するかどうかを見ます。
主な分析ツールとして、次のものが挙げられます。
・Google Analytics 4:アクセス解析ツール。ページビュー数やCV率などが計測可能。
・Google Search Console:Webサイト管理ツール。Google検索における掲載順位や流入キーワード、クリック率などを計測可能。
・PageSpeed Insights:ページの読み込み速度を計測可能。
・Sprocket Insights:生成AIによる高精度なユーザー行動や経路などの多様な分析から仮説立案、改善策の提案が可能。
※Google Analytics 4、Google Search Console、PageSpeed Insightsは、米国およびその他の国におけるGoogle LLCの商標または登録商標です。
【STEP4】改善策実行・仮説検証の繰り返し
仮説は複数立て、改善策を実行しては検証する作業を繰り返しましょう。立証された仮設があれば、本格実施するなどして強化します。
3.Webサイト分析のよくある課題

Webサイト分析を進めるにあたって直面しがちなよくある課題と、その解決案をご紹介します。
無料ツールでは正確なところややるべき施策がわからない
アクセス解析やSEOツールの多くは無料で提供されていますが、無料版では機能制限があることもあり、どうしても限界があります。よくあるのが、無料で手軽に行えることに意識が集中してしまい、肝心のWebサイト分析の目的が忘れ去られてしまうことです。
Webサイト分析の目的は、改善によるWebサイトの成果創出にあるため、無料ツールで分析した結果、改善策がわからなければ、どんなに多くの情報を入手できたとしても意味がありません。「やるべき施策は何か?」を明確にする仕組みが必要です。
解決策の一つは、サイト分析が可能であるのはもちろん、その分析結果をどうサイト改善に活かすかを提案してくれる有料ツールを選ぶことです。近年はAIツールも増えていますが、Webサイトの改善策を提案するAIを搭載した有料ツールも出てきています。専門家にアドバイスをもらうこともできますが、自社で独自に実施する場合は有効な有料ツールを利用するのが良いでしょう。
どの指標を重視すればいいかわからない
サイト分析で重視すべき指標がわからないという課題です。例えば「急にCV数が下がった」場合、直近で何か施策を実施したのであれば、その施策が原因の可能性が高いですが、直近で何も施策を行っていない場合は困ってしまいます。「どこを見ればいいのか?」がわからず、見るべき指標がずれてしまうということがあります。
予防策として、基本の指標を決めておき、全体を俯瞰して計測する習慣を持つこと、そして時系列で変化を見ることが挙げられます。さらに、Google検索のアルゴリズム(※2)や市場環境の変化が関係していることもあるため、外部環境についても常に最新情報を得ておきましょう。
またAIが重要な要因を特定するツールを利用することも有効です。自身で迷いながら指標を選ぶよりも、AIが分析結果をもとに提案してくれるものを利用するほうが効率的ですし、精度も高まります。
※2 Google検索のアルゴリズム:主にキーワード検索結果の順位を決めるルールのこと。
具体的な改善策を立てられない、工数がかかりすぎる
サイト分析結果を目の前にして、問題は浮き彫りになったものの、自信のある仮説が立てられない、または仮説が多すぎる、意思決定が困難などの事態に陥ることがあります。チームメンバーと専門家を含めて議論を重ね、何十時間かかってようやく決定するなど、工数がかかりすぎることもよくある課題です。
この課題については専門家に一任する、A/Bテストで複数の仮説を同時検証するなどの解決策があります。またAI搭載ツールにおいては、複数仮説を高速で検証する機能が備わったものが出てきているため、ぜひ押さえておきましょう。
4.Webサイト分析の課題解決に役立つ生成AI活用の「Sprocket Insights」とは?

先ほどご紹介したサイト分析ツールでは、TOPPANが導入を支援している株式会社Sprocketが提供する「Sprocket Insights」がおすすめです。
「Sprocket Insights」とは?
Webサイトに潜む課題を抽出し、改善策を導き出すWebサイト改善支援分析ツールです。グラフ等で次なる改善策を可視化するため、簡単に確認できます。
さらに、仮説を立て、要件定義を行い、改善策を実行します。生成AIによる高度な分析と改善策の提案機能により、スピーディーなPDCAの実践が可能です。
特徴
・わかりやすく可視化されるため、データ分析業務が効率化される
・分析スキルが不足していても理解でき、迅速な施策立案、実施につながる
・データ分析業務が高速化し、PDCAの回転率がアップする
注目の分析機能
・ユーザー行動経路分析:Webサイト内のユーザー行動経路を可視化し、課題と対策を生成AIが提案。CVまでのボトルネックをAIが特定し、次の解決策を提案します。
・ロイヤリティ要因分析:KGI(最終目標)とKPI達成に貢献している要因を独自のロジックで定量的に分析して表示。最終的な成果に貢献している要因を可視化し、優先すべき改善点を明確にします。
・N1分析:特定の行動をとったユーザー群からランダムにピックアップし、行動履歴としてタイムライン表示。なぜそのユーザーは離脱したのか、一人ひとりの行動履歴から要因を深掘りします。
事例を通じた導入効果
TOPPANは社内実践事例として、自社サイトに活用しました。資料ダウンロードを促進するために「人が立案した企画」と「Sprocket Insightsの分析機能による企画」とを比較した結果、ツール利用の企画工数は、人による企画と比べて73%削減を実現。成果も1.7倍に向上しました。
5.まとめ
Webサイト分析は、目的とゴールを明確にし、単なるツール利用で終わらないように進めるのがポイントです。また効果測定とさらなる改善策の立案、実行を継続すること、できるだけ工数をかけずに精度の高い改善策を実施する仕組みを作ることもおすすめです。
TOPPANがご提供する生成AIを活用したWebサイト改善支援分析ツール「Sprocket Insights」は、Webサイト分析・改善策の企画・実行のPDCAサイクルを高速化します。ぜひお気軽にご相談ください。
2025.10.28