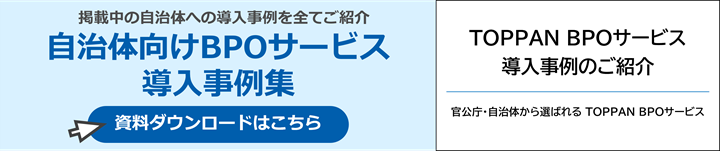特定健診の受診率が低い原因は?
対処法と受診率向上のためのポイント
近年、国内では、特定健診の受診率が低いことが問題視されています。受診率を向上させ、生活習慣病につながる状況を早期に発見し、健康寿命を延伸するとともに、医療費削減につなげる必要があります。
今回は、自治体に向け、特定健診の受診率が低い原因から特定健診の受診率向上のための取り組みにおいて直面する課題、その解決策とポイントまでご紹介します。
■特定健診の受診率が低い原因
まず、特定健診の概要と共に、受診率が低い原因をご紹介します。
●特定健診とは
特定健診は、正式には「特定健康診査」と呼ばれ、生活習慣病の発症や重症化の予防のために、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診です。
対象は医療保険の被保険者のうち、40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者であり、質問票(服薬歴、喫煙歴等)、身体計測、理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液検査、脂質検査、血糖検査、肝機能検査、検尿が基本的な検査項目となります。
健診の結果、一定の条件に当てはまった方には特定保健指導を行います。
特定健診の費用は健診機関や自治体によって異なります。多くの自治体では無料で受診券を配布しており、年1回受けられるようにしています。
●特定健診の受診率
国内の特定健診の受診率はどのくらいなのでしょうか。厚生労働省による令和5年度都道府県別特定健診受診率調査の結果、全国平均で59.7%でした。年々伸びてはいるものの、全国目標である70%にはまだ届いていません。
●特定健診の受診率が低い原因
特定健診の受診率が低い原因として、次の点が考えられています。
・特定健診の年齢に達していることを知らない
・受診の時間が取れない
・受診に費用がかかることがある
・いつでも医療機関を受診できるから必要ないと思っている
・受診そのものが面倒に感じてしまう
特定健診の対象年齢についてそれほど認知が進んでいません。40歳になった時に「特定健診を受けられる年齢になった」と知る機会を得られていないと考えられます。
また、特定健診は1時間程度で終了しますが、事前予約や医療機関への移動などを考えると仕事を長時間抜ける必要があり、休暇を取る必要があることもあります。そのため、働き盛りの世代は受診の時間がなかなか取りにくいという実情があります。
受診したいけれど無料券が手元になく、費用がかかる場合はどうしても敬遠されがちです。
また現状では体に異常を感じておらず、気になることがあればいつでも医療機関を受診できるため、わざわざ受診しなくてもいいという状況もあるようです。そして、がん検診には興味があっても特定健診には興味が湧かないということもあります。
また受診の手続きが面倒など、手間を感じてしまうこともあります。
■特定健診の受診率向上が自治体に強く求められている理由
特定健診の受診率向上は、単なる健康意識の啓発に留まらず、自治体運営における財政健全化や法的義務の遂行という極めて重要な側面を持っています。現在、全国の自治体がこの課題に注力している背景には、以下の3つの大きな理由があります。
●周知・広報の多角化による認知の徹底
厚生労働省が主導する「第4期特定健診・特定保健指導」の期間(2024年度〜2029年度)において、国は全国平均の受診率目標を70%と定めています。これまでの推移を見ると、全国平均は緩やかに上昇しているものの、依然として目標値との間には隔たりがあります。自治体は保険者として、この高い壁を乗り越えるための実効性のある計画の策定と、具体的なアクションを強く求められるフェーズに入っています。
●受診環境の整備による利便性の向上
最も直接的な理由として挙げられるのが、後期高齢者医療制度を支えるための支援金の多寡です。特定健診や特定保健指導の実施状況が芳しくない自治体に対しては、国に納める後期高齢者支援金が最大10%加算されるという厳しい財政的ペナルティが存在します。
逆に、成果を上げた自治体には支援金の減算というインセンティブが与えられます。この加算・減算制度は自治体の予算規模に大きな影響を及ぼすため、受診率向上は財政を守るための必須課題なのです。
●未受診者への個別勧奨の実施
特定健診は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を早期に発見し、重症化を未然に防ぐための強力な武器です。もし受診率が低いまま放置されれば、数年後には透析導入や脳血管疾患といった重篤な合併症を患う
住民が増え、それに伴う自治体の医療費負担も著しく増大します。住民が健康で自立した生活を送れる期間、すなわち「健康寿命」を延ばすことは、医療費・介護費の適正化を実現し、持続可能な街づくりを行う上での基盤となります。
このように、特定健診の受診率向上は、国の方針への適合、自治体財政の安定化、そして住民のQOLの維持という、三位一体の意義を持っています。これらの理由から、多くの自治体で新たな受診勧奨のあり方が模索されています。
■特定健診の受診率を向上させるための一般的な施策とアプローチ
受診率の低迷という課題に対し、多くの自治体では多角的なアプローチによってその打開を試みています。主な施策は「認知の拡大」「利便性の向上」「個別の動機付け」に分類されますが、これらをいかに効率よく、ターゲットに届く形で実施するかが成功の鍵を握ります。
●周知・広報の多角化による認知の徹底
まずは、住民が「自分が特定健診の対象であること」を正しく認識し、そのメリットを理解してもらうための広報活動です。従来の広報紙や公式ウェブサイトへの掲載に加え、近年ではSNSを活用したプッシュ型の情報発信や、公共施設、スーパー、金融機関など、生活動線上のポスター掲示を強化する動きが加速しています。対象者の年齢やライフスタイルに合わせ、目に留まりやすい媒体を使い分けることが一般的になっています。
●受診環境の整備による利便性の向上
仕事や家事で忙しい現役世代にとって、平日の日中に医療機関へ足を運ぶのは容易ではありません。このハードルを下げるため、休日や夜間の健診実施、ショッピングモール内での集団健診、さらには地域を巡回する健診車の運行など、受診場所や時間の選択肢を増やす工夫が行われています。また、がん検診とセットで受けられるセット健診の推進により、一度の来場でまとめて検査を済ませたいというニーズにも応えています。
●未受診者への個別勧奨の実施
一度の案内では動かない「無関心層」や「受診忘れ層」に対しては、ハガキの再送付や電話による督促、アウトバウンドコールなどの直接的な働きかけが有効です。
特に電話での勧奨は、相手の事情を直接聞き取りながら不安を解消できるため、高い効果が期待できます。このように個々の受診状況に合わせたきめ細やかなリコール活動を継続することが、受診率の底上げには不可欠です。
●インセンティブの付与
受診することそのものに「おトク感」を持たせるため、地域の店舗や公共施設で使えるポイントや商品券を付与する施策も広まっています。この「健康ポイント事業」は、健康に関心が薄い層にとっても受診する直接的な動機となり、ポジティブなイメージを醸成するきっかけとなります。単なる義務感ではなく、楽しみながら受診できる仕組みづくりが、多くの自治体で注目されています。
これらの施策はどれも重要ですが、自治体の限られた人的リソースだけで全てを高いクオリティで実施し続けることは難しく、結果として「現場の疲弊」という新たな課題を生んでいる側面もあります。
■特定健診の受診率向上のための取り組みにおける課題
特定健診の受診管理や指導を実施している自治体は、受診率向上のためにさまざまな取り組みを進めていますが、次のような課題に直面しています。
●チラシを送付しても見てもらえない・見てもらえても受診につながらない
特定健診の受診勧奨の方法は、多くの場合、郵送物によるものです。送付する郵送物にはチラシなども封入しますが、それらを送付してもそもそも開封してもらえなかったり、開封して目にしてもらえても受診しようとは思われなかったりして、受診率向上につながらないことも課題の一つです。
●個別電話、夜間訪問などでの勧奨は業務負荷が高い上に成果が出ない
郵送物の送付だけではなかなか受診につながらないため、特に必要と思われる対象者に個別に電話したり、仕事の帰宅後の時間、夜間に自宅を訪問したりすることもあります。しかし、電話や訪問を1件ずつ実施するのは自治体職員にとって業務負荷が大きいものです。
また実施しても、思うような成果が表れてこないことも課題となっています。
●職員のスキル向上による健診受診率のアップには限界がある
個別電話や訪問の成果が出ないのは、職員のスキル不足が問題だという視点もありますが、スキル向上を実施したとしても、先述の通り、受診しない理由は多岐にわたるため、受診率の向上には限界があるのが実情です。
■特定健診の受診率向上のための対処法とポイント
では、上記のような課題を解決し、特定健診の受診率向上につなげるにはどうすればいいのでしょうか。課題を解決するための対策と共に受診率向上のポイントをご紹介します。
●対象者の階層化による階層別アプローチ
受診勧奨を実施する対象者は、ある程度絞り込んでいるかと思われますが、絞り込んだ後、さらに階層化し、階層別にアプローチ方法を変えるとういのも方法の一つです。受診歴・通院歴、年齢などから勧奨対象を階層別化し、グループ分けします。そして各グループを対象に最適なメッセージと手法を選定します。つまり、対象者すべてに同じ郵送物を配布するといった手法ではなく、最適なメッセージを最適な手法で届けるのです。
たとえば、40歳から59歳までの比較的若い層はデジタルに親しんでいると思われるため、SMS・ショートメッセージで勧奨を行うことで気にしてもらいやすくなります。最適な勧奨方法によって受診率の向上を目指すことが可能です。
●特定健診受診者へのインセンティブを検討
特定健診を受診するとポイントがもらえて、ポイント数に応じて地域の特定店舗で割引サービスが受けられるといったインセンティブを付与する自治体もあります。特定健診の受診にそこまでメリットを感じない中高年に、特に有効な施策といえます。
●「健診の手引き」の冊子改善
健診の手引きとは、特定健診などの健康診断の目的や内容、手順、注意事項などをまとめた手引書で、薄い冊子やチラシ形式で作成・配布されることが多い資料です。
この健診の手引きが見づらく、わかりにくいものだと、特定健診への関心も薄れてしまうでしょう。そこでレイアウトやデザインを改善する試みも有効です。
実際に、文字量・色覚・視線予測を実施し、見出しの文字サイズを大きくしたり、項目ごとに色分けしたりしてわかりやすくした事例があります。受診目的の明確化や予約などのアクション指示の単純化などを実現します。
●BPOの活用
BPOを利用して、特定健診の受診勧奨をアウトソーシングすることも有効な手段であり、近年、自治体での活用も進んでいます。
BPOとは「Business Process Outsourcing」の略で、ビジネスプロセスのアウトソーシングを意味しますが、単なる「アウトソーシング」の意味合いだけではなく、対象業務を効率化し、より質の高い業務レベルにまで引き上げ、業務の成果を高めるために利用されています。
受診勧奨の業務経験のあるBPO事業者に委託すれば、自治体職員の負荷を削減できる上に一定の効果が期待できます。
■受診率向上が自治体と住民にもたらす具体的な成果とメリット
適切な戦略とBPOの活用などによって受診率が向上することは、単に目標数字を達成すること以上の、大きな実りをもたらします。自治体運営の安定化と、住民の健やかな暮らし。この双方が手にする具体的なメリットを整理します。
●自治体側が享受する財政の安定と業務の最適化
自治体にとっての最大のメリットは、先述した支援金加算の回避による財政への貢献です。受診率の目標達成によりペナルティを回避し、逆にインセンティブを得ることで、自治体全体の予算編成にゆとりが生まれます。また、受診勧奨などの事務作業をBPOで標準化・効率化できれば、職員は本来の専門性が求められる健康政策の立案や個別指導により注力できるようになり、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。
●住民側が享受するQOLの維持と経済的負担の軽減
住民にとっての最大の恩恵は、病気の早期発見による健康寿命の延伸です。覚症状がない段階で生活習慣病のリスクを把握し、改善できれば、将来的に重い病気で苦しむリスクを最小限に抑えられます。これは、生涯にわたって高いQOL(生活の質)を維持することに直結します。また、病気が進行してから必要となる高額な治療費や入院費を回避できるため、住民自身の経済的な安心感も大きく向上します。
●データ活用による個別最適化された健康支援の実現
受診率が向上し、より多くの住民データが蓄積されることで、自治体は一人ひとりの健康状態に合わせた、より精度の高い支援が可能になります。例えば、リスクが高い層へ集中的にリソースを割くといった選択と集中が行えるようになり、限られた予算で最大の健康効果を生み出すことができます。受診率の向上は、こうした住民一人ひとりに寄り添った行政サービスを実現するための、最も重要なデータベースを構築する行為でもあるのです。
受診率向上は、自治体にとっては健全な財政と持続可能な行政サービスを確保するための鍵であり、住民にとっては一生涯の安心を手に入れるための手段です。この相乗効果を最大化することこそが、受診勧奨施策の真のゴールと言えるでしょう。
■TOPPANの特定健康診査受診勧奨支援パッケージとは?
TOPPAN BPOでは、自治体さまの業務を幅広く承っていますが、特定健診の受診勧奨における実績も多数有します。その実績と蓄積したノウハウを基に「特定健康診査受診勧奨支援パッケージ」をご提供しております。
●特定健康診査受診勧奨支援パッケージとは
本サービスは、特定健康診査の対象者分析によるグループ分けから、勧奨コンテンツの提供、勧奨業務、報告書作成まで一括で支援するものです。
データ受領から分析・グループ化、コンテンツ制作まで汎用化されたパッケージを活用することで短期間での実施が可能です。
●特定健康診査受診勧奨支援パッケージの特徴
特徴は、TOPPAN独自の分析システムによる対象者のグループ分けを行った上で、オリジナルの勧奨コンテンツを活用して健診の受診率向上につなげられる点です。
・対象者を7つにグループ分け
特定健診の検査結果などのデータ分析により対象者を7つにグループ分けし、勧奨に適切な対象者を分類します。
・各グループに応じた勧奨コンテンツ
7つのグループごとに対象者特性に応じた、ナッジ理論を活用した勧奨コンテンツをご用意しています。
対象者の特性に応じた「自分事化」させる勧奨コンテンツと各種勧奨方法の提供から実施後の報告書作成まで、一括した業務支援を行い、担当者さまの業務負荷を減らします。
●勧奨方法
勧奨方法は、次の3種類に対応しています。
・通知物
・電話
・SMS・ショートメッセージ
健診受診率の低いグループや、特に注力したいグループに合わせた勧奨方法の選択、組み合わせにより、最適な勧奨方法を検討し、受診率の向上を目指します。
ご興味のある方は、まずはお気軽にご相談ください。
2025.06.23