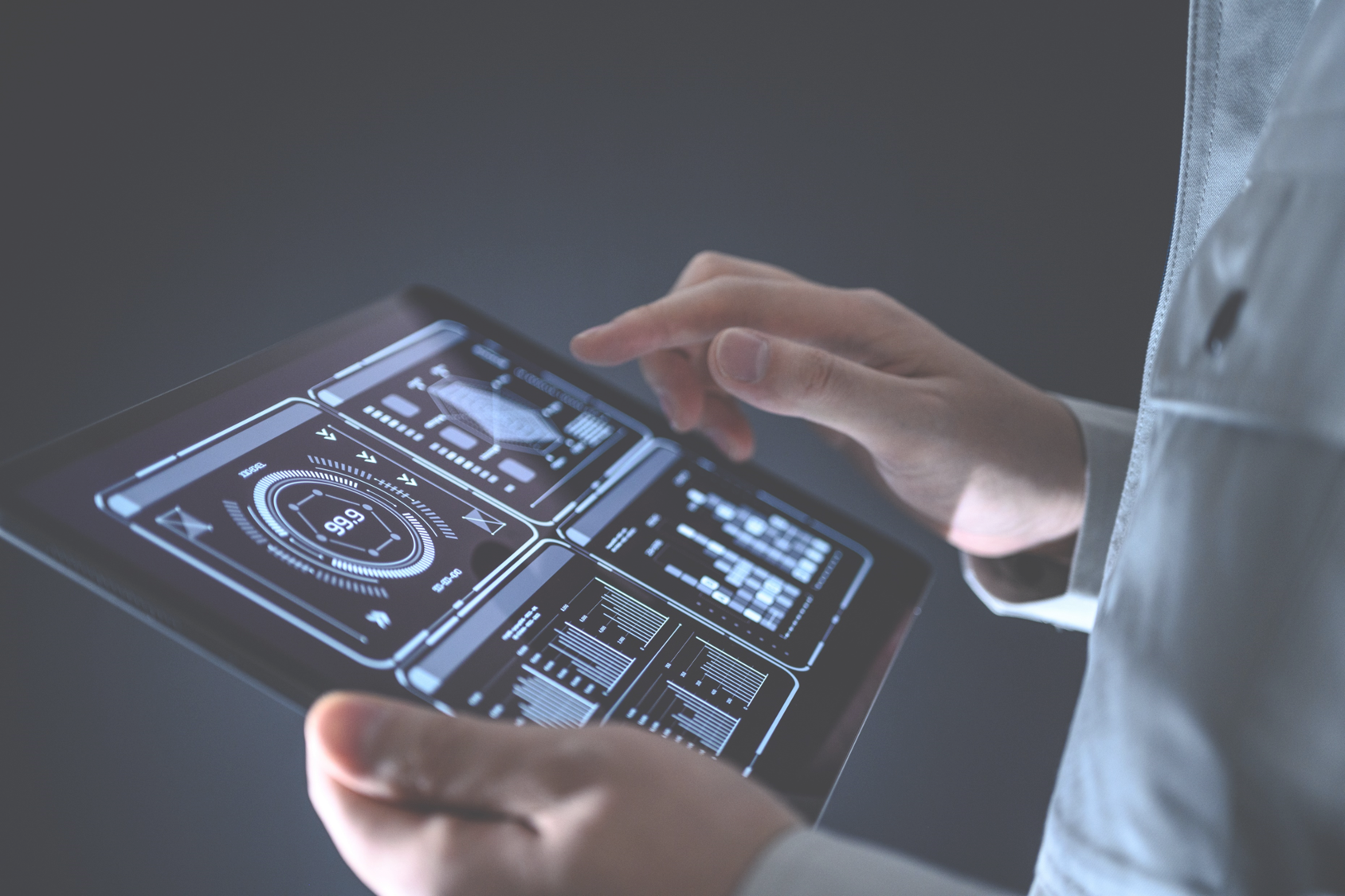工場における熱中症対策をご紹介
工場の熱中症対策においては、暑さ指数や気温を常時把握し、換気・冷房や休憩を徹底することで、
熱中症を起こさない現場づくりを進めることが重要です。
また体調確認を習慣化し、こまめな水分・塩分補給や通気性の良い服装の推奨も欠かせません。
近年は気候変動の影響もあり、夏においては非常に高温になる日が多いです。
一見、熱中症が起きにくいように思える工場や倉庫内などの室内でも
熱中症発症のリスクは存在しているため、日ごろから熱中症対策を実施する必要があります。
また、厚生労働省から2025年4月15日に「労働安全衛生規則」の一部改正が発表され、
事業者に対して現場における熱中症対策を徹底する動きが進んでいます。
本コラムでは、熱中症の発症原因や、対策についてご紹介します。
<目次>
■熱中症とは
■熱中症の発症原因
■暑さ指数・WBGTとは
■工場における熱中症リスクについて
■工場における熱中症対策
■現場機器などを使った冷却対策
■工場における熱中症対策をサポートするe-Platch
■まとめ
■熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境で長時間活動することによって、
体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、
体温調節機能が十分に働かなくなったりすることで起こる健康障害の総称です。
熱中症の主な症状として、めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気などがあり、
さらに重度になると意識障害や、けいれんなども起きる可能性があります。
また、最悪の場合は命にかかわるケースもあるため、
発症した場合はできるだけ早期に対策をとることが重要です。

■熱中症の発症原因
熱中症は、体から熱が放出されにくくなることで発症しやすくなります。
このような状態は、下記のような原因から引き起こされる可能性が上昇します。
・高気温、高湿度、強い日差しなどの外的環境の条件
・栄養・水分不足、暑さに慣れていないなどの身体的な条件
・長時間にわたる屋外作業、水分補給忘れなどの行動の条件
そのため、単に気温が高いから熱中症が起きるわけではなく、
「身体が暑い」と感じやすいような状況において起きやすいといえます。
例えば、同じ気温の状態で作業を行う場合も、
こまめに水分補給を行ったり、日光を避けるようにすることでリスクの低減が可能です。

■暑さ指数・WBGTとは
ここまで説明してきた通り、熱中症のリスクを可視化するためには、
気温の計測だけではなく、体から熱が放出されにくい状態を可視化する必要があります。
このような状態を指標化したものが「暑さ指数」で、
熱中症のリスクを把握するためには暑さ指数の計測が推奨されます。
暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)とは、
熱中症を予防することを目的として、
人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標です。
温度と同じく単位は「℃」を使用しますが、
単なる気温とは異なる指標で、WBGTを算出するためには熱収支に与える影響が大きい
気温・湿度・輻射熱(・風)を計測する必要があります。
このように外気の状態を把握することで、熱中症リスクの把握が可能になるため、
熱中症が起きやすい状態の把握は、一般的な温湿度計のみでは難しく、
黒球温度・湿球温度・乾球温度が計測できるセンサーの使用が好ましいです。
また、従来より、熱中症対策においてWBGTは注目されていましたが、
厚生労働省が「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令を2025年4月15日に公布し、
2025年6月より職場における熱中症対策強化が義務付けられることが決定しました。
・暑さ指数が28℃か気温31℃以上
・連続して1時間以上、あるいは1日あたり計4時間を超えて作業を行う場合
これらの条件に該当する従業員がいる場合、
事業者は、熱中症の疑いがある人を早期に発見するための体制整備や、
熱中症の疑いがある人が見つかった場合の対策の手順を整備し、
それらを周知することが義務付けられました。
こういった背景もあり、暑さ指数や気温などをしっかりと把握し、
そのうえで、熱中症をおこさないような現場づくりを進める重要性が増しています。

■工場における熱中症リスクについて
事業を行う上で熱中症対策は重要性が増していますが、
令和5年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)のうち、
全体の約4割が建設業と製造業で発生しており、
製造業においても熱中症対策を意識した現場づくりを行う必要があります。
ここまで説明してきたように、熱がこもりやすい環境において熱中症は発生しやすいため、
製造業の現場である工場や倉庫においても、
・作業着を着た状態
・空調環境・換気環境が適切ではない状態
・熱を発する設備の近く
など、様々な要因によって熱中症が引き起こされるリスクがあります。
このように対策を講じないまま事業を継続することは難しくなっており、
しっかりと熱中症をおこさない対策を考慮する重要性が高まっています。

■工場における熱中症対策
本稿では工場において実施するべき熱中症対策をご紹介します。
1. 作業環境管理
まずは、WBGT値の低減を目指す必要があります。
現場においては屋根を設置したり、空調環境を整えたりすることで、
熱がこもりにくい環境を整備する必要があります。
また、連続した作業を行う場合は休憩できる場所などを整備するのも有効です。
2. 作業管理
作業の負荷や作業時の環境に応じて休憩を設定したり、
作業者を定期的に交代することによっても、リスクの低減が可能です。
作業者自身は水分不足状態に気付かない場合も多いため、
定期的に水分補強を促したり、職場で水分補給に関するルールを設定することも大切です。
前述したとおり、暑さになれていない場合も熱中症のリスクは上昇するため、
なれていない作業者に対しては、順化期間を設けることも有効です。
3. 健康管理
健康診断の結果などに基づいて就業場所の変更等の対策も重要です。
糖尿病や高血圧などの持病を抱えている従業員を把握することができれば、
従業員ごとに熱中症対策を講じることも可能です。
睡眠不足や、前日の飲酒状況によってもリスクは上下するため、
就業開始のタイミングで健康状態をヒアリングすることも有効な施策です。
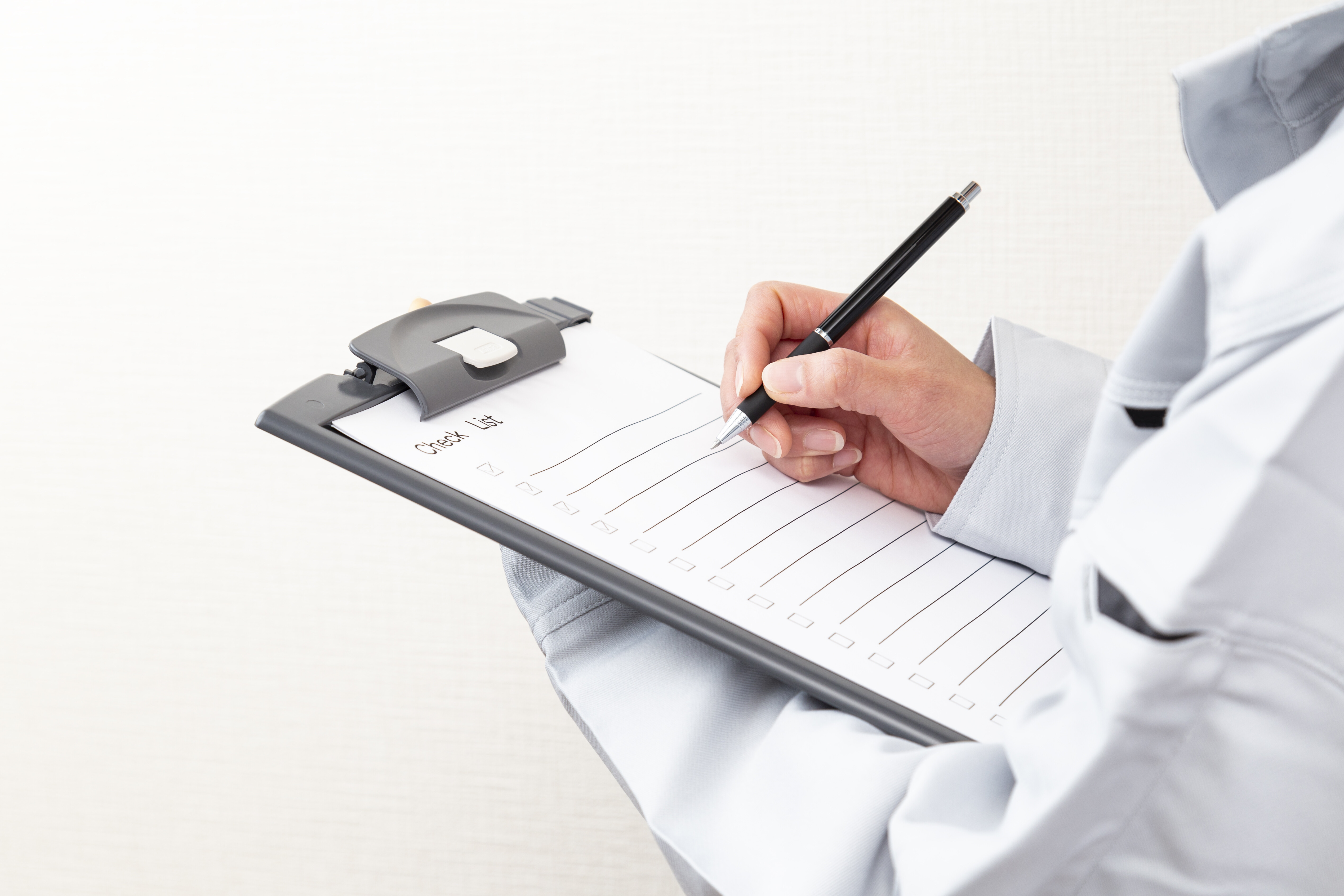
このように、実行できる熱中症対策は多岐にわたりますが、
現場の状況に応じて対策を実行することで、リスクを最小限にとどめることができます。
■現場機器などを使った冷却対策
暑さ指数の監視と並行して、現場を直接冷やす「冷却」機器の導入も重要です。
以下では製造現場を対象にした具体的な方法をまとめます。
まず、コンプレッサーなどの近くでは大型の工業用扇風機等を活用し、
室温自体を数℃下げることで熱中症の防止効果が期待できます。
作業者個人にはファン付き空調服を支給すると体調管理がしやすくなります。
ヘルメットや首元に貼れる冷却シートも同時に利用すれば、
作業中でも外へ出ずに手軽に冷却できます。
休憩所には経口補水液や塩タブレットなどを常備し、水分・塩分補給を励行しましょう。
また、熱を発する工程が複数ある場合は換気ファンを追加して暖気を排気することも大切です。
これらの対応を重ねることで、WBGT値が高い日でも安全な環境づくりが可能になります。
最後に、導入した機器は定期点検を行い、
故障を早期発見する体制を構築し、継続的に運用することが重要です。
■工場における熱中症対策をサポートするe-Platch
TOPPANが提供するe-Platchは、空間の温湿度、暑さ指数など、
現場の環境データの遠隔監視を実現するサービスです。
ここまでご紹介してきた通り熱中症対策においては、
暑さ指数の管理や、暑い状況下での作業負荷を軽減することが重要です。
ここではe-Platchで実現可能な熱中症対策についてご紹介します。
・暑さ指数などのモニタリング
e-Platchは温度・湿度の見える化に加えて、暑さ指数の見える化も可能です。
現場にセンサーを設置することで、データを遠隔地に飛ばすため、
作業者が勤務している空間環境をどこからでも確認できます。
さらに、二酸化炭素濃度の見える化も実装しているため、換気状況を確認することもでき、
従業員が働きやすい環境を保てているかを把握することも可能です。
・熱中症が起きやすいメーター巡回点検作業の負荷軽減
e-Platchは圧力や、水質データなどの現場のメーター情報を自動収集します。
メーターの巡回点検作業は、
屋上や、屋外、屋内の熱のこもりやすい環境での作業を行う必要があり、
広大な敷地をもつ現場の場合は真夏日の場合も屋外を移動して作業するため、
熱中症の可能性が排除できません。
e-Platchはこのような巡回点検作業を自動化するため、
熱中症発症リスクの高い作業を削減することができます。
■まとめ
今回は熱中症について、熱中症対策などについてご紹介しました。
年々、気温の上昇が進んでいることもあり、
継続的に熱中症対策を実施していく必要があります。
現場の状況、従業員の健康状態などを把握することでリスクの低減が可能なため、
暑さ指数を把握することは、熱中症対策の大きな一歩になります。
現場環境のモニタリングや、熱中症対策でお困りの方はTOPPANにご相談ください。
2025.08.27