学校では生成AIをどう活用すべき?
~ガイドラインや事例など~
かつてないスピードで社会に普及し、高い利便性によって社会に様々な影響を及ぼしている生成AI。教育分野においても利活用が期待されるのと同時に、情報モラルや誤った出力などのリスクも指摘されています。1人1台端末の標準仕様であるブラウザや日常的に利用する検索エンジンなどにも組み込まれている環境下において、学校では生成AIをどのように活用していくべきなのでしょうか。文部科学省作成の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(令和6年12月26日Ver. 2.0)」をもとに、解説していきます。
目次
1. 生成AIとは?
2. 学校での生成AIの活用事例
3. 生成AI利活用に関する文部科学省のガイドライン
4. 学校での生成AI活用に際しての注意点
5. 学校での生成AI活用をサポートする英作文AI添削サービス「ライップ」
1.生成AIとは?
生成AI(Generative AI)とは、人間が作成したコンテンツを学習して新たなコンテンツを生成できる人工知能技術。代表的なサービスとしてChatGPTやGemini、Claudeなどが知られています。テキスト、画像、音声、動画など様々な形式のコンテンツを“生成”できるのが特徴です。
文章を生成する場合、生成AIの核となる技術は大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)と呼ばれるもので、膨大なデータから言語パターンを学習し、人間のような文章を生成することができます。こうした技術の進化によって、生成AIは単なる情報検索ツールを超え、創造的な作業の支援や業務効率化に貢献するツールへと発展しています。
一方で企業における生成AIの活用はアメリカなど他国と比較して後れを取っており、必要なスキルを持った人材やノウハウの不足がボトルネックだといわれています。こうした課題を解決するためにも、子どもたちが早い段階から生成AIについて正しく理解し、活用に慣れておくことは重要です。
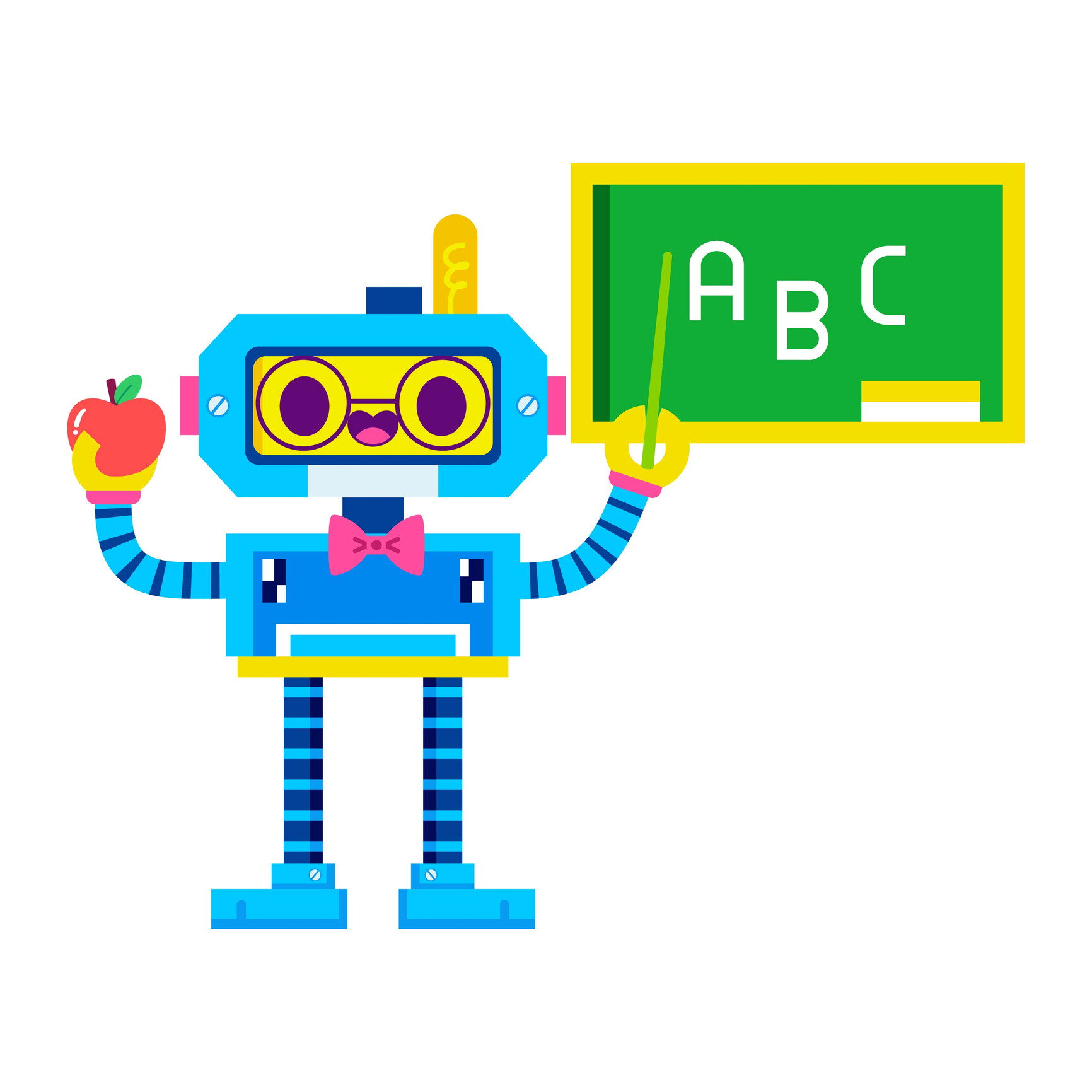
2.学校での生成AIの活用事例
学校における生成AIの活用目的には「児童・生徒による授業での利用」と、「教職員による校務効率化のための利用」の大きく2種類あります。それぞれの活用事例をご紹介します。
①授業での活用
学校現場での生成AIの適切な活用に向けて、まずは限定的な利用から始めて懸念やリスクに対策を講じるため、文部科学省は令和5年度から「生成AIパイロット校」を指定し、活用を支援しながら事例の収集を行っています。
「生成AI自体を学ぶ」「使い方を学ぶ」「各教科等の学びにおいて積極的に用いる」のように、情報活用能力の一部として生成AIを学びに活かすための力を段階的に高めながら、知見の蓄積を進めています。
生成AIパイロット校での実践事例として、作成した英作文を生成AIに入力して自然な英語表現の提案を受ける、グループでの話し合いで出た意見に対して生成AIからアドバイスをもらうなどの取り組みが行われています。自分たちだけでは足りない視点を発見して議論を深めたり、自分で考えた文章について生成AIに修正すべき箇所を指摘させたりするなど、人間主体の活動を補う役割としての活用が進んでいます。
②校務効率化での活用
生成AIパイロット校では、授業準備や事務作業などの校務の効率化に生成AIを活かす取り組みも行われています。実践事例として、学校行事の保護者案内文のたたき台作成や英語の小テストの問題作成、アンケートの集計結果の分析などが挙げられます。これらの活用によって教員の業務負担が軽減され、児童・生徒と向き合う時間の確保につながることが期待されています。
3.生成AI利活用に関する文部科学省のガイドライン
文部科学省は令和6年「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」を策定し、学校現場での生成AI活用の指針を示しました。このガイドラインでは、次の2つの「基本的な考え方」が掲げられています。
①人間中心の生成AIの利活用
生成AIを人間の能力を補助・拡張し、可能性を広げてくれる有用な道具になり得るものと捉え、出力結果を参考の一つとし、リスクや懸念を踏まえたうえで、「最後は人間が判断し責任を持つ」という基本姿勢が示されています。
生成AIの利用を目的とするのではなく、教育活動の目的を達成するために効果的かを吟味したうえで活用し、真偽や適切性を判断できることが前提となります。そのため、学びの専門職として適切な指導計画や学習環境の設定といった教員の役割はさらに重要になり、教員が一定のAIリテラシーを身に付けることが求められます。文部科学省では、教員向けの生成AI活用に関するオンライン研修会の実施や、学校現場で利用可能な研修教材の提供などのサポートを行っています。
②生成AIの存在を踏まえた情報活用能力の育成強化
生成AI時代を生きる児童・生徒にとって、生成AIの仕組みの理解や学びに活かす力の育成は非常に重要です。生成AIパイロット校に限らず、すべての学校で情報の真偽を確かめる習慣づけを含めた情報活用能力を育むことが求められます。
例えば生成AIを効果的に活用するためのプロンプトの工夫の仕方や、出力結果をうのみにせず批判的に評価する姿勢、生成AIと協働しながら創造的な活動を行う力など、AI時代に必要な資質・能力の向上を図る必要性が示されています。

4.学校での生成AI活用に際しての注意点
学校現場で生成AIを活用する際に押さえておくべきポイントがあります。活用に際して何に注意し、どのようなリスクや懸念が考えられるかを理解したうえで正しく活用することが求められます。どのようなチェックポイントを押さえる必要があるのか、説明していきます。
①ハルシネーションの可能性を考慮する
生成AIには「ハルシネーション」と呼ばれる現象があります。これは、実際には存在しない情報や誤った情報を、あたかも事実であるかのように提示してしまう特性です。こうした特性を理解したうえで、情報モラル教育をこれまで以上に充実させることが求められます。
例えば以下のような学習活動に取り組むことが期待されています。
• 情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動
• ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動
• 情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動
• 情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動
• 健康を害するような行動について考えさせる学習活動
• インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可能性がある、どこかに記録が残り完全に消し去ることはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解を促す学習活動
②個人情報やプライバシーの保護
生成AIを教育活動に取り入れる場合、成績や進路情報などのプライバシーや個人情報の取り扱いには十分注意が必要となります。児童・生徒の氏名、成績、顔写真、健康状態などの個人情報を含む内容は入力しない、必要に応じて保護者等への説明の機会や問い合わせ窓口を設ける、プライバシーポリシーや利用規約を確認するなどの対応が必要です。また、個人情報保護に関する校内研修の実施や、生成AIサービス利用に関する校内ガイドラインの策定も重要な取り組みとなります。
③著作権の保護
生成AIが作成したコンテンツの著作権や、生成AIに入力する情報の著作権についても注意が必要です。意図せず著作権を侵害してしまわないよう、著作権や知的財産権に関する基本的な考え方を理解したうえで、「この使い方は問題ないだろうか」と意識することが重要です。
例えばキャラクター名などの特定の固有名詞をプロンプトに入力するなど、既存の著作物と類似したものを意図した生成を行わない、AIによる生成物が既存の著作物と類似していないか確認する、生成AIの回答を引用する場合は出典や引用を記載するなどの著作権侵害を避ける取り組みは効果的です。
生成AIは、使い方によって教育に革命的な変化をもたらす可能性を秘めています。人間と生成AIを対立的に捉えたり、過剰に不安に思って「使用させない」のではなく、どんなリスクがあり得るか理解したうえで人間中心の利活用ができるよう、情報運用能力を育成していくことが重要です。
5.学校での生成AI活用をサポートする英作文AI添削サービス「ライップ」
英作文生成AI添削サービス「ライップ」は、生成AIを活用した英作文の的確な添削と即時フィードバックで学びを質の高いレベルで支援すると同時に、教員の添削業務を効率化できるサービスです。
「ライップ」の特徴は、単なる英文添削にとどまらず、英作文を多角的に分析し、具体的な改善点や表現の幅を広げるための個別アドバイスを提供する点にあります。また、生徒一人ひとりのAIによる添削結果や質問を、教員がリアルタイムで確認することができます。
さらに、学習に関係ない質問への回答制限や手書きへの対応など、学校現場での利用に最適化されているため、安心かつ便利に利用することが可能です。
「ライップ」についてもっと詳細が知りたいという方はぜひお問い合わせください。
2025.04.03



