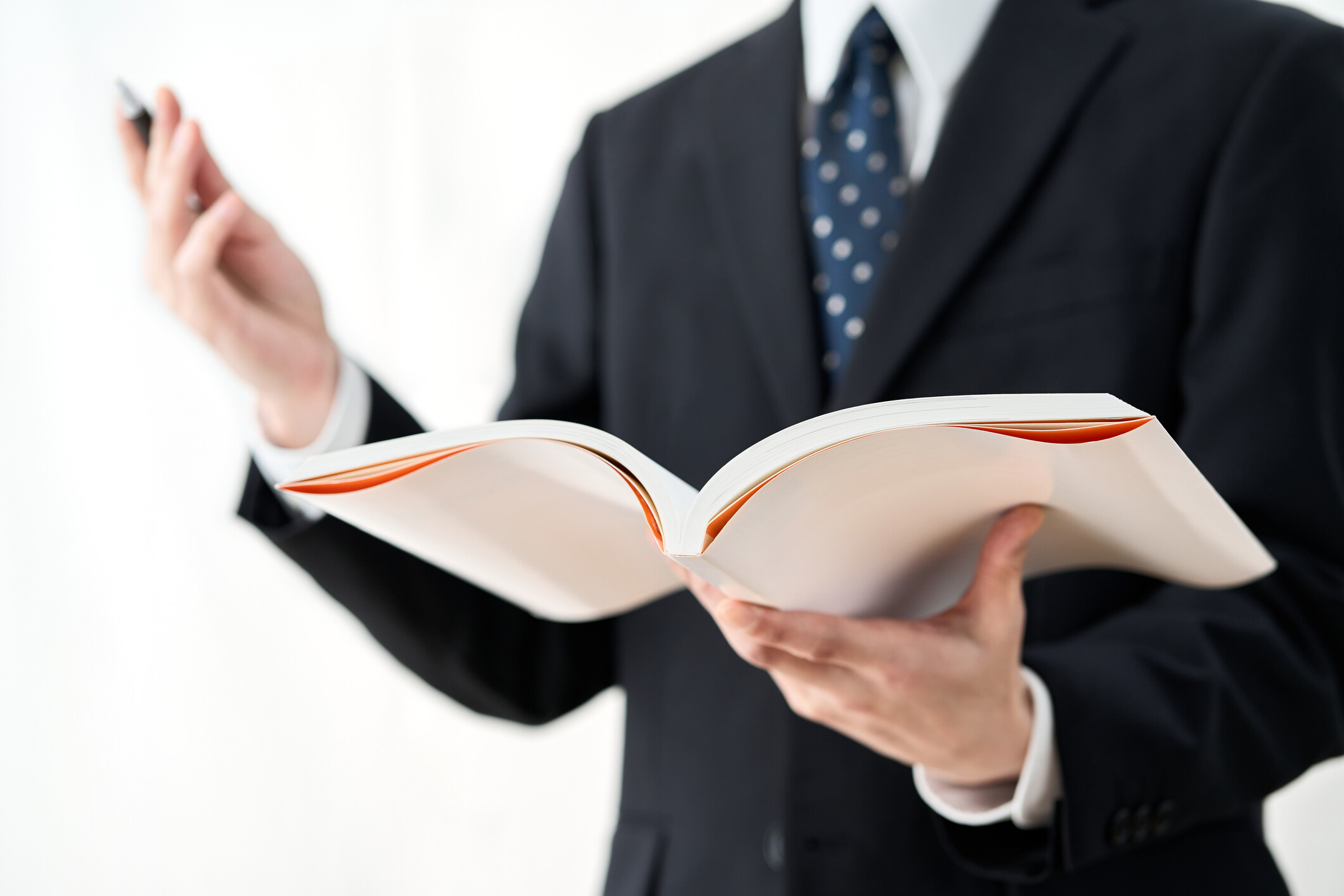教員の働き方改革
最新の取り組み事例を紹介
文部科学省が推進する、教員の働き方改革。教育の質をより向上させるためにもさらなる加速が必要です。学校で働き方改革を進めるために今すぐやるべきことを、取り組み事例からひも解いていきます。
目次
1. 教員の働き方改革を進めるべき理由とは
2. 教員の働き方改革、まずやるべき3つのポイント
3. 外部人材の活用事例
4. ICTの活用事例
5. 教員の意識改革の事例
6. 教員の作業の効率化をサポートする「navima(ナビマ)」
1. 教員の働き方改革を進めるべき理由とは
令和6年12月公表の「令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」によると、令和5年の1年間を通じた教諭の時間外在校時間が「月45時間超」の割合は、小学校で24.8%、中学校で42.5%でした。特に中学校ではまだまだ長時間残業が多い状況です。
令和6年度の教員採用試験の倍率は全体で3.2倍、小学校は2.2倍といずれも過去最低。また、採用試験に合格しても辞退する人が相次いでいることもニュースになりました。やりがいを感じられる仕事ではあるものの、長時間労働や精神的負担などから二の足を踏んでしまうようです。この状況が続けば、教員の人材確保が難しくなることも予想されます。
今後AIの導入やプログラミング学習の進化なども含めた端末のさらなる活用促進や、デジタル教科書の活用、アクティブラーニングや外国語教育への対応など、学びの変化に対応していかなければ、国際競争力の低下も懸念されます。教員がそのための時間を確保できるよう、働き方改革を進めて授業や生徒との関わり以外の作業時間を削減する必要があるのです。
2.教員の働き方改革、まずやるべき3つのポイント
文部科学省がまとめている「全国の学校における働き方改革事例集」(令和5年3月改訂版)や「令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」(令和6年12月)などから、具体的にどのような取り組みが行われているのか見ていきます。
教員の働き方改革で一定の成果につながっている取り組みから、「外部人材の活用」「ICTの活用」「教員の意識改革」という共通点が見られました。まずこの3つのポイントのなかで自校に取り入れられそうなものを検討するとよさそうです。
それぞれについて、具体的な取り組み内容を見ていきます。
3.外部人材の活用事例
教員がすべてを担うのではなく、外部のスタッフに業務委託することで負担を減らす事例として、インパクトの大きなものは部活動の地域移行です。例えば神戸市では2026年から部活動を「地域クラブ活動」に移行し、運営主体は学校ではなく地域の団体となります。
また、プールの管理やプールの授業を外部の専門業者に委託したり、いじめの対応や保護者からの過剰な苦情についてスクールロイヤーに相談し、法的観点からの助言を求めたりも。
他にも機器のメンテナンスやソフトウェアの設定をICT支援員に、プリントの印刷や入力業務、備品の整理・補充を教員業務支援員に支援してもらうなど、外部人材の活用は様々な形で広がりはじめています。
令和7年度文部科学省予算案においても、「学校における働き方改革の推進のための支援スタッフの充実等」のための予算として122億円が計上されるなど、積極的な導入を後押しする方針が打ち出されています。
さらにグループ担任制、体育等の合同授業の実施など、教員同士の連携で作業時間の確保を行っている例も見られました。
4.ICTの活用事例
デジタルを活用した業務量の削減例として、情報共有方法の変更が挙げられます。例えば、時間割や年間行事、指導案、会議資料などをデジタル化してクラウドで共有することで、ペーパーレス化と素早い情報共有を実現している事例が見られました。教職員同士のやりとりのオンライン化によって、対面での職員朝礼・終礼を廃止した例も。
ほかにも、特別教室や備品の予約管理のオンライン化、欠席連絡など保護者との連絡ツールをデジタル化することで、効率化に成功している事例もありました。
さらに、小テストや授業プリントのデジタル化と自動採点、端末の持ち帰りによって家庭学習をデジタル化するなど、指導にICTを導入することで大幅な時間削減を実現している事例も多く見られました。
例えば家庭学習をオンライン提出にすることで年間33時間以上の削減、授業プリントを紙ではなくデータでの配布にすることで年間43時間、採点システムの導入で年間25時間削減できると示されています。これは担任1人あたりの削減時間なので、学年、学校全体で見ると大きな時間短縮を実現できることになります。

また、ICTを活用することで、転記の繰り返しによる作業ミス防止や、ペーパーレス化による印刷・配布の手間の削減などのメリットも生まれています。
5.教員の意識改革の事例
こうした外部人材の活用やICTの活用など、従来のやり方を大きく変革していくにあたってボトルネックになるのが「どうせ変わらない」「教員がやるのが当たり前」といった意識です。
働き方改革で成果を出している学校では、教育委員会や管理職の危機意識と、現場の当事者意識が高いという特長が見られました。こうした意識を高める取り組みとして、勤怠管理の徹底、管理職に向けた働き方改革研修の実施、ストレスチェックの実施などが行われています。
文部科学省も、教員の在校時間を自治体ごとに公表する、働き方改革に関する観点を校長の人事評価に加えるなどの方針を打ち出し、意識改革を後押ししています。
危機意識と当事者意識が高まることで、部活動の地域移行や、中間テスト・運動会・学芸会などの行事の見直し、短縮授業の実施や清掃時間短縮など日課表の見直し、家庭訪問の廃止、PTA活動の見直しなど、業務そのものの大幅な見直しも大胆に推進しやすくなります。
6.教員の作業の効率化をサポートする「navima(ナビマ)」
教員の作業負荷軽減に役立つのがデジタル学習サービス「navima(ナビマ)」です。一人ひとりに最適な問題を自動出題・自動採点し、間違いに応じて類題や学年をさかのぼって基礎的な問題を出題することができるので、家庭学習や授業中のスキマ時間に取り組む自主学習として最適です。採点を待って児童生徒が行列をつくる必要もありません。また、先生用管理ツールで個人単位での正答率や学習時間を把握することができるため、成績管理も負担なくスムーズに行えます。
プリント問題の印刷や配布、回収、丸付けなどの作業時間を徹底的に効率化。「navima」の詳しい内容はぜひお問い合わせください。
2025.01.31