統合報告書とは?
開示義務や求められる背景について解説
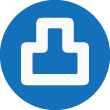
- TOPPAN CREATIVE編集部
統合報告書は、企業の財務情報と非財務情報をまとめ、将来的な価値創造のストーリーを伝える重要な資料です。近年は、投資方針や企業経営への期待の変化、さらには社会的課題の深刻化を受け、統合報告書の作成に取り組む企業が増えています。
この記事では、統合報告書を担当する方が、上司・関係部署への説明方法や具体的な作成手順を把握できるよう、基礎知識から報告書の意義、掲載内容などをわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
・統合報告書とは何か
・統合報告書に盛り込むべき具体的な内容
・統合報告書の作成ステップと作成のポイント
統合報告書とは
統合報告書とは、企業の財務状況と財務以外の活動内容を一つにまとめたレポートです。
投資家やステークホルダーに向けて、組織の中長期的な価値創造のストーリーを伝える目的があります。
売上や利益、資産といった基本的な財務情報と、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組み、顧客満足度、福利厚生、知的財産といった非財務情報などを「統合的」に開示することで、企業の持続可能性と全体像を分かりやすく伝えることが可能です。
企業が発行するレポートには、統合報告書の他にも「アニュアルレポート」「サステナビリティレポート」「有価証券報告書」などがあり、それぞれ以下のような違いがあります。
| 統合報告書 | アニュアルレポート | サステナビリティレポート | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|---|
| 概要 |
企業の中長期的な価値創造を伝える報告書 |
過去1年の業績や財務状況をまとめた報告書 | ESG・社会的責任に関する取り組みを伝える報告書 | 財務・法的情報をまとめた報告書 |
| 内容 | 財務情報+非財務情報 | 財務情報が中心 | 非財務情報 | 財務情報 |
| 読者 |
投資家 |
株主 |
投資家 |
投資家 |
| 開示義務 |
なし |
なし |
なし |
あり |
統合報告書とその他の報告書との違いについて解説します。
アニュアルレポートとの違い
アニュアルレポートは、企業が年に一度発行する年次報告書であり、主に過去1年間の財務成績や事業活動の結果をまとめた資料です。
一方、統合報告書は過去の実績に加えて、企業の中長期的なビジョンや価値創造のプロセスを非財務情報とともに伝えるもので、より未来志向の内容となっています。
つまり、アニュアルレポートが「過去」の報告書であるのに対し、統合報告書は「未来」に向けた企業戦略を伝える資料といえるでしょう。
サステナビリティレポートとの違い
サステナビリティレポートは、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)に関する取り組みや、社会的責任(CSR)をどのように果たしているかをまとめた報告書です。このレポートでは、環境保護への貢献、労働環境の整備、ガバナンス体制などの非財務情報が中心に扱われます。
統合報告書が財務情報と非財務情報を統合して企業価値全体を説明するのに対し、サステナビリティレポートは非財務情報に特化した内容です。
また、統合報告書は主に投資家に向けて企業の価値を伝えることを目的としていますが、サステナビリティレポートは幅広いステークホルダーとの対話や、ESG評価機関への情報開示を目的として作成されるのが一般的です。
サステナビリティレポートは、企業の環境・社会への貢献を強くアピールしたい場合に適したレポートといえるでしょう。
有価証券報告書との違い
有価証券報告書は、企業が投資家や金融当局に向けて、正確かつ詳細な財務・法的情報を提供するための法定開示書類です。金融商品取引法に基づき、上場企業は事業年度ごとの開示が義務付けられており、記載する項目や書式も厳格に定められています。
一方で、統合報告書の発行は任意であり、比較的自由な形式で発行可能です。
また、有価証券報告書の内容は財務情報が中心ですが、統合報告書は企業文化や人材戦略、社会貢献などの非財務情報を統合的に伝えられる点が大きな違いです。
統合報告書は開示義務がある?
統合報告書は、2025年8月時点で法的な開示義務はありません。そのため、東京証券取引所に上場している企業であっても、統合報告書を作成している企業とそうでない企業が混在しています。
しかし、法的な強制力がないにもかかわらず、企業の中長期的な価値創造や非財務情報への関心の高まりから、統合報告書を発行する企業は急増しています。
企業価値レポーティング・ラボ(Cvrl)の調査によると、2024年には1,177の組織(うち上場企業は1,090社)が統合報告書を発行しました。なお、2014年は135組織にとどまっており、約10年間で統合報告書を作成する企業が9倍近く増加していることになります。
さらに、2023年度からは有価証券報告書に非財務情報の記載欄が新設されるなど、日本でも非財務情報の開示を求める動きが加速しています。将来的には統合報告書の必要性がさらに高まると予測されるため、早い段階から準備を進めておくことが重要です。
統合報告書の作成が求められている背景
なぜ今、多くの企業が統合報告書の作成に取り組んでいるのでしょうか。その背景には、投資のあり方や企業経営に求められるものの変化と、深刻な社会課題の存在があります。それぞれの要因を詳しく解説します。
ESG投資やESG経営の普及
統合報告書の作成が求められる大きな背景として、ESG投資やESG経営の急速な普及が挙げられます。
2008年のリーマン・ショック以降、「従来の財務情報だけでは企業の本質的なリスクや健全性を見極められない」という認識が広まり、非財務情報の重要性が世界的に注目されるようになりました。実際に、ESG投資市場は年々拡大を続けており、多くの投資家が投資判断の際にESGの視点を積極的に取り入れています。
統合報告書は、こうしたESGへの対応状況を投資家に示す手段として有効であり、企業価値を訴求する上でも不可欠なツールとして活用されています。
人材不足の深刻化
少子高齢化の進行による人材不足も、統合報告書の重要性を高める一因となっています。人的資源が不足している企業では、持続的な成長が見込めないためです。
近年では、人材を単なるコストではなく、企業の中長期的成長を支える「重要な資本」としてとらえ、採用・育成・定着といった取り組みを戦略的に活用していく「人的資本経営」の考え方が注目されています。
投資家もまた、人的資本に関する情報を重要な投資判断材料として見ており、自社の人材戦略や具体的な取り組みを伝えるための資料として、統合報告書の作成・活用が求められるようになっています。
統合報告書の内容例
統合報告書には、厳密に定められた書式は存在しません。そのため、企業のビジネスモデルや理念、ステークホルダーのニーズを考慮しながら、独自の統合報告書を作成できます。
ただし、「統合報告書」としての客観的評価や一定の体裁を求める場合は、国際的なガイドラインに沿った作成が望ましいでしょう。特に、国際統合報告評議会(IIRC)が策定した「国際統合報告フレームワーク」は、広く活用されており、多くの企業がこれに準拠しています。
IIRCのフレームワークでは、統合報告書に含めるべき内容要素として、以下の8つを挙げています。
●組織概要と外部環境:企業の基本情報や取り巻く市場・社会環境の説明
●ガバナンス: 意思決定プロセスや監督体制に関する情報
●ビジネスモデル:どのように価値を創出しているかの全体像
●リスクと機会:組織が直面する課題や成長機会の特定
●戦略と資源配分: 企業の戦略目標、資源配分計画について
●実績: 財務・非財務両面での成果や進捗
●見通し: 今後の展望や取り組みの方向性
●作成と表示の基礎: 報告書作成における前提や基準
これらの項目をバランスよく網羅し、企業の持続可能性と価値創造のプロセスを一貫して示すことで、投資家をはじめとするステークホルダーに対する信頼性の高い報告が可能です。
統合報告書の作成ステップ
統合報告書の作成には、計画的かつ部門横断的なアプローチが求められます。単なる情報開示にとどまらず、企業の価値創造プロセスを社内外に正確に伝えるためのプロジェクトとして取り組むことが重要です。
統合報告書を作成する際の基本の手順は次の通りです。
1.プロジェクトチームの発足
2.構成の検討
3.データの収集・管理
4.データの編集・原稿作成
5.校正・承認
6.公開
それぞれのステップで押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
1.プロジェクトチームの発足
統合報告書を作成する際は、社内の様々な部門から情報を集約し、戦略的なストーリーをまとめる必要があります。
経営企画部やIR担当の部署が中心的な役割を担うケースが多いですが、関連する各部署からメンバーを集め、部門横断的なプロジェクトチーム(運営委員会)を設置して取り組むことがおすすめです。
専門的な知見が必要な場合は、外部の制作会社やコンサルティング会社との連携も検討しましょう。
2.構成の検討
次に、報告書全体で何を伝えるべきかを明確にします。
どのようなストーリーにするのか、他社の事例も参考にしながら構成を練ることが重要です。
基本的な流れに沿って作成したい場合は、IIRCのフレームワークを参考にすると良いでしょう。
3. データの収集・管理
構成案が決まったら、必要な情報やデータを収集・整理します。財務データはもちろん、ESG(環境・社会・ガバナンス)関連の指標も重要な要素です。
これらの情報は、各部署から集約して整理し、システマティックな方法で管理することが求められます。情報の信頼性と一貫性を保つためにも、収集プロセスを標準化し、データの出所や算出根拠を明確にしましょう。
4. データの編集・原稿作成
収集したデータをもとに、報告書の原稿を作成します。この段階では、情報の正確性と一貫性を保ちながら、読者にとってわかりやすく魅力的に伝えることが重要です。
言葉遣い表現のトーン、スタイルは全体を通して統一するほか、専門用語の多用を避け、簡潔で明瞭な表現を心がけましょう。原稿ができたら、関連部門による事実確認や、外部レビュアーによる校正を実施すると、内容の正確性や論理性を担保しやすくなります。
5. 校正・承認
原稿が完成したら、最終的な校正と社内承認のプロセスに入ります。厳密な校正を経て、品質の最終確認を行いましょう。
誤字脱字や文法のチェックはもちろん、データの正確性、全体の一貫性と流れを細かく確認する必要があります。最終的には経営陣や関連部門からのフィードバックを受け、企業のビジョンや中長期戦略と齟齬がないかチェックしましょう。
6. 公開
公開の準備ができたら、報告書を適切なプラットフォームを通じて公開します。
企業のWebサイト上でデジタル版を公開する方法や、株主総会などのタイミングに合わせて印刷版を制作・配布する方法が一般的です。
統合報告書の作成事例
TOPPANでは、多くの企業の統合報告書作成をサポートしています。ここでは、実際に公開されている統合報告書の作成例をご紹介します。
コマツ

コマツ(株式会社小松製作所)は、建設・鉱山機械などの事業を展開する企業です。2024年度の統合報告書では、会社の歴史や社長メッセージ、事業概要から中期経営計画、サステナビリティ・マネジメント、役員対談など網羅的な内容となっています。
大同特殊鋼株式会社

大同特殊鋼株式会社は、輸送機や発電所、産業機械、パソコンなど幅広い分野へ特殊鋼(特定の性質を強化した合金鋼)を提供している企業グループです。2024年度の統合報告書は、冒頭のカバーストーリーに地球環境保護への取り組みを大きく取り上げ、環境にやさしい企業であることが伝わりやすい構成になっています。
住友ベークライト株式会社
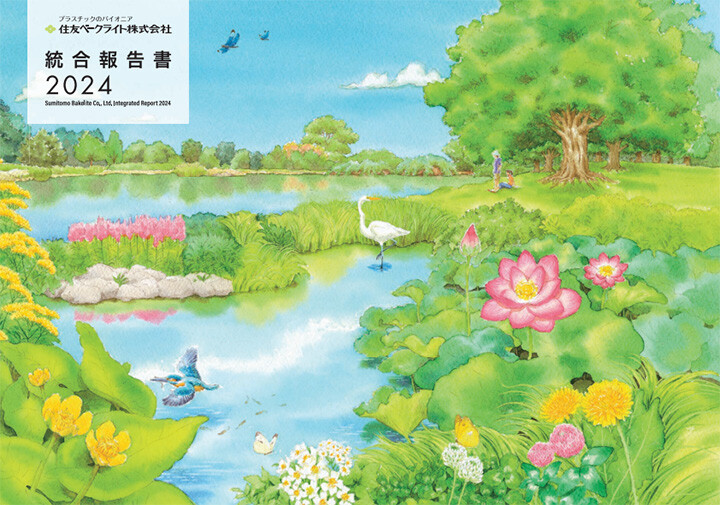
住友ベークライト株式会社は、日本で初めてプラスチック(ベークライト)の工業化に成功した企業として知られる化学メーカーです。2024年度の統合報告書は、新たに策定された経営課題を解決するためのストーリーやアクションが詳細に記載されています。
企業の価値を伝える統合報告書を作成するポイント
統合報告書を通じて企業の本質的な価値を正確に伝えるためには、単に情報を羅列するのではなく、戦略性や整合性を持った表現が求められます。
IIRC(国際統合報告評議会)は、質の高い統合報告書の条件として、以下の7つを挙げています。
●戦略的焦点と将来志向: 短・中・長期の戦略や成長ストーリーが語られている
●情報の結合性: 企業の価値創造に影響を与える様々な要因の相互関係・全体像が示されている
●ステークホルダーとの関係性: 顧客、従業員、投資家などの主要なステークホルダーのニーズをどの程度理解し、対応しているかが明示されている
●重要性(マテリアリティ): 企業の価値創造に影響を与える重要な課題が明示されている
●簡潔性: 情報がわかりやすく整理されている
●信頼性と完全性: 正確な情報が網羅的に含まれている
●首尾一貫性と比較可能性: 基準が一貫しており、過年度の報告書や他社の報告書との比較がしやすい
これらの視点を意識し作成することで、企業の将来性や価値創造のプロセスを効果的に伝えやすくなるでしょう。
TOPPANは統合報告書の相談から納品までサポートします
企業の中長期的な価値創造について包括的に開示できる「統合報告書」は、今後ますます必要性が高まると考えられます。しかし、財務・非財務両面にわたる情報収集と整理、さらに明確な形式が存在しないという特性から、作成に高いハードルを感じている企業も少なくありません。
社内での知見やリソースに不安がある場合には、まずはページ数を抑えた簡易的なレポートから始めてみるのも一つの方法です。
TOPPAN CREATIVEでは、統合報告書の作成を支援する「はじめての統合レポート」サービスを提供しております。あらかじめ用意された台割(設計書)とデザインテンプレートの活用、各部署から収集したデータや原稿をまとめるだけで、効率的に統合報告書の作成が可能です。統合報告書の作成をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
2025.09.17