マーケティングオートメーション(MA)導入ガイド|流れや注意点を解説
マーケティングオートメーション(MA)は、マーケティング活動を効率化し、成果を出すための有効なツールとして多くの企業で活用されています。今回はマーケティングオートメーションをこれから導入しようとされている方に向け、マーケティングオートメーションの概要や流れ、注意点をご紹介します。
<目次>
1.マーケティングオートメーション(MA)とは?
2.マーケティングオートメーション(MA)導入のメリット
3.マーケティングオートメーション(MA)導入のデメリット
4.マーケティングオートメーション(MA)を導入するタイミング
5.マーケティングオートメーション(MA)導入の流れ
6.マーケティングオートメーション(MA)導入でよくある失敗
7.マーケティングオートメーション(MA)導入の注意点
8.まとめ
1.マーケティングオートメーション(MA)とは?
マーケティングオートメーション(MA)とは、「マーケティング活動を支援する、可視化と自動化のためのツール」のことを指します。「Marketing Automation」の頭文字を取ってMAツールと呼ぶこともあります。個々の見込み顧客の興味・嗜好・関心に合わせ、適したタイミングで継続的にコミュニケーションを行うことで、顧客とのエンゲージメント強化を実現するプラットフォームです。

マーケティングオートメーションはすでに多くの企業で導入されており、購買意欲を高めるためのツールとして役立てられています。そして検討度合いの高い見込み顧客を選別した後、マーケティング部門から営業部門に引き渡します。
2.マーケティングオートメーション(MA)導入のメリット
続いて、マーケティングオートメーションを導入することで、どのようなメリットがあるかをご紹介します。
自動化による効率化
マーケティングオートメーションを利用することにより、営業とマーケティング関連業務が一部自動化され、効率化につながります。リードへの適切なタイミングでのメール配信などを自動化し、マーケティング業務の作業効率化を実現します。さらに、営業部門に対して質の高いホットなリードが引き渡されるため、商談につながりやすく、営業活動の効率化にも寄与します。

顧客に合わせたマーケティングが可能
マーケティングオートメーションは、単なるメール配信ツールではありません。リード一人ひとりの特性に応じて、興味・関心のある内容に即したコンテンツを提供することに長けています。また、適切なタイミングで情報提供する仕組みであるため、リードが知りたい情報を知りたいタイミングで提供することができます。
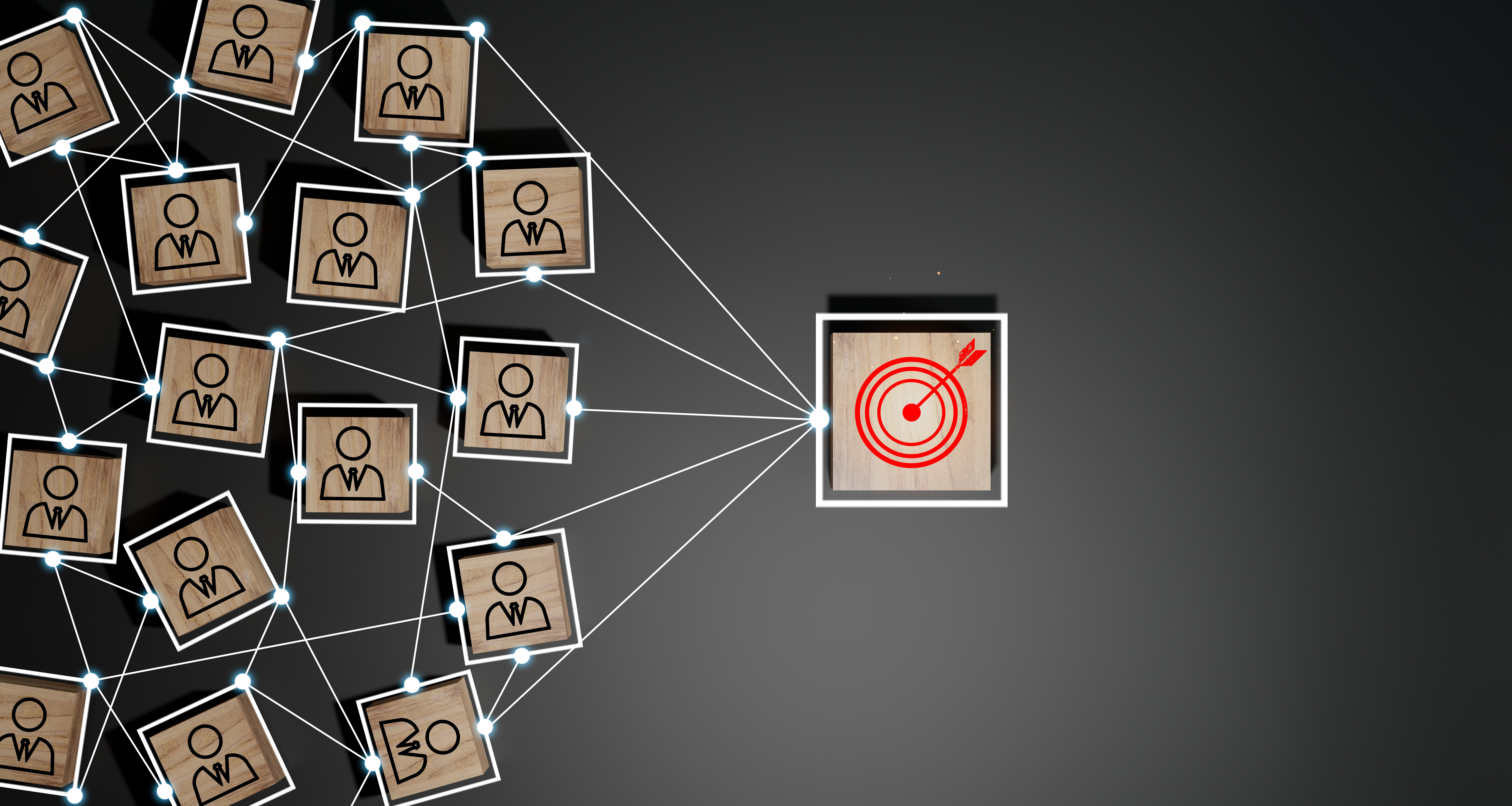
商談化の促進
マーケティングオートメーションを活用してリードの購買意欲を高めることで、商談化の促進につながります。ツールを通じてリードの検討段階を可視化することができるので、受注確度・検討度合いの高いリードを選別することが可能です。営業部門は商談に集中できるため、売上につながりやすくなります。

3.マーケティングオートメーション(MA)導入のデメリット
マーケティングオートメーションは強力なツールですが、導入にはメリットだけでなくデメリットも存在します。これらを事前に理解しておくことが重要です。
●継続的なコストの発生
マーケティングオートメーションの導入には初期費用だけでなく、月額のランニングコストが発生します。多くの場合、管理するリード数やメール配信数に応じた従量課金制が採用されています。
これらのコストは、会社の予算計画に継続的に組み込む必要があるため注意しましょう。
●運用リソースの確保と専門知識の必要性
マーケティングオートメーションは導入すれば自動で成果が出る魔法のシステムではありません。効果的な施策を企画・実行し、データを分析・改善できる専門知識を持った担当者が必要です。
例えば、顧客の行動を分析してシナリオを設計したり、スコアリングのロジックを最適化したりするには、デジタルマーケティングの知見が求められます。新たな担当者の配置や育成、または外部のソリューション活用も視野に入れる必要があります。
●成果が出るまでに時間がかかる
導入後すぐに売上が劇的に向上するわけではありません。
顧客データの蓄積、コンテンツ(資料のダウンロード促進、セミナー案内など)の準備、シナリオのテストと改善といったプロセスを経るため、成果を実感するまでには中長期的な視座が求められます。
4.マーケティングオートメーション(MA)を導入するタイミング
自社のビジネスにおいて、マーケティングオートメーションの導入が最適なタイミングはいつでしょうか。いくつかの代表的な兆候をご紹介します。
保有リード数が一定数を超えた時
保有するリード数が数千件の規模になってくると、Excelなどでの手動での管理や顧客情報の管理が限界を迎えます。また、メルマガの一斉配信といった画一的なアプローチや施策では非効率です。個々のリードの興味・関心に合わせた施策を実行し、効率的に営業へ引き渡すためにはマーケティングオートメーションのシステムが不可欠です。
この規模のリード数があれば、スコアリング機能も効果的に活用でき、スコアリング結果を営業部門と共有できます。
継続的にリード獲得ができるWebサイトがある時
マーケティングオートメーションは、顧客のデジタル上の行動を可視化し、ナーチャリング(育成)を行うツールです。そのため、オウンドメディアやサービスサイトなど、顧客が訪問し、資料のダウンロードや閲覧、セミナーに申し込んだりする「受け皿」となるWebサイトが機能していることが前提となります。
このWebサイトを通じて顧客の行動データを蓄積できなければ、マーケティングオートメーションを導入しても最大限活用することは難しいでしょう。
マーケティング担当チームのリソースが確保できる時
マーケティングオートメーションは導入すれば終わりではなく、継続的な運用が成果の鍵を握ります。シナリオ設計、コンテンツ制作、データ分析と改善といったデジタルマーケティング活動を担う担当者(またはチーム)のリソース確保が必要です。
SFAとの連携設定や運用プロセスの構築、さらにプロセス全体の最適化など、マーケティングオートメーションをソリューションとして使いこなすための体制と理解が求められます。単なるツール導入ではなく、会社全体のビジネス戦略としてマーケティングオートメーションを位置づけ、ビジネスの成長に繋げることが重要です。
5.マーケティングオートメーション(MA)導入の流れ
マーケティングオートメーションを導入する際の基本的な流れを紹介します。合わせて、導入する目的や検討のタイミングについても触れます。
1.課題の洗い出しと目的設定
まずマーケティングオートメーションを導入する目的を設定します。目的は企業によって異なり、複数ある場合もありますが、目的を設定せずに導入してしまうと、手段が目的化し、失敗してしまいます。まずは現状把握を行い、営業・マーケティング部門それぞれにおいて課題を洗い出しましょう。
その際、まずは大きく、以下の2項目で課題を整理しましょう。
・ 自社にとっての営業とマーケティング活動の「ボトルネック」は何か?
・ 日々の営業とマーケティング活動で、特に「負荷の高い業務」は何か?
この中で例えば、「リードを営業に引き渡してもなかなか受注に至らない」といった課題が挙がれば、「受注につながるリードを創出すること」が目的になると同時に、マーケティングオートメーション導入の検討タイミングといえるでしょう。
2.顧客データの整理・棚卸し
マーケティングオートメーションの導入目的が明確になったら、すでに社内に存在する既存顧客のデータや、見込み顧客のデータなど、顧客データの把握と整理を行います。この顧客データの整理がしっかりとなされていなければ、せっかくのデータもツールで活用することができません。ぜひ社内のあらゆる場所から集めましょう。
3.マーケティングオートメーションの比較・選定
マーケティングオートメーションを比較し、選定していきましょう。機能を選定する際は、「便利そうだから」「いつか使うだろう」といった漠然とした理由を避け、1.で設定した目的に応じて、「必要な機能が備わっているか」という視点で機能を見るようにしましょう。
候補ツールが出揃ったところで、操作性やサポート対応、価格など複数項目で比較していきます。サポート対応についてはただ導入をサポートしてくれるだけではなく、マーケティングの戦略設計段階から支援してくれるサービスもあるため、広い視野で検討することをおすすめします。
4.マーケティングオートメーションの各種設定・開発
マーケティングオートメーションの各種設定や開発を行います。マーケティングオートメーションは導入しただけではすぐ使うことができません。顧客リストの登録はもちろんのこと、顧客が商品を購入するまでのカスタマージャーニーマップ、リードの興味・関心のレベルに合ったメール配信を行うステップメールなどの設計および設定が必要です。
5.各種準備
その他、マーケティングオートメーションを活用するに当たって、準備すべき事項に対応していきましょう。例えば、リードの興味・関心の内容に合わせて提供するクリエイティブコンテンツの整備、運用フローの整備、マーケティング部門と営業部門などの部門・部署間の連携などが求められます。
6.効果検証の準備
マーケティングオートメーションの目的が達成できているかの効果検証をどのように行うのかを事前に決めておくことも大切です。
6.マーケティングオートメーション(MA)導入でよくある失敗
マーケティングオートメーションは、導入すれば必ず成果が出るというものではありません。失敗することも出てきます。そこであらかじめ、よくある導入の失敗ケースを知っておきましょう。

スキルやリソースが不足していて使いこなせない
前述の通り、マーケティングオートメーションは導入すればすぐに使えるものではなく、戦略設計からコンテンツの準備など様々な設定・設計が必要です。成果が出るかを決めるのは、この部分がしっかりしているかどうかといっても過言ではありません。また、操作性の部分で、ツール自体のUIが複雑、機能が多すぎて分からない、といった理由から使いこなせないというケースもあります。
目的の設定が不明確で成果が出ていない
マーケティングオートメーションを導入する際に、「他社が導入しているから」「導入すれば成果が出せる気がする」などの自社の課題に直接紐づいていない理由で導入してしまうと、成果が出ないという失敗に終わってしまいます。
部門間連携がうまくいかない
特にマーケティング部門と営業部門の連携がうまくいかないケースが多いといわれます。例えば、マーケティング部門がどれだけリードを育成しても、営業部門にとって成約につながりにくい特性があるリードであれば、売上につながらず、成果が出せません。
7.マーケティングオートメーション(MA)導入の注意点
マーケティングオートメーションを導入する際には、注意点があります。しっかり押さえることで、成功につながるでしょう。
課題を明確にして目的を設定する
目的を設定するには、まず自社の課題を洗い出し、明確にすることが重要です。課題は、マーケティング部門のみならず、営業部門など他部門や部署にもヒアリングしてできるだけ多く抽出しましょう。コスト削減や人材不足の解消、Webにおける幅広い層のリードの獲得、成約率の向上など課題に応じた目的設定を行うことで、狙った成果を出すことができます。
自社が使いこなせる機能の入念な確認
使いこなせる機能を事前に確認することで、操作性が低いことによる失敗は、未然に避けられます。マーケティングオートメーションの選定時に、まずはトライアルとして実際に触ってみることです。使い勝手をよく考えた上で行いましょう。
戦略設計・コンテンツ制作支援サービスの活用
戦略設計やコンテンツ制作についてスキルやリソースが不足している場合は、支援サービスを利用する方法もあります。シナリオメールの設計・配信や、実際に送るHTMLメールやテキストメールの作成もサポート範囲に含まれていることもあります。
部門間連携への注力
部門間で理想的なリードにズレを感じる場合は、共通したペルソナやカスタマージャーニーを確実に共有し直すことが重要です。また、営業部門からのフィードバックを通じて、マーケティング部門が引き渡すリードを変更するといったすり合わせや柔軟な対応が重要です。
8.まとめ
マーケティングオートメーションをこれから導入したいとお考えの方に、主に導入手順や失敗しないためのポイントをご紹介しました。導入に際してお困りの方は、TOPPANのマーケティングオートメーション(MA)伴走支援サービスにご相談ください。
300社以上へのCRMの導入・運用実績から蓄積されたナレッジと、製造業として培ってきた品質管理手法をもとに、導入前の戦略設計段階からサポートしております。
また導入後の運用支援においては、マーケティングオートメーション運用に特化した専門チームが支援するほか、業務量・幅に応じた人員数の可変や、高度な運用に求められるコンテンツ制作・プランニング・分析・データ基盤構築などのスペシャリストのアサインも可能です。貴社の状況に合わせ、最適な体制をご提供することができます。まずはお気軽にご相談ください。
2025.11.17













