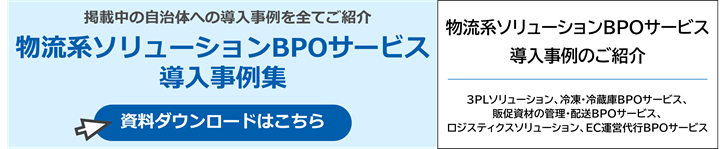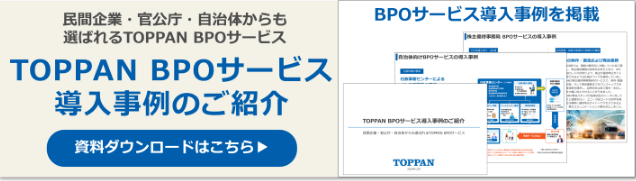物流業界における2030年問題とは?
企業が今から始めるべき対策
国内で急速に進んでいる少子高齢化による労働人口の減少を背景として、国内のあらゆる業界に影響が出る中で、物流業界においてはより一層、労働力不足が深刻化しています。物流業界はトラックドライバーの長時間労働規制を背景として生じている「2024年問題」に直面していますが、その先にある「2030年問題」にも焦点が当たっています。
今回は、物流業界における2030年問題の概要と共に、企業が今から始めるべき対策と3PL活用のメリットや方法について解説します。
■物流2030年問題とは?
物流2030年問題とはどのような問題なのでしょうか。またその原因となる背景についても見ていきましょう。
●物流業界における2030年問題とは
物流業界における2030年問題とは、日本国内で現状起きている少子高齢化に伴う労働人口減少の影響から、物流業界において生じる問題全般を指しています。主に物流企業における労働力不足やそれに伴う競争の激化、人件費の高騰などが挙げられます。
●物流業界の人手不足の現状と未来
2030年に焦点が当てられているのには理由があります。
国土交通省が中心となって行った「持続可能な物流の実現に向けた検討会」(2023年8月)では、2024年問題によってトラックドライバーの労働時間削減による具体的な対策を行わなければ、輸送能力が不足する可能性があるとしています。
紹介されていた試算によれば、トラックドライバーの年間の拘束時間の上限を原則3,300時間とすると、対策を行わなければ、2024年度は輸送能力が14.2%不足する見込みがあるといいます。そして2030年度には、不足する輸送能力の割合が34.1%にまで増えてしまう可能性があると予測されています。
もともとトラックドライバーについては、全産業と比較して平均年齢が3~6歳高いとされています。一方で、道路貨物運送業は65歳以上の就業者の割合が少ない業種であることから、担い手の減少が急速に進んでいく恐れがあります。
■2030年問題の先にある、2040年問題とは?
物流業界では、すでに「2024年問題」への対応が日常化しつつありますが、これは労働環境是正のための法的な「入り口」に過ぎません。私たちが真に注視すべきは、その先に控える構造的な危機、「2030年問題」および「2040年問題」です。2024年の制度改正だけでは解決しきれない、長期的な視点での課題について解説します。
●輸送能力不足が顕在化する「物理的危機」
2024年問題が「働ける時間の制約」であったのに対し、2030年問題は少子高齢化による「担い手そのものの不足」が顕在化するフェーズです。国の試算では、何も対策を行わなかった場合、2030年度には輸送能力が約34%不足すると予測されています。これは、荷物の3つに1つが運べなくなる計算であり、法規制への対応を超えた、物理的な供給不足の危機と言えます。
●高齢化のピークと労働力確保の限界
そして、さらに深刻なのが「2040年問題」です。2040年には日本の高齢者人口が約3,928万人でピークに達するとされ、現役世代(生産年齢人口)が急速に減少する「超高齢化社会の極地」が到来します。 この頃には、全産業で人手不足が極まり、物流ドライバーを含む若年層の労働力確保は、現在よりも遥かに困難になると予測されています。2025年現在はまだ序章に過ぎません。労働力が激減する2040年を見据え、省人化・自動化への抜本的な投資が急務となっています。
■物流2030年問題で懸念される具体的な影響
もし、2030年問題に対して有効な対策を講じず、現状のまま推移した場合、私たちのビジネスや生活にはどのような影響が出るのでしょうか。想定されるリスクは、単なる「配送の遅れ」にとどまらず、企業経営の根幹や、私たちの消費行動そのものに関わる問題へと発展する可能性があります。
●配送サービスの水準低下と送料無料の限界
最も懸念されるのは、これまで当たり前だった物流サービスレベルの維持が困難になることです。長距離輸送の網が維持できなくなり、翌日配送や時間指定配達といったきめ細やかなサービスの提供エリアが縮小する可能性があります。
また、需要に対してトラックの供給が追いつかない「需給逼迫」により、運賃相場が高騰することも避けられません。これにより、商品価格への転嫁や、EC通販などで一般的となっていた「送料無料」サービスの維持・継続が困難になるケースも想定されます。
●企業の売上機会の損失とサプライチェーンの分断
荷主企業にとっては、商品があっても運ぶ手段がないために販売機会を損失するリスクが現実味を帯びてきます。
必要な時に必要なモノが届かない状況は、製造ラインの停止や小売店の棚割れに直結し、企業の競争力を大きく削ぐことになりかねません。企業は「運賃の値上げ要請を受け入れる」といった受動的な対応だけでなく、サプライチェーン全体を見直し、無理のない配送スケジュールへの変更や在庫拠点の再配置といった能動的な対策が求められます。
■政府が実施している主要施策とは?
物流2030年問題に対して、日本政府はすでに様々な施策を実施しています。内閣官房が2024年2月に公表した、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議で策定された「2030年度に向けた政府の中長期計画」では、主に次の施策が挙げられています。
●適正運賃収受や物流生産性向上のための法改正等
荷待ち・荷役時間の短縮に向けた、計画を作成することを、荷主や物流事業者に義務付ける施策や、トラックドライバーの賃上げに向けた標準的運賃の引上げなどを挙げています。
●デジタル技術の活用による物流効率化
荷待ち・荷役時間の短縮のための自動化・機械化設備やシステム投資の支援、物流標準化や積載率向上のための共同輸配送、自動運転やドローン物流などのデジタル技術活用による無人化などが掲げられています。
●多様な輸送モードの活用推進
トラックに代わり鉄道や船舶による運搬を進めるモーダルシフトの推進、自動物流道路の構築、自動運搬船の商用運航などが計画されています。
●高速道路の利便性向上
大型トラックの法定速度を2024年4月に90km/hに引き上げる施策や、ダブル連結トラックの運航路線の拡充や駐車マス整備などを通じた導入促進などが施策されました。
●荷主・消費者の行動変容
再配達削減のための試みや「送料無料」表示の見直しを進める施策などが挙げられます。
■企業が今から始められる2030年問題への対応策とは?
国を挙げて物流業界の人手不足に対して対策が投じられる中、物流企業はどのようなことができるのでしょうか。主な対応策として考えられることをご紹介します。
●物流サプライチェーンの最適化
物流2024年問題が生じて以来、もはや問題は一企業で完結できるものではないことがわかっています。荷主も含めたサプライチェーン全体が一丸となって取り組まなければならないときにきています。2030年問題においても同様であり、物流サプライチェーンの最適化を目指す必要があります。
特に注目されているのは、デジタル化です。サプライチェーン全体を見通した上で、AIが最適な配送ルートを導き出したり、IoTによるリアルタイムの在庫管理、データの可視化によるサプライチェーン全体の最適化の視点を持ったりすることが求められています。
●共同配送
少ないトラックでより効率的に運ぶために、積載率向上の取り組みは欠かせません。共同配送は大きな対応策の一つとなります。共同配送を進めるにあたって、求められるのは、デジタル化です。各社が自社の物流状況をデータとして把握することで、共有が可能であり、積載率などの改善にもつながりやすくなります。
●AI・デジタル技術の導入による業務効率化
政府の「物流革新に向けた政策パッケージ」でも強調されている通り、トラックドライバーの長時間労働の要因となっている「荷待ち・荷役時間」の短縮は、企業が優先的に取り組むべき課題です。これを実現するためには、従来のアナログな運用から脱却し、自動化・機械化設備やシステム投資によるDXを推進する必要があります。
具体的には、バース予約システムによる待機時間の削減や、検品・仕分けロボットの導入による省人化などが挙げられます。
さらに近年では、AIが最適な配送ルートを算出したり、IoTで倉庫内の状況を可視化したりする技術も普及しています。これらのデータを活用し、将来的な物流リソースの共有(フィジカルインターネット)を見据えたデジタル基盤の構築こそが、2030年を乗り越える鍵となります。
●3PLの活用
物流工程全体を見通したときに、人手不足を補填するための有効策の一つに3PLの活用があります。3PLとは、「Third(3rd)Party Logistics(サード・パーティ・ロジスティクス)」で、自社や運送事業者以外の「サード・パーティ=第三者」に対し、物流業務を包括的にアウトソーシングする手法を指します。
荷主が在庫管理、輸送、配送、包装、注文処理などの物流工程を外部委託することで、物流効率化を図ることができます。
■3PLが物流効率化につながる理由
対応策の一つとして取り上げた3PLについて、もう少し詳しく確認していきましょう。
●3PLが物流効率化につながる理由
3PLを活用することで、なぜ物流効率化につながるのでしょうか。その理由は、アウトソーシングによる人手不足への対応策となるだけではなく、3PL事業者が第三者の視点で包括的に物流業務やコスト、管理面を見通し、問題改善を進められる可能性があるためです。
3PL事業者によっては、専門知識や技術を背景に、企業にとって最適な物流ソリューションを提案してくれるところもあり、それによって物流効率化を進めることができます。それにより、物流品質が向上すれば、少ないリソースでも顧客満足度向上につなげられ、競争力を強化できる見込みがあります。
また3PLはアウトソーシングの一種であるため、繁忙期・閑散期に応じて柔軟に体制を変更できます。コスト効率も高まるでしょう。
●3PLをワンストップで委託するのも一案
3PLはサービスによって対応範囲が異なりますが、ワンストップで委託することでより高い効果が期待できるでしょう。近年、EC需要も増えていることから、従来の物流業務に含まれない、お客さまからの問い合わせ対応といった周辺業務も生じています。そのような応対関連の業務も含めたワンストップソリューションを提供している3PLサービスを選ぶことで、より業務効率化が期待できると考えられます。
●最新システムの活用と物流DXの加速
2030年問題への対応として、AIによる配送管理やWMS、省人化ロボットなどのテクノロジー導入は不可欠です。しかし、これらを自社単独で整備するには、多額の初期投資と専門的な運用ノウハウが必要となり、大きな経営リスクを伴います。
3PLを活用するメリットは、事業者が保有する最新のデジタル基盤や高度な物流インフラを、自社で資産を持たずに利用できる点にあります。これにより、投資コストを抑えながらスピーディーに物流DXを実現できます。データに基づいた在庫の適正化や業務の可視化が進むことで、将来的な労働力不足にも耐えうる、持続可能な物流体制の構築につながります。
■まとめ
人手不足が深刻化する中で、物流2030年問題への対応策についてもさらに強化していく必要があります。様々な対応策がある中で、3PLの活用は、新たな可能性が見出せる方法といえるでしょう。
TOPPAN BPOでは、3PLワンストップソリューションをはじめ、物流に関連するBPOサービスをご提供しております。
3PLワンストップソリューションでは、長年の印刷業務で培った知見やノウハウを活かした業務効率化やコスト削減のご支援、受発注システムと事務局運営による3PLを実現し、物流最適化につなげます。
物流2030年問題の対応策としてもご活用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。
2026.01.23