外来業務の効率化と説明の標準化
─DICTORが支える下部消化管外科診療
北里大学病院での導入事例
「DICTOR(ディクター)」は、医療従事者本人の声をもとに説明動画を作成し、術前説明や入退院時の案内など、患者さんへの説明業務をサポートするサービスです。
動画を活用することで、業務効率化に寄与するとともに、患者さんやご家族が安心して医療を受けられる環境づくりを支援します。
本記事では、北里大学病院での導入事例をご紹介します。
導入施設紹介
北里大学病院は、学祖・北里柴三郎博士の精神を受け継ぎ、患者中心の医療とチーム医療を実践しています。
患者の人権を尊重し、安全で信頼される医療を提供するとともに、地域との連携や、未来を担う医療人の育成にも積極的に取り組んでいます。

ご協力いただいた先生
北里大学医学部 下部消化管外科学 主任教授 内藤 剛 先生
下部消化管外科を専門とし、大腸疾患、特に大腸がんの外科的診療を中心に担当している内藤先生。近年は、高度肥満症や2型糖尿病に対する外科的治療、いわゆる減量・代謝改善手術にも力を入れています。
丁寧な説明が生む負担と説明業務の課題
手術説明における課題を教えてください。
内藤先生:下部消化管外科では、手術のインフォームドコンセントを丁寧に行おうとすると、どうしても1時間ほどかかってしまいます。
病院としても「業務時間内に説明を完結させること」が求められ、さらに必ず第三者の同席が必要です。
つまり、1回の説明で複数の医療従事者が1時間拘束されることになり、膨大な業務の中で大きな負担となっていました。
限られた時間ですべてを網羅する必要があることも、日々の課題として感じていました。
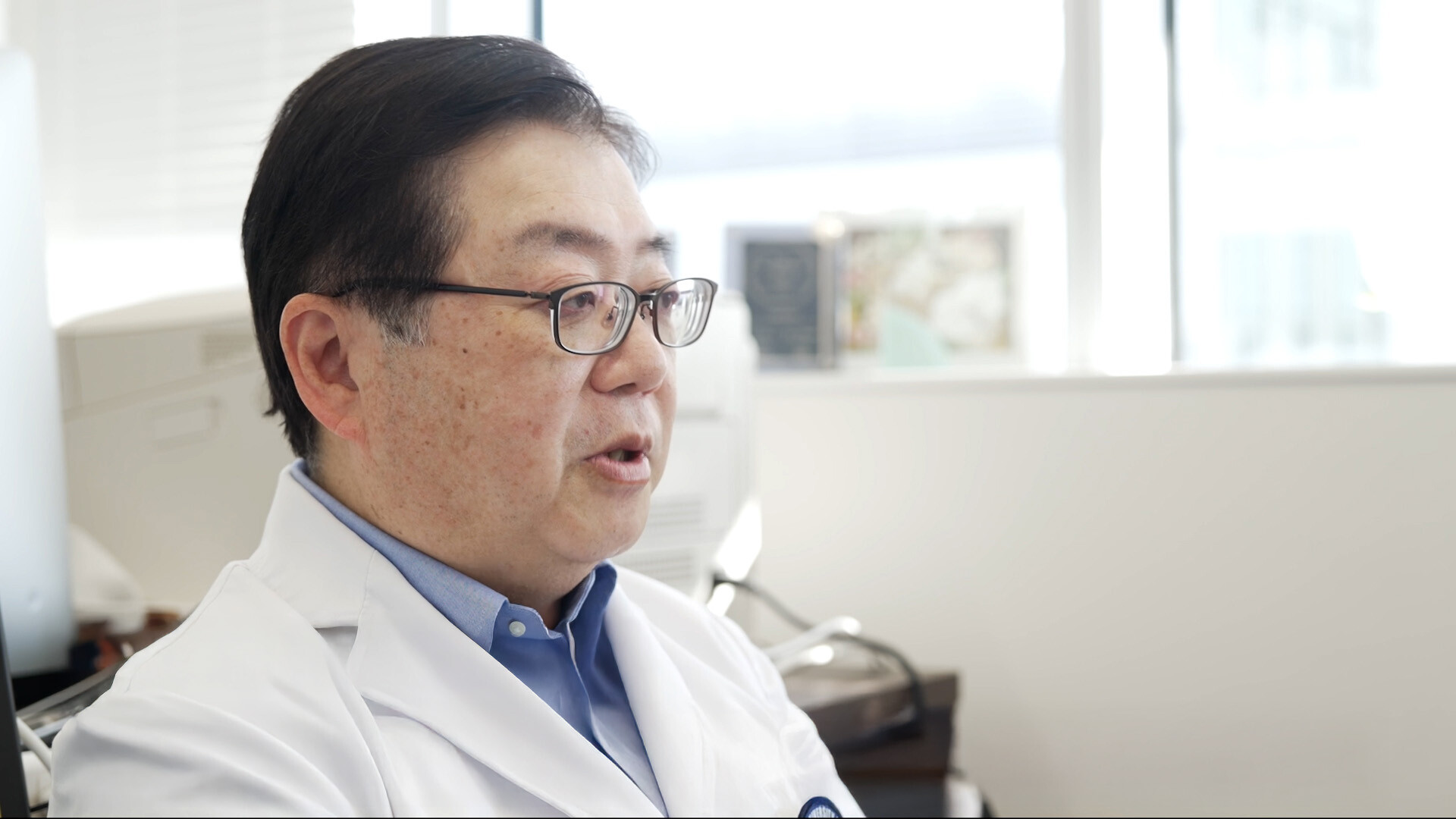
DICTOR導入のきっかけ
DICTORに興味を持った理由は何でしょうか。
内藤先生:我々にとっても限られた時間の中で十分な説明を担保できるのは大きな魅力でした。また、主治医の顔と声で説明できることが、患者さんにとって親近感につながると感じました。
実際の活用シーン
現在どのような場面で活用されていますか。
内藤先生:私が主にDICTORを活用しているのは、外来診療の初診時です。特に、減量・代謝改善手術を受けるために外科外来を訪れる患者さんに対して使用しています。
こうした患者さんは、市中病院の先生から「このような治療があるので、話を聞いてみてはどうか」と紹介されて来院されるケースが多いです。まだあまりポピュラーな手術ではないため、患者さん自身は情報をほとんど持っていないことも珍しくありません。
そのため、手術の概要だけではなく、肥満という疾患をなぜ治療する必要があるのかといった基本的なところから、すべて説明する必要があります。従来は、この初診時の口頭説明だけで30分ほどかかることもありました。

外来診療での活用と導入効果
実際の外来での導入効果を教えてください。
内藤先生:外来では、1人あたりの説明時間が約30分削減でき、その間に2人ほどの患者さんを診ることができます。新患が1日に3、4人来る日もあるため、業務効率化の効果は非常に大きく、外来業務は格段に楽になりました。
働き方改革の観点でも、効率よく仕事を進め、人的リソースを有効に使うことが重要です。DICTORでは、私たちがその場にいなくても、アバターが私たちの声で患者さんに説明できます。まさに、AIへのタスクシフトを実現していると言えるでしょう。
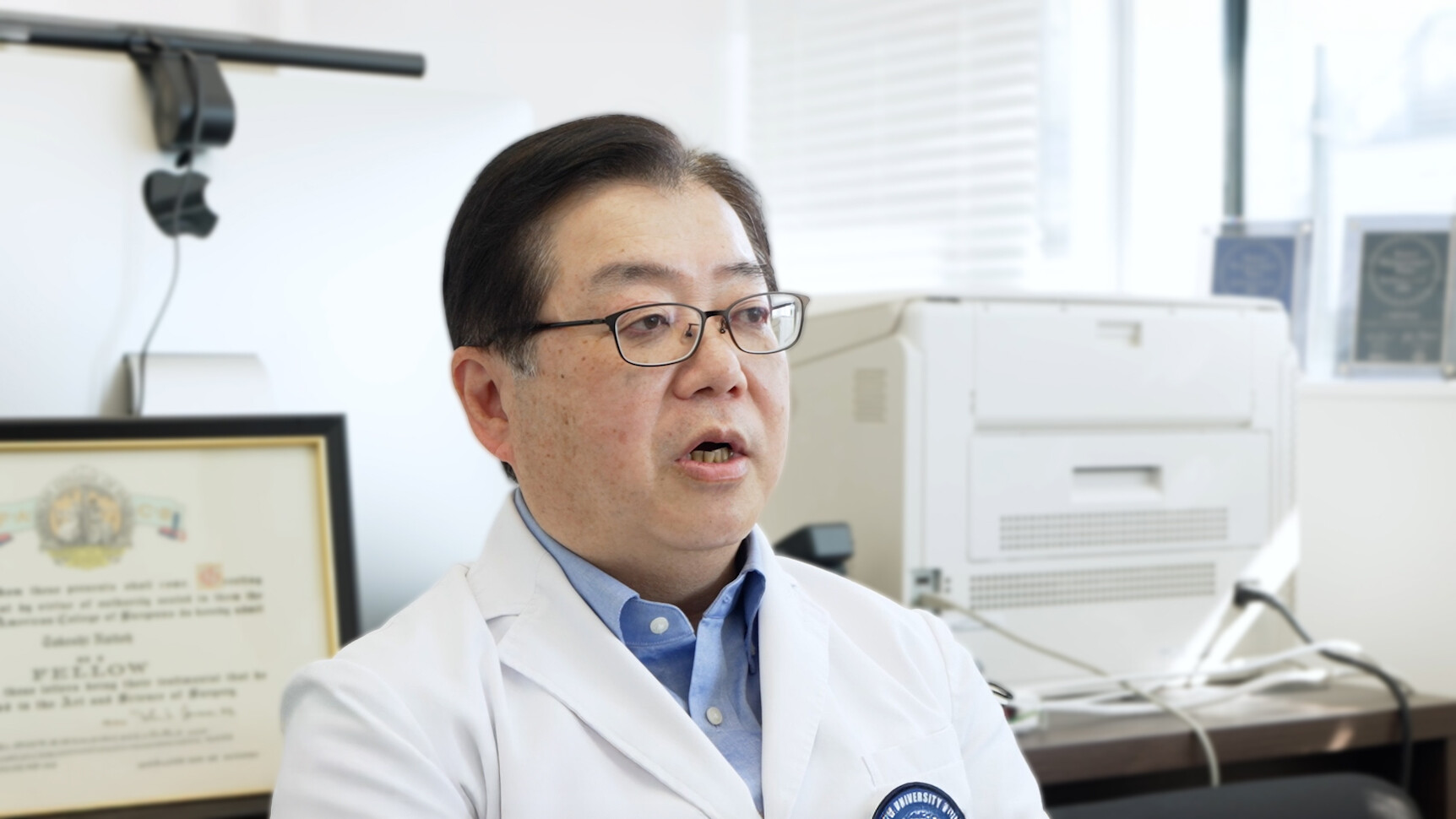
実証を経て
患者さんからのリアクションはいかがでしたか。
内藤先生:最初はアバターであることを伝えずにDICTORをご覧いただいていますが、後から「実はアバターなんですよ」とお話しすると、皆さんとても驚かれます。「違和感がないですね」「とても自然ですね」といった声が多く、クオリティの高さを実感しています。
また、対面でインフォームドコンセントを行った場合と比べても、理解度に差は感じません。そのため、DICTORだけでも十分に説明として成り立っていると考えています。
さらに、初診時だけでなく手術前にも同じ動画を使うことで、患者さんからは「これ、最初にも聞きました」といった反応が返ってくることがあります。そのおかげで、私たちも患者さんの理解度を把握しやすくなりました。
今後の活用について
DICTORの導入は、病院全体の働き方にも影響しますか。
内藤先生:医療現場では、説明と同意(インフォームドコンセント)があらゆる業務の前提となっており、これが業務時間を圧迫しています。
入院案内や生活指導のように、医師や看護師が必ずしも対面で行う必要のない説明もあります。
たとえば、入院時に「何を持ってくるか」「病棟にはどんな設備があるか」といった説明は、必ずしも看護師や医師が対面で行う必要はないでしょう。
こうした業務をDICTORに置き換えることができれば、説明の効率化や時間削減に大きく貢献できると感じています。
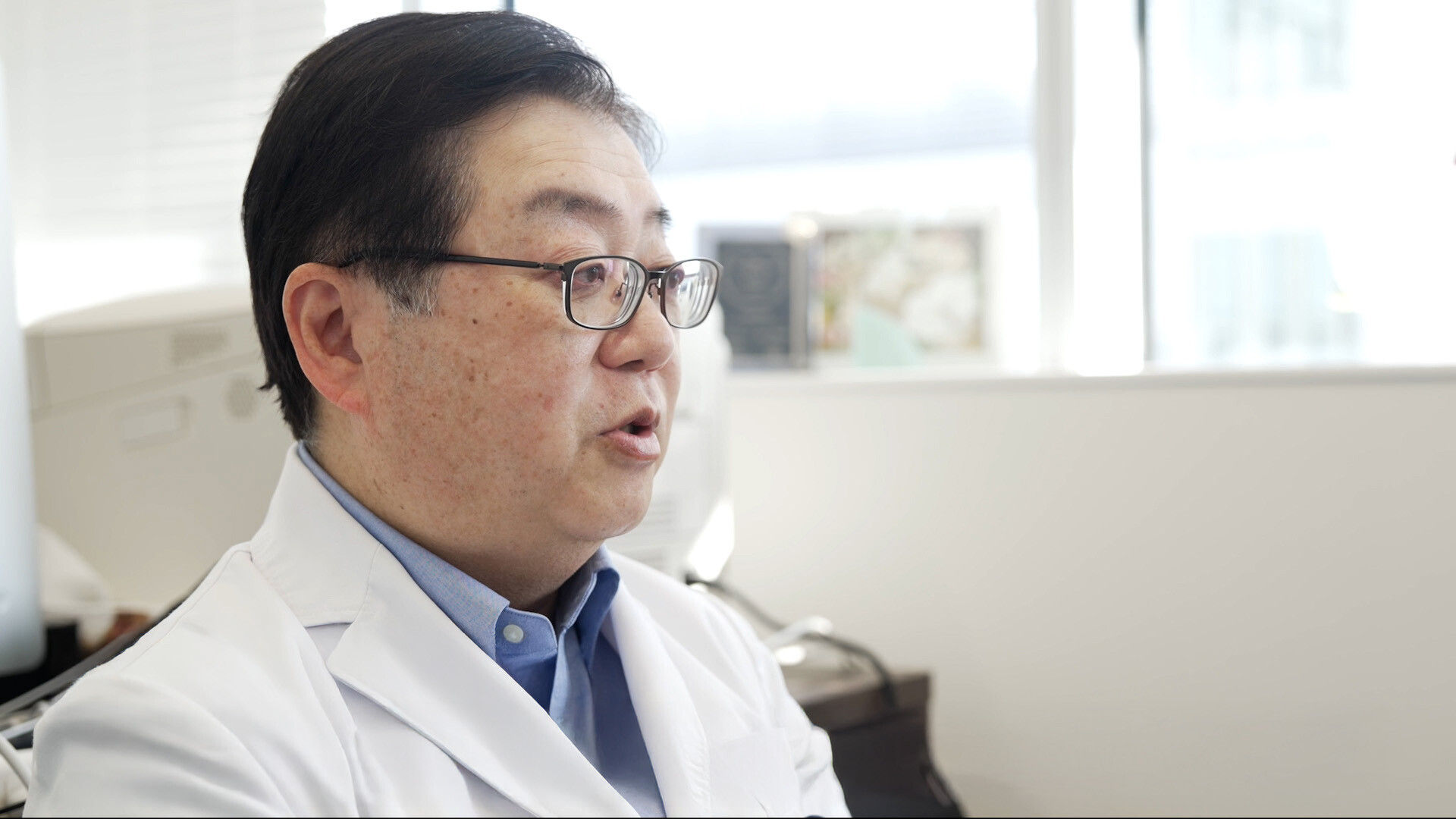
導入を検討している医療機関へ、DICTORならではの利点とは
従来の説明動画と比べて、どのような利点がありますか。
内藤先生:これまでも、様々な説明動画は存在しました。病院ごとに工夫してビデオを撮影する取り組みも多くありますが、DICTORの優れている点は大きく2つあります。
まず、担当の医師や看護師の顔と声で説明できること。患者さんにとって非常に安心感があります。
もう一つは、テキストベースで内容を作成しているため、更新が容易なことです。
従来のビデオでは内容を変更するたびに撮り直しが必要でしたが、DICTORなら一部を修正するだけで、その他の部分はそのまま活かせます。この柔軟さは、日常業務にとても適していると感じています。
● 患者説明業務支援サービス「DICTOR」●
DICTORは、患者さんへの説明業務を支援し、医療現場の業務効率化とコミュニケーションの質の向上を実現するサービスです。導入をご検討の際は、医療機関の規模やニーズに合わせたご提案・デモのご案内も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
本記事はインタビュー動画の内容を書き起こしたものです。動画は以下のリンクからご覧いただけます。
2025.09.25



