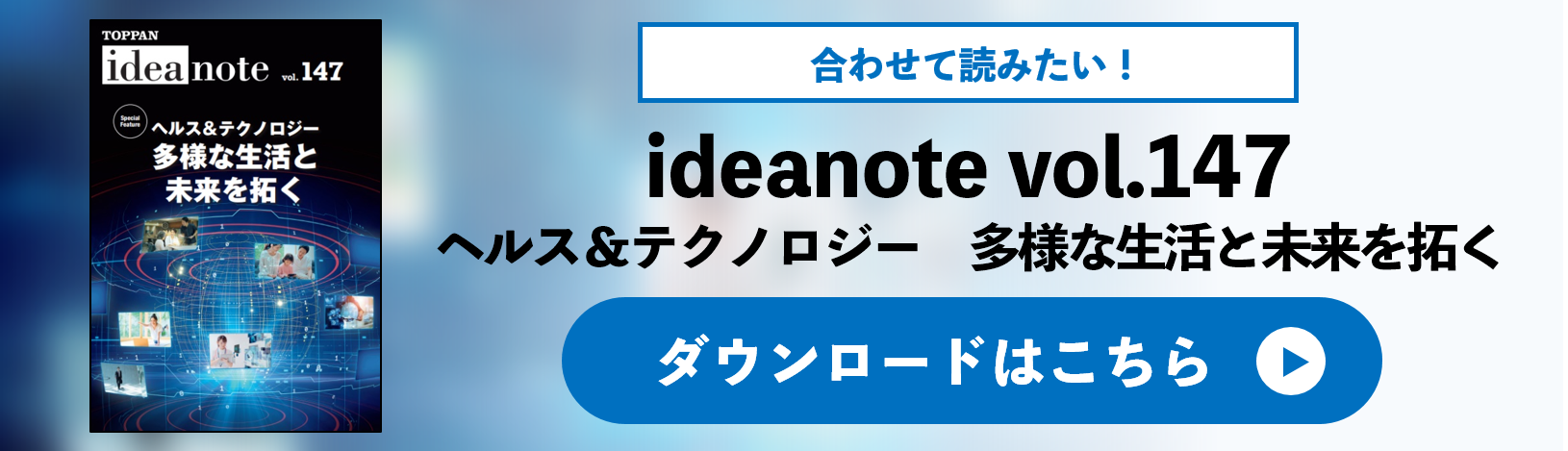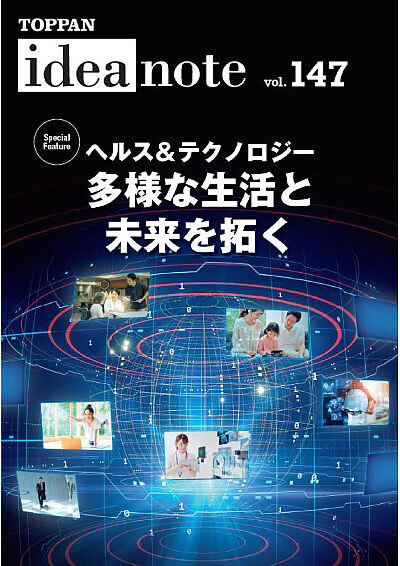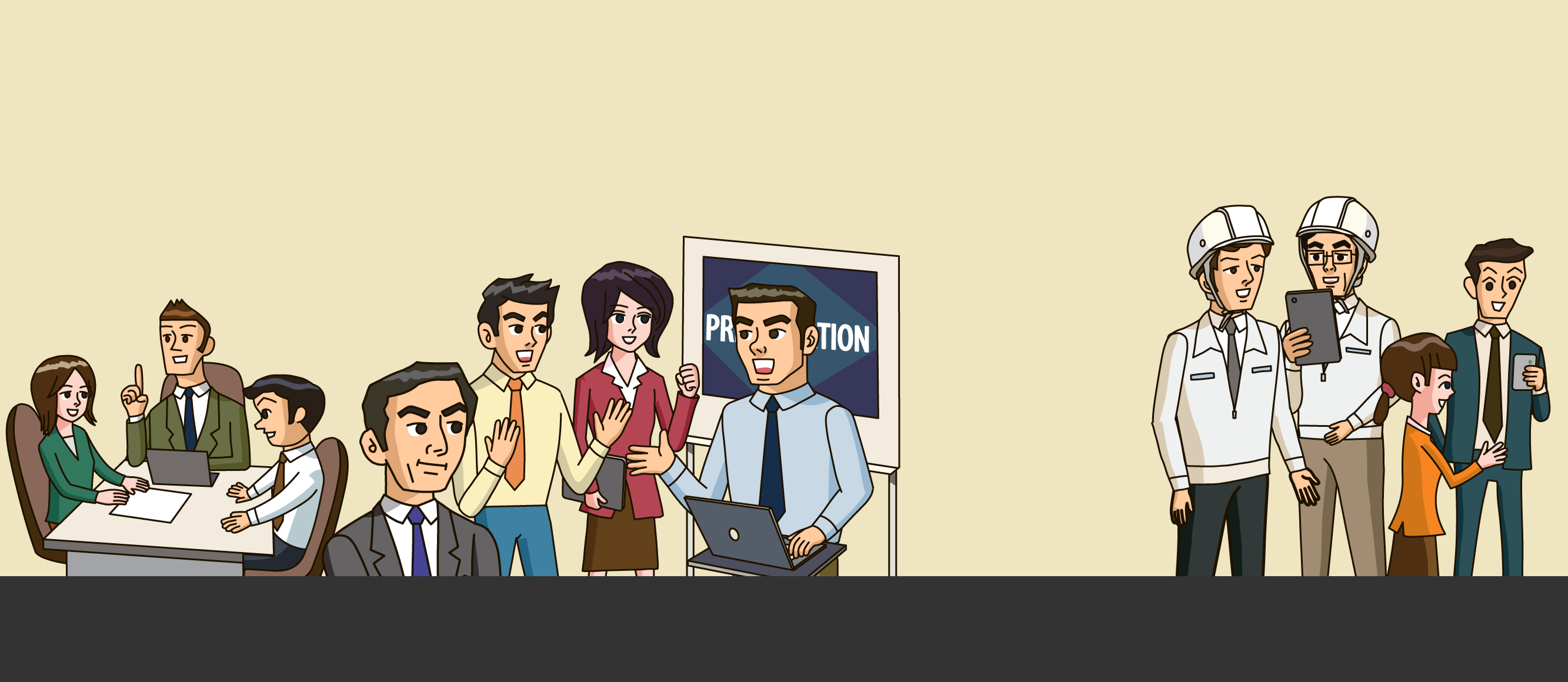ストレスチェックシステムとは?
注目される背景や導入のポイントを解説
ストレスチェックが2015年12月より義務づけられてから、年に一度各企業で実施されています。課題について、解決方法を探している方もいるでしょう。近年はストレスチェックシステムの導入が進んでおり、効率化に役立てられます。
今回は、ストレスチェックシステムの特徴や注目されている背景、導入メリット、選定・導入のポイント、システムの具体例をご紹介します。
ストレスチェックとは?実施割合もご紹介
ストレスチェックの概要と企業における実施割合を見ていきましょう。
ストレスチェックとは
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問に従業員が回答し、それを企業が集計・分析することで、各従業員のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査を指します。
ストレスチェックの実施は「労働安全衛生法」に定められており、2015年12月から労働者が常時50人以上いる事業所では、毎年1回すべての労働者に対して実施することが義務づけられています。
業者等の責務が記されている労働安全衛生法第三条において、事業者はこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけではなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場の労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない旨と、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない旨が明記されています。
企業がストレスチェックを適切に実施することは、従業員の安全と健康を確保し、労働災害を予防するために事業者が行うべき重要な責務の一つです。
ストレスチェックの実施割合
国内におけるストレスチェックの実施割合は年々増加傾向にあります。
厚生労働省が令和2年度に行ったアンケート調査結果(※1)では、全事業場のうち8割以上が取り組んでいます。事業場の規模別にみると、実施が努力義務となっている小規模事業場でも約4割が実施しています。全体の割合は年々増加しているものの、小規模事業場のうち他の場所に同一経営の本社や支社などを持たない単独事業場の実施割合は1割以下という現状があります。
厚生労働省の報告書(※2)によれば、2020 年度にストレスチェックを実施しなかった(できなかった)事業場の理由として、最も多い理由は「労働者数 50 人未満の事業場であり、実施義務がなかった」で約72%、次いで「ストレスチェック制度の義務化を知らなかった」で約24%でした。
実施義務がなければ実施しない割合が多いことから、現場ではまだ必要性をそれほど感じていないと考えられます。
※1 出典:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000917251.pdf
※2 出典:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/000951471.pdf
企業が実施する目的
企業がストレスチェックを行う目的として、労働安全衛生法にあるように、従業員の安全と健康を確保でき、労働災害が起きないように職場環境を改善していくことが挙げられます。また、従業員が感じるストレスの要因を知ることで、その要因を取り除くことができるようになり、職場環境をよりよくしていくことができます。
特に従業員一人ひとりについて、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止するためには、心理的な状況を知ることが必要です。そのため、ストレスチェックは重要な役割を担っています。
ストレスチェックシステムとは?
ストレスチェックを適切かつ効率的に継続して行い、結果を活かしていくためにストレスチェックシステムの活用が進んでいます。
ストレスチェックシステムとは
ストレスチェックシステムとは、ストレスチェックを効率的に実施するための機能が備わっているシステムのことです。厚生労働省による「職業性ストレス簡易調査」の実施について、紙の調査票ではなく、システムを通じてPCやスマートフォンなどのデバイス上で実施でき、その調査結果の自動集計や管理を手軽に行うことができます。
調査結果に応じて、高ストレスと判定された対象者に対しては、医師への面接推奨や相談窓口につなげるといったアフターフォロー機能が備わっているシステムもあります。
注目されている背景と導入メリット
ストレスチェックが義務化されて以降、企業内で実施する際に集計や活用に関して手間を要するという課題があります。ストレスチェックシステムは、職業性ストレス簡易調査に規定されているチェックを効率的に実施し、集計を効率化してくれることから注目を集めています。
特にチェックから集計、フォローまで、一連の流れを半自動で運用できることは効率的な運用につながります。
ストレスチェックシステムによりストレスチェックをスムーズに実施できるようになることで、よりメンタルヘルスケアや職場環境の改善につながりやすくなるでしょう。
ストレスチェックシステム選定・導入のポイント
ストレスチェックシステムを選定する際や、導入する際には、次のポイントを押さえて実施することで、よりシステムを活用できると考えられます。
さまざまなタイプの中から自社に最適なものを選ぶ
ストレスチェックシステムには、さまざまなタイプがあるため、よく比較検討し、自社に合ったものを選びましょう。例えばストレスチェックを運用する側にとって効率性が重視されたタイプや、ストレスチェック実施後のフォローが充実しているタイプ、メンタルヘルス以外の健康状態の管理機能も備えるタイプなどがあります。
対応設問数やチェックを受けるデバイス、多言語対応を確認する
ストレスチェックシステムによって、対応している設問数やチェックを受ける際に使用できるデバイス、対応言語などは変わってきます。
特にPCだけではなく、スマートフォンやタブレットにも対応していれば、従業員が受検しやすくなります。このようなシステムを選定することで、定期的なチェックが抵抗なく浸透していくと考えられます。またオリジナルの設問が用意されているシステムなら、従業員の心理状態をより多角的にとらえられます。
セキュリティ面が徹底管理されているものを選ぶ
ストレスチェックの結果には個人情報が含まれるため、従業員個人と管理者だけが結果を共有できる仕組みが整っているなど、個人情報保護に配慮されたシステムを選定しましょう。
TOPPANのストレスチェックシステムの例
実際のストレスチェックシステムはどのようなものなのか、TOPPANが手がけるストレスチェックシステムを例に挙げてご紹介します。
専門家監修の個人向けケアに特長のあるシステム
TOPPANの企業向けストレスチェックシステムは、ハーバード大学医学部客員教授の根来秀行氏監修の下、メンタルヘルス不調のリスク判定と、個人向けケアの自動化を実現したストレスチェックシステムです。
新職業性ストレス簡易調査票80問と独自の31問で構成
ストレスチェックの調査票には、「職業性ストレス簡易調査票」57問に加えて、「ワーク・エンゲージメント」や「成長の機会」など、職場や個人レベルのポジティブな側面も測定することで、メンタルヘルス不調の一次予防につなげるストレス調査票である「新職業性ストレス簡易調査票」80問を採用しています。
さらに、この80問に加えて、本ストレスチェックシステムでは睡眠・運動・食事に関する生活習慣や、環境変化の実感の有無に関する独自の質問項目31問を追加しています。従来のストレス判定に加え、「コンディション」「環境変化の有無」の2つの指標により、コンディションの数値化とリスク(3段階)および環境変化の実感有無(2段階)を自動で判定します。従来のストレスチェックと比べて、幅広いチェックが可能になり、リスク発見や早期対策を促します。
高ストレス対象者へのフォローが充実
ストレスチェック結果から判明した高ストレス対象者に対しては、医師面接の推奨や各種相談窓口の案内を自動で行います。またコンディション要注意/危険の判定者には、根来教授が監修する動画コンテンツへの誘導を、環境変化を実感する人には、環境変化への対処法のアドバイスなどを自動で行います。これにより、適切な個人向けケアをより進めやすくなります。
TOPPANは2021年3月に本ストレスチェックシステムを開発し、サービス化に先立って、TOPPANの従業員を対象に2020年9月に試験運用を実施しました。その結果と知見を活かし、サービス化へと準備を進めています。
まとめ
ストレスチェックは多くの企業にとっての義務である一方で、その効率的な運用に課題があります。そこで効率化するための手段としてストレスチェックシステムの活用が進んでいます。ストレスチェックシステムは、多様な機能を持つため、自社に最適なシステムを見極めて導入するのをおすすめします。
TOPPANがサービス提供を予定しているストレスチェックシステムは、ご紹介したように、設問数が多く、チェック後のフォローが充実しています。ストレスチェックシステムの導入をご検討の際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、TOPPANでは他にも従業員のメンタルヘルスケアや健康増進に役立つサービスをご提供しております。詳細に関しましては、サービス紹介ページをご覧ください。
2023.11.28